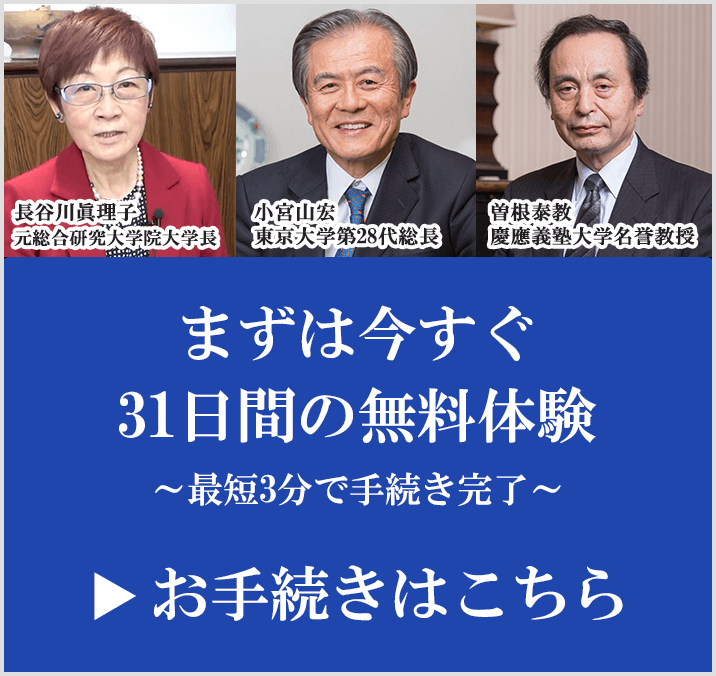●人種と道徳観念の関係を論じた『Natural History of Man』
カール・フォン・リンネの100年後にチャールズ・ダーウィンの時代になるのですが、その頃に書かれた『Natural History of Man』(1855年)という本があります。これは私がイギリスにいる時に古本屋さんで買ったものですが、『Natural History of Man』ですから「人間の自然史」ということになります。プリチャード(James Cowles Prichard)という医者が書いたのですが、とてもきれいな図版がたくさん入っています。今日は2巻あるうちの1巻しか持ってきていないのですが、きれいな図版がたくさんあって、このようにインドの人の格好や衣装が手書きの絵で入っていたりする、すごい本です。
『Natural History of Man』の副題が、「身体的、道徳的な作用が、人類の異なる部族において、どう変容を起こさせるかの影響についての考察」となっています。ですから、いろいろなことで、いろいろな人種やグループが変容していくが、そこには身体的なものと道徳的なものがあると考えているのです。
それはキリスト教の聖書の考えとして、神様が人間を創った時に道徳観念というものも人間に与えた、ということになっているので、人間なら必ず道徳観念があるはずだということなのです。そして、世界中で民族、部族、文化が違うと道徳も違うということが分かってきました。そうした場合に、体の様子が変わる、違うということと、道徳も変わるということを結び付けながら、世の中にたくさんいる、いろいろな文化の集団とか人種的なものを説明しようとしました。ですから、これも基本は結構、差別的です。
●19世紀、人類学の成立と先住民の扱い
そういう流れがずっとあって、人類学は人の頭の大きさを測ったりとか、肌の色を色見本のようなもので白いものから黒っぽいものまで並べて、この人種はどの色だということを調べたりするなど、いろいろなことをしてきたわけです。
そして、西欧諸国によって世界中が植民地化して征服されていった19世紀に、いわゆる人類学が成立するので、先住民に関する記録、標本収集、生体計測、つまり体を測る、頭を測るなどということが人類学の普通の手法になったのです。
そこで、19世紀の人類学成立期ですが、アメリカの人類学者は、ア...