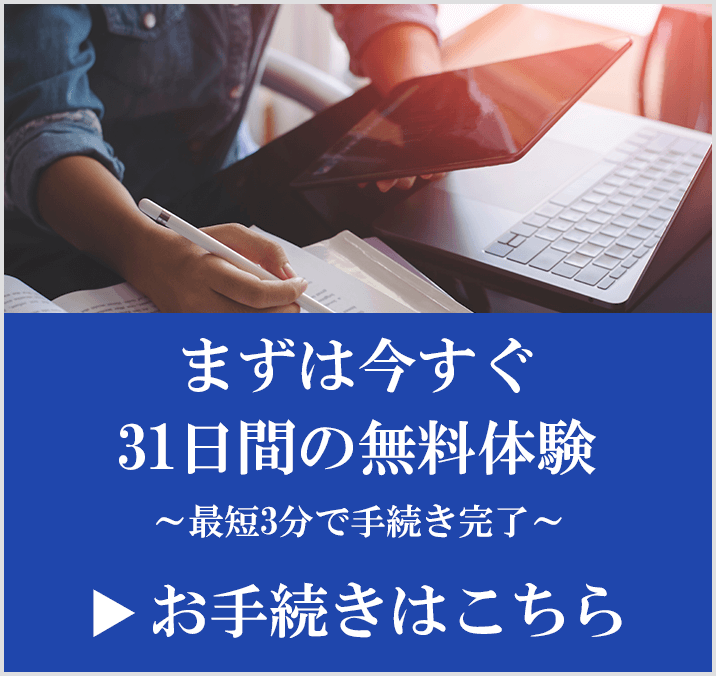●三国同盟成立前夜
今回から、大名同士の和睦・同盟の成立過程を掘り下げていきます。和睦と同盟の違いは非常に単純で、前者が停戦合意にとどまるのに対し、後者は相互不可侵だけでなく、軍事支援協定を含みます。
今回は、同盟成立のおおよその流れをみていきます。事例としては、甲斐の武田信玄、駿河の今川義元、相模の北条氏康が結んだ三国同盟です。これは三大名の勢力拡大を支えた同盟として非常に有名で、小説やドラマなどでは三大名が直接面談するシーンがしばしば描かれます。もっとも、三大名が一同に会したというのはフィクションで、実際にあった出来事ではありません。
●前提にある三者の対立構造の変化
さて、この三国同盟ですが、武田信玄の父親である武田信虎、今川義元の兄である今川氏輝、北条氏康の父である北条氏綱(いわゆる北条早雲こと伊勢宗瑞の嫡男といったほうが分かりやすいでしょう)といった父親たちの時代は、今川氏と北条氏が同盟を結んで、武田信虎と戦う、という対立構造にありました。
事態が急変したのは、今川氏輝の病死とその跡継ぎをめぐる御家騒動でした。この御家騒動は、北条氏綱の援軍を得た今川義元の勝利に終わるのですが、家督を継いだ今川義元が、突然武田信虎と同盟を結ぶのです。北条氏綱の反対を押し切っての強硬策でした。この理由はよく分からないのですが、今川義元が後になって書いた書状を読むと、どうも北条氏の援軍の振る舞いに何か問題があったようです。つまり、せっかく北条氏綱が送った援軍が、今川家の面目を潰すものと受け止められ、裏目に出たのです。
とはいえ、武田・今川同盟の成立には、今度は北条氏綱が黙っていられません。今までは一緒に武田信虎と戦ってきた経緯がある上、再三の反対を押し切っての同盟です。これでは自分の面目は丸潰れだ、北条氏綱もこう考えたようです。この結果、北条氏綱は今川義元との同盟を破棄し、今川氏の本国である駿河の東半分を占領してしまいます。この結果、武田・今川同盟対北条氏という新しい構図が出現しました。
●同盟破壊の原因は「顔を潰された」点にある
さて、ここで注目して頂きたいのは、同盟関係を破壊した原動力が何か、という点です。それは大名の面目でした。顔を潰されたと考えた大名は、今までの関係を破壊する方向に...