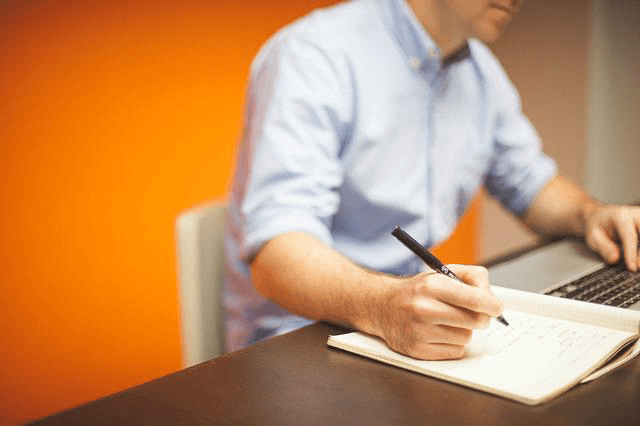●イーロン・マスクが描いた、理想を実現するための「マスタープラン」
―― 先ほどイーロン・マスクの生涯について先生にお話をいただきました。マスクが躍進できた理由として、先生は「マスタープラン」というものを掲げていますが、これはどういうことでしょうか。
桑原 マスクが言っていることは、世界を救うとか、人類を救うとか、非常に突拍子もない夢物語のような感じがするわけです。また、車の世界においても、これだけガソリン車が多い時代に、全てを電気自動車に替えていきたいと。まず普通に考えれば非常識な、誰が考えてもそれはできっこないよというビジョンを平気で掲げるわけです。しかし、マスクの場合は、理想論とか夢物語を語るのではなく、どうしたらそれが実現できるのかという構想、「マスタープラン」をきっちりと描くことができるのです。
その実行に関していえば、当然ある程度のズレなどはあるわけですが、長い目で見ていくと、言ったことを全て実現していくのです。
―― なるほど。
桑原 そこにマスクの凄さがあると思います。
だから、世の中にプランをつくるとか、構想をぶち上げることができる人はたくさんいますが、それを実現できる人はどれだけいるのかと。あるいは、そこに至るまでの、本当に緻密な計画を立てられる人がいるのかということでいえば、マスクは物理学の出身者ですから、非常に緻密な計画を立てることができます。それと同時に経済学の学位も持っています。そして、人を使い、お金を動かして実行していくことができるという、構想力と実行力。この2つを兼ね備えた、非常に稀有な人なのではないかと思います。
―― ロケットを打ち上げるにしても夢のような話ですが、きちんとプランが立っているということになるわけですね。
桑原 そうですね。例えば、本人の中では完全にテスラモーターズに関するマスタープランをちゃんと持っていたので、ここまで来られたと思います。
―― なるほど。それが2006年に発表した「マスタープラン」で、「マスタープラン2」が2016年ですね。
桑原 はい。10年後ですね。ですから、2006年に発表されたのが「マスタープラン1」となります。もともとは「秘密の」といわれていまし...