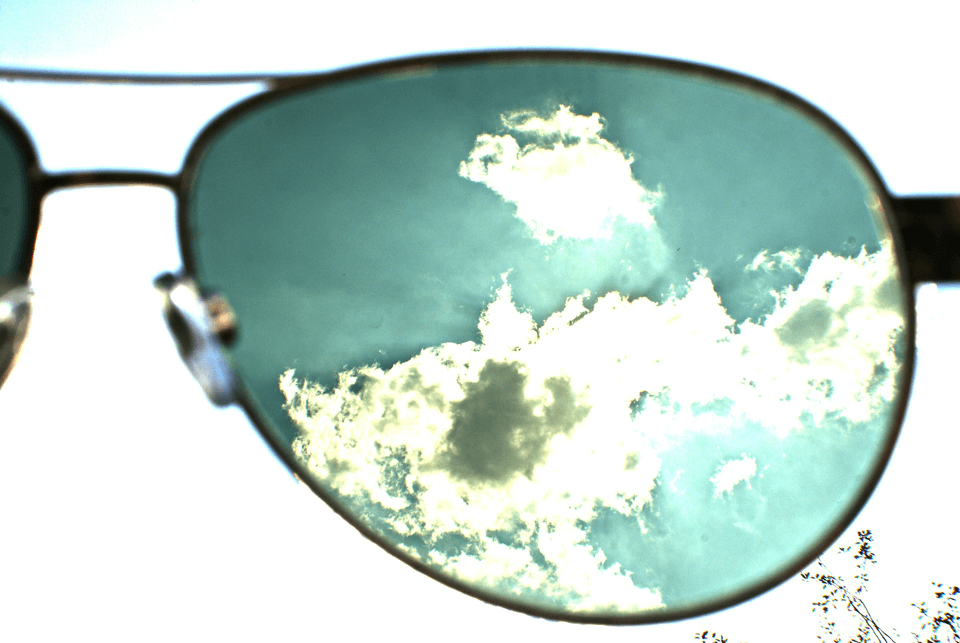●ブルーライトは、本当に目に悪いのか
筑波大学眼科教授の大鹿哲郎です。今日はまず、最近よくいわれる「ブルーライト」の影響についてお話しします。ブルーライトは本当は目に悪いのではないかといわれていますが、一方では実は良いのではないかという説もあります。
最近、蛍光灯に代わってLEDライトやスマホが非常に普及し、ブルーライトが世の中にあふれ、接する機会が増えています。その一方で、ブルーライトを選択的にカットし、目に入らないようにする眼鏡も売られています。このように、ブルーライトがどの程度目に影響するか、非常に関心を持たれている方も多いと思います。
ブルーライトとは、短波長から長波長にわたる可視光のうち短波長の方の光で、一番短いものをいいます。具体的には400~500ナノメートルほどの光です。光のエネルギーは短波長の方が強く、いろいろなものに影響が強く出る可能性があります。
●ブルーライトは、一日のリズムを作りだすのに必要だ
私たちはブルーライトをどこで感知しているのでしょうか。十数年前に網膜の新しい細胞が見つかりました。第四の網膜神経節細胞といわれるものです。私たちは、そこでブルーライトを感受しています。この細胞でブルーライトを感受すると、頭にその信号が伝わって、そこでメラトニンという物質が産生されます。このメラトニンが、体内時計をつかさどります。
人間の一日のリズムを、概日リズムといいます。朝起きて光を浴びると、ブルーライトを網膜で感知して、人間は朝になったことを感じます。逆に夜はだんだんと暗くなるのでブルーライトが少なくなり、次第に眠くなります。こうした一日のリズムをつかさどっているのがブルーライトであり、それを感知するのが第四の神経節細胞ということになります。
このリズムが乱れてしまうと、よく眠れなかったり、あるいは不眠症になったり、逆に昼間眠くなったりします。最近このブルーライトが増えているという話をしましたが、特に問題になるのは、夜寝る前にスマホや液晶テレビをずっと見たり、コンピュータの作業をしたりすることです。そうするとブルーライトが目に入るので、一日のリズムが狂ってしまい、寝付きが悪くなることは確かにあると思います。
しかし逆に、朝はブルーライトが必要です。それをカットして目に入れないのは、あまり良くありません。だから朝には...