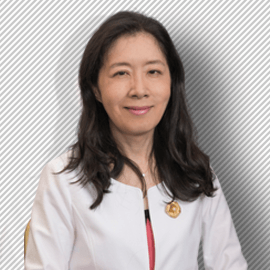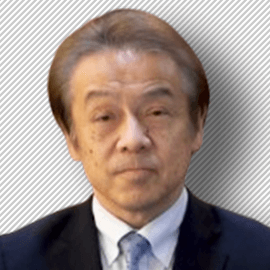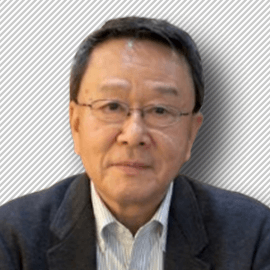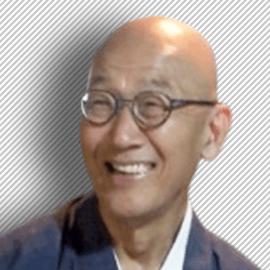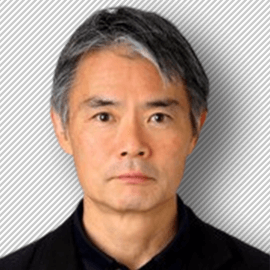ランキング
- 24時間
- 1週間
- 1ヵ月
逆境に対峙する哲学(10)遺産を交換する
台本もない。主語もない。専門分野も違う。3人の哲学者による2時間におよぶ「哲学カフェ」風鼎談講義は筋書きのない世界をさまよいながら、いよいよ最終回を迎えることに。カルヴィーノ、ナイチンゲール、本居宣長、プラトンの...
徳と仏教の人生論(5)陰陽と東洋思想を知ることの意味
宇宙や人生の本質について考察を深めていく今回の講義。前回に続く、宇宙がもう1つの宇宙のような存在をつくりたくて人間を創造したという話は非常に興味深い。陰陽(陰と陽)の両面を理解し、自然の摂理に根差した東洋思想を深...