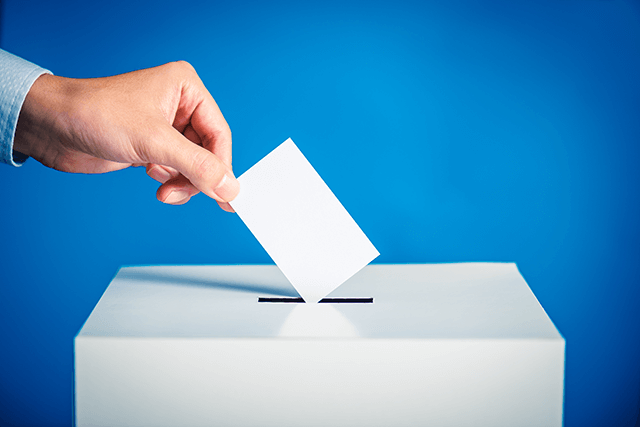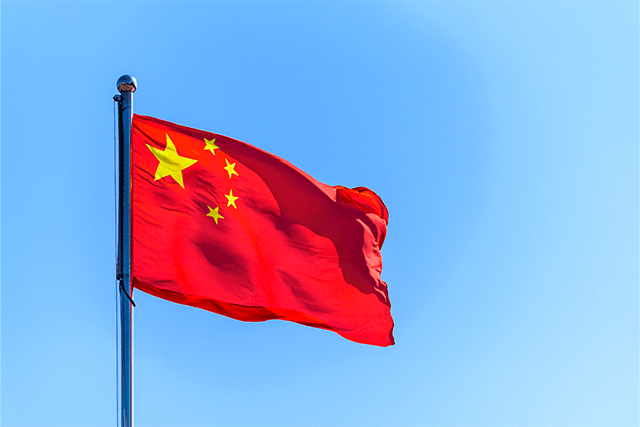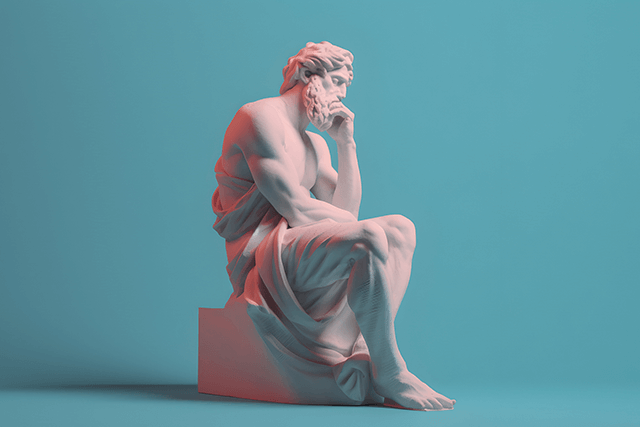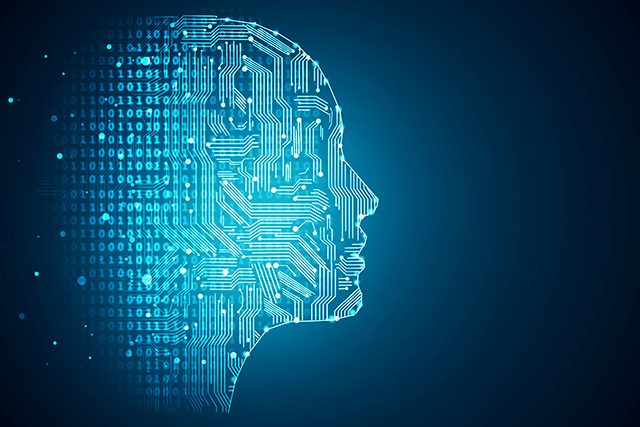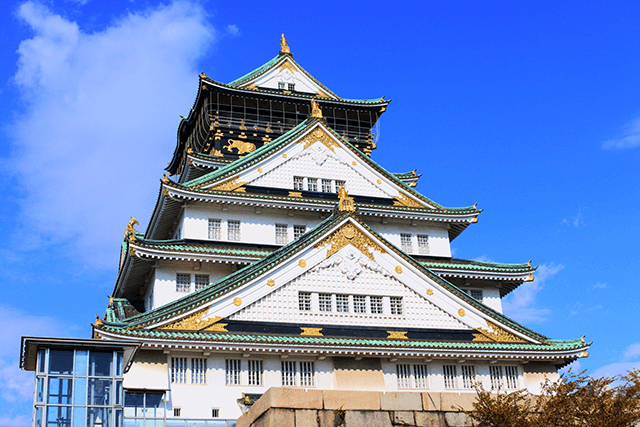日本の総人口は2080年まで減少が続く
人口減少と日本の未来(1)日本人口の歴史的推移と予測
「日本の歴史上、初めて急速に人口が減少する」――津田塾大学総合政策学部教授の森田朗氏によれば、日本はかつてないほどに人口が減少していくと予想される。いったいどういうことなのか。それに対してどのような対策が立てられ...
収録日:2018/03/29
追加日:2018/07/24
的外れな少子化対策…男女共同参画や待機児童より非婚・晩婚
第三次ベビーブームはなぜ起きなかったのか
日本には、これまで二度のベビーブームがあった。第一次ベビーブームは第二次世界大戦後、昭和22年から昭和24年に生まれた「団塊の世代」。第二次ベビーブームは、この世代が親となった昭和46年から昭和49年頃を指す。では、次...
収録日:2017/03/27
追加日:2017/04/27
日本の課題は「少子高齢化」ではなく「少子化」
2019年頭所感(2)日本の少子化対策と地方活性化のために
2019年の日本はどのような方針で臨むべきか。課題先進国から課題解決先進国としての姿を見せるには、国内の課題を解決する必要がある。中でも最重要の課題は急激に進む「少子化」への具体的な対策であろう。(全2話中第2話)
収録日:2018/11/21
追加日:2019/01/01
進化生物学から見る「母親の子殺し」の理由と歴史
進化生物学から見た少子化問題(1)近代以前の嬰児殺
「近代以前の社会は母親の子殺しに割と寛容だった」と、総合研究大学院大学理事で先導科学研究科教授の長谷川眞理子氏は語る。ヒトは昔から母親による子殺しが多いという。なぜかつて母親の子殺しは許されたのか。長谷川氏が進...
収録日:2016/11/25
追加日:2017/03/10
「逆・タイムマシン経営論」は本質を見抜くための方法論
「逆・タイムマシン経営論」で磨く経営センス(1)人口問題の本質
過去の新聞や雑誌を読み返すと、本質が見えてくることがある。例えば、昨今、大問題となっている人口減少は、実は戦前から、ついこの間まで、日本にとっては悲願だった。しかし、一度、それが達成されると、一転して人口減で日...
収録日:2020/09/18
追加日:2020/11/05