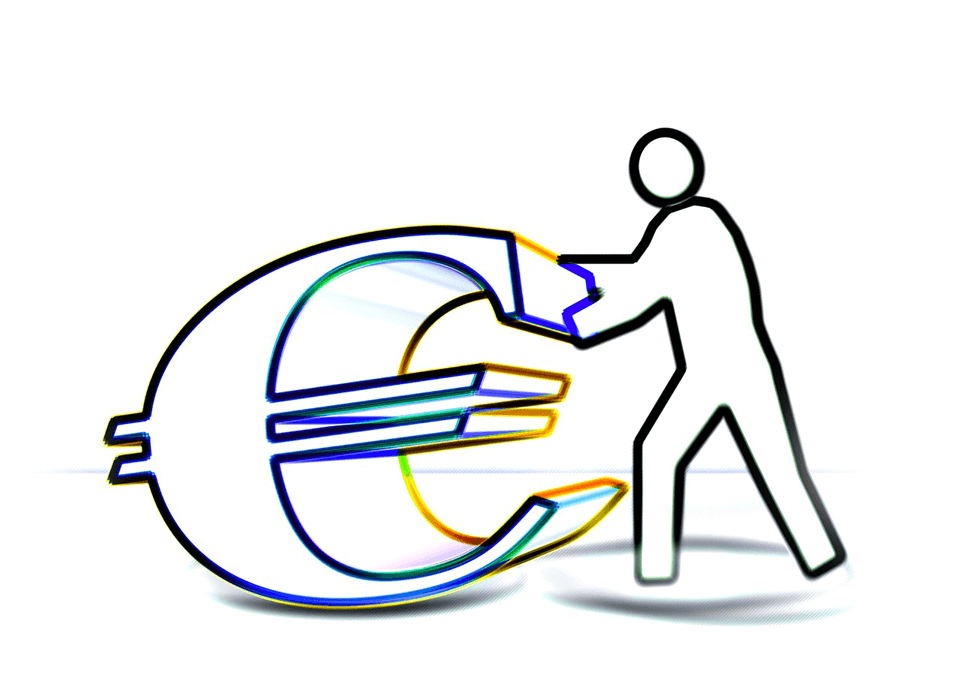●ユーロドルの上昇もそろそろ過剰領域という読み
一方で、ユーロドルはどうかというところに話を移しますが、今見ていただいているグラフは、赤い線で実際のユーロドルの動きを示しています。一方、青い折れ線グラフで示したものは、ファンダメンタルズモデルに基づくユーロドルの推計値ということになってきます。私はシティグループのG10FXストラテジーというグローバルなチームで働いているのですが、このモデル自体は実は私が作ったものです。私のロンドンの同僚も「このモデルはいいね」ということで、チームのモデルとして採用されています。ドル円のモデルももちろん採用されているのですが、このユーロドルのモデルもチームのモデルとして採用されているものなのです。
これに基づくと、現在の推計値が大体1ユーロ1.03ドルぐらいということになってきます。実際のユーロドルは前回申し上げました通り、1.04ドル台から足元1.11ドル、1.12ドルぐらいまで上がってきていて、ユーロ高になっています。ですから、このモデルの推計値よりも0.1ドルぐらい、ドル円でいうと10円ぐらい、今ユーロの過大評価になっているわけです。ドル円のモデルと同じように、ドル円に引き直せば10円程度のこういった過大評価、あるいは過小評価は、ひっきりなしに発生するものですから、今の状況に、あまり大きな違和感はありません。ただ、そろそろユーロドルの上昇は過剰領域に入ってきたかな、という見方をしているところです。
●ユーロドルモデル分析のための6つの変数
ユーロのモデルはどういった変数から成り立っているのかというと、前回示したモデル分析の一覧表の下段にあるユーロドルのモデルの決定係数や、t値、p値を見ていただくと、実はドル円よりも信頼度の高いモデルであることがお分かりいただけます。ユーロドルに関していえば、1番目から6番目まで6つの変数を持っています。1番目が米独長期金利差、つまり10年金利差で、これはインフレを加味しない名目金利差です。2番目がユーロドルのベーシススワップですが、これは通貨スワップ市場における米ドルのプレミアムと考えてください。3番目がFRB(連邦準備制度理事会)とECB(欧州中央銀行)のバランスシートを対比させたもので、これもドル円のモデル分析のところでもお話ししましたが、量的緩和の反映の部分です。4番目がアメリカとヨーロッパの経常収支格差で、こ...