テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
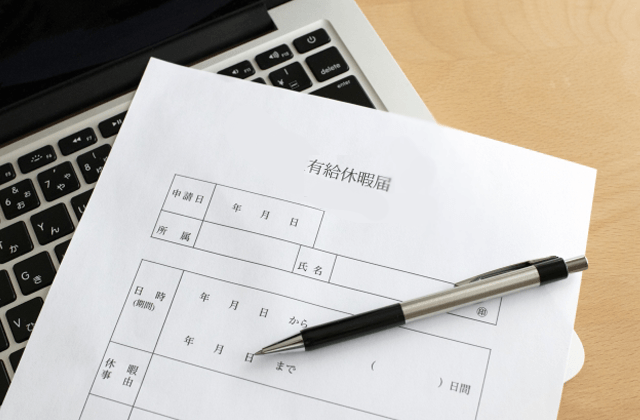
年間4兆円分が未消化!有給が取りにくい業界は?
2019年4月1日から、年次有給休暇の5日以上の取得が義務化されることになりました。これは「年10日以上有給休暇の権利がある従業員」について、「すべての企業」が対象です。義務なので、取りたくないと思っている人も取ることになります。これはなかなか踏み込んだ施策ではないでしょうか。
ということで今回は、有給の現状と今後の対策について、資料をもとに考えてみましょう。
では、日本の有給取得率はどれくらいなのかというと、2017年は51.1%という数字です。つまりほぼ半分、有給が20日あったとして、消化されているのは10日ということになります。海外の取得率は、ブラジル、フランス、スペイン、香港といった地域では100%。韓国で90%、アメリカで70%です。調査にある諸外国の中で日本はワースト1位という結果になっています。また、さかのぼって昭和60年(1985年)以降の有給消化率推移を見ると、平成4年(1992年)、5年(1993年)がピークで56.1%となっており、それ以降はずっと低調が続き、平成28年は49.4%です。大きな変化は起こっていません。こう見ると国が本腰を上げたのもわかります。
1位 卸売業・小売業:11.7日
2位 生活関連サービス業・娯楽業:11.6日
3位 建設業:11.2日
4位 宿泊業・飲食サービス業:10.9日
5位 教育・学習支援業:10.6日
小売、生活関連サービス、娯楽、建設、宿泊、飲食といったところが休めていないということがわかります。理由には、人手不足が大きく関連しているようです。人手を確保できなければ、一人あたりの業務量が増大してしまうことは容易に想像できます。このことは休めない理由からも読み取れます。休めない理由で最多なものは、「みんなに迷惑がかかると感じるから」です。ひとりひとりの従業員の負担がより重くなっている現実が見えてきます。
この点に関して第一生命経済研究所では、省力化・合理化によって修正してくことが可能なのではないか、と指摘しています。たとえば、小売業であればセルフレジを充実させる、AIの需要予測に基づく発注システムの整備などによって、ある程度自動化することができます。もちろん、こういったシステムを導入できない企業も多いでしょう。この点に関しては、アウトソーシングやマニュアル化を徹底することで見直すといった提案がなされています。
厚生労働省によると、例えば「年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができる(労働基準法第39条第6項)」とのこと。また、計画的付与によって成立した日程は、労働者の都合や会社側の都合では変更できないという性質もあるようです。
また、有給に関して特に管理側の注意点としては、理由を問うてはならない点もあります。有給はその理由によって可否を決定することはできません。無駄なトラブルにならないよう、こういった有給を巡るルールに関してもよく確認しておいたほうがいいかもしれません。
ということで今回は、有給の現状と今後の対策について、資料をもとに考えてみましょう。
2017年の有給未消化総額は4兆円
第一生命経済研究所の行った試算によると、2017年の有給未消化総額は4兆円相当ということが明らかにされています。この金額は、産業別に正社員の1日あたりの賃金を算出し、それを有給未消化分の日数と掛け合わせるといった計算によって導かれたものです。ただし、この計算には、非正規雇用(アルバイト・パート)の方々の数字は含まれていません。これらも入れるとさらに金額が大きくなることが考えられます。この数値は過去10年間を通してもさほど変わっていないとのことです。つまり、同研究所の資料にもとづけば、わたしたちは毎年4兆円分の有給を消滅させてきたということになります。では、日本の有給取得率はどれくらいなのかというと、2017年は51.1%という数字です。つまりほぼ半分、有給が20日あったとして、消化されているのは10日ということになります。海外の取得率は、ブラジル、フランス、スペイン、香港といった地域では100%。韓国で90%、アメリカで70%です。調査にある諸外国の中で日本はワースト1位という結果になっています。また、さかのぼって昭和60年(1985年)以降の有給消化率推移を見ると、平成4年(1992年)、5年(1993年)がピークで56.1%となっており、それ以降はずっと低調が続き、平成28年は49.4%です。大きな変化は起こっていません。こう見ると国が本腰を上げたのもわかります。
有給未消化数の多い業界
業界別で有給取得率を見てみましょう。以下、2017年の正社員における有給未消化日数の多い順に5位までです。(右の数字は有給未消化日数)。1位 卸売業・小売業:11.7日
2位 生活関連サービス業・娯楽業:11.6日
3位 建設業:11.2日
4位 宿泊業・飲食サービス業:10.9日
5位 教育・学習支援業:10.6日
小売、生活関連サービス、娯楽、建設、宿泊、飲食といったところが休めていないということがわかります。理由には、人手不足が大きく関連しているようです。人手を確保できなければ、一人あたりの業務量が増大してしまうことは容易に想像できます。このことは休めない理由からも読み取れます。休めない理由で最多なものは、「みんなに迷惑がかかると感じるから」です。ひとりひとりの従業員の負担がより重くなっている現実が見えてきます。
この点に関して第一生命経済研究所では、省力化・合理化によって修正してくことが可能なのではないか、と指摘しています。たとえば、小売業であればセルフレジを充実させる、AIの需要予測に基づく発注システムの整備などによって、ある程度自動化することができます。もちろん、こういったシステムを導入できない企業も多いでしょう。この点に関しては、アウトソーシングやマニュアル化を徹底することで見直すといった提案がなされています。
「計画的付与」という方法
この4月からの有給義務化を受けて、法律上「計画的付与」と呼ばれるという方法を取るところもあるようです。これは会社と労働者の代表が協定を結ぶことによって決まるものです。たとえば、一斉消化日を設けたり、社員をグループに分けて、グループごとに決められた休暇を取得したり、社員個人があらかじめ有給付与計画表をつくって消化していくものなどがあります。ただし、この「計画的付与」に相当する有給は、個人の持ち日数の5日を超える部分となっています。厚生労働省によると、例えば「年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15日までを計画的付与の対象とすることができる(労働基準法第39条第6項)」とのこと。また、計画的付与によって成立した日程は、労働者の都合や会社側の都合では変更できないという性質もあるようです。
また、有給に関して特に管理側の注意点としては、理由を問うてはならない点もあります。有給はその理由によって可否を決定することはできません。無駄なトラブルにならないよう、こういった有給を巡るルールに関してもよく確認しておいたほうがいいかもしれません。
<参考サイト>
・Economic Trends 第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2018/ito190225.pdf
・年次有給休暇取得率の推移(男女計,男女別)|内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-03.html
・年次有給休暇の計画的付与について【労働基準法第39条関係】|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
・Economic Trends 第一生命経済研究所 調査研究本部 経済調査部
http://group.dai-ichi-life.co.jp/dlri/pdf/macro/2018/ito190225.pdf
・年次有給休暇取得率の推移(男女計,男女別)|内閣府男女共同参画局
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h30/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-03-03.html
・年次有給休暇の計画的付与について【労働基準法第39条関係】|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










