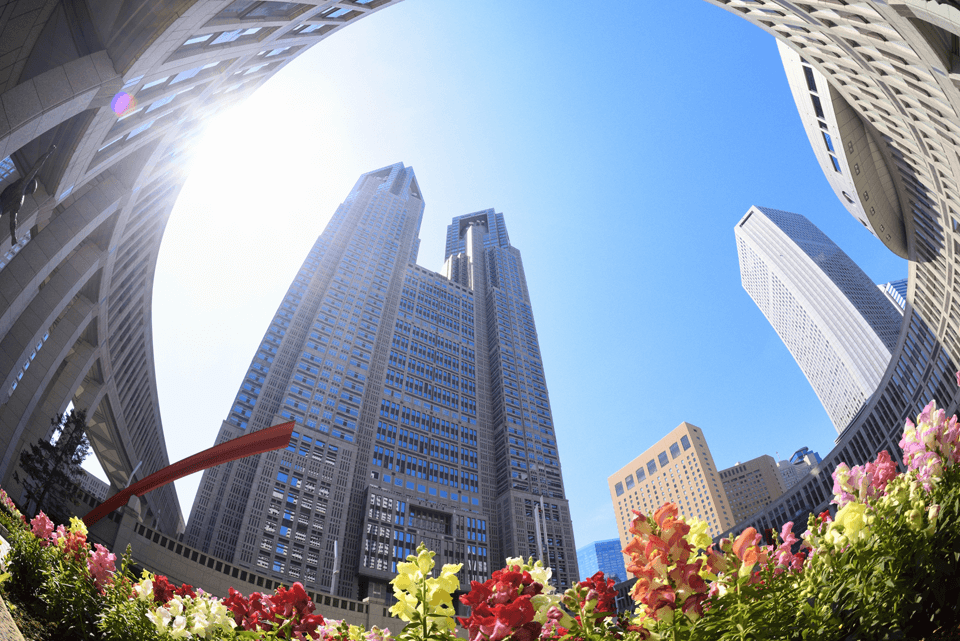●都議会選挙の結果を理解する3つの観点
都議会選挙が終わりました。この結果をどのように理解すればいいのか、大きく3つの観点からお話します。1つ目は、選挙結果をどう解釈するのかということです。2つ目は、今回出てきた、二元代表制という問題です。知事が政党を作れば、チェック機能が失われるのではないか、と言われています。3つ目は、国政および国政選挙への影響です。この3点に絞って、お話します。
●都民ファーストの会が勝ち、自民党が大幅に負けた
第1に、都民ファーストの会は、なぜ圧勝したのでしょうか。公認候補が50人いましたが、島しょ部で1人落選したのを除いて、その他は全員当選しました。しかも上位で勝っています。これは圧勝と言っていいでしょう。小選挙区、つまり1人区だけで圧勝だったわけではありません。例えば、世田谷区のような8議席の選挙区でも、勝っています。
この点において、フランスのエマニュエル・マクロン大統領の共和国前進(アン・マルシェ!)が議席ゼロの状態から過半数を取ったという点と非常によく似ています。経験不足の新人が多数いるという点も、似ています。政策を見てみると、ポイントを外しているわけではありませんが、十分練られてはいません。
今回はっきりしたのは、都民ファーストの会が勝ったというだけではなく、自民党が大幅に負けたということです。原因は三重苦・四重苦などと言われています。加計学園問題があり、その中で下村博文氏や萩生田光一氏との関係、あるいは稲田朋美防衛大臣や豊田真由子議員の発言などが、選挙で足を引っ張ったということでしょう。国政での失言などが都議会選挙に影響を与えた、と理解されています。いずれにせよ、自民党のつまずきは明白です。
いつでも与党に付くのかという批判もありますが、公明党は与党に付きました。民進党は議席を減らしました。あるいはむしろ、民進党から都民ファーストの会に移った人もかなりいるでしょう。維新の会は東京では議席を取れず、1議席だけでした。
こう見ると、予想通りの結果です。公明党を加えて、過半数は超えるだろうと見られていました。無所属で、後から公認された6人を含めて、55名です。ただし、経験不足の人がたくさんいるという問題があります。
●二元代表制という表現は正しくない
第2に、二元代表制において、知事が党を持ち、党が圧勝すると...