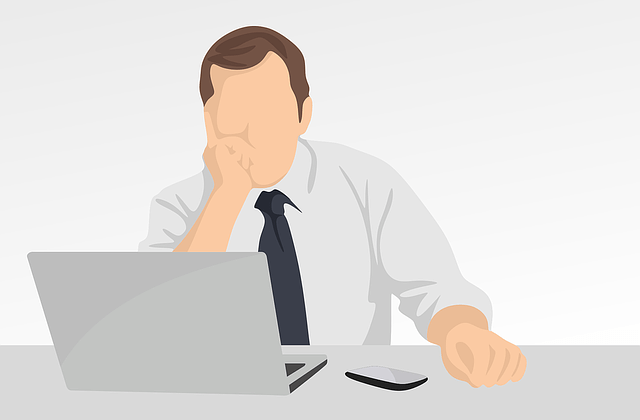●若者の「就職」意識が変わっている
柳川 少なくとも若い世代に関しては、近年かなり急速に就職の意識が変わってきているのだろうという気がしています。大手の企業に行くのではなく、ベンチャーに行くなり、自分で会社を興そうという人が、うちの大学(東京大学)でも割と増えています。構造的にはだいぶ変わってくるのではないかと思います。
―― ベトナム戦争が終了した後、大企業がリストラばかりしているうちに、ハーバード、コロンビア、スタンフォード大学の出身者が自分でベンチャーを始めたことで、流れが変わりました。あれと同じようなこととして、特に伊藤元重先生のゼミや植田和男先生のゼミを見ていると、30代前半で自分の組織をつくっている人が出てきています。あれは、いいことですよね。
柳川 いいことだと思います。特に今は、少人数のベンチャーこそ、イノベーションや生産性の向上がうまくいく時代だと思います。大企業がうまくいかなかったという面もありますが、そういう若い小さな会社に、非常に伸びしろがある。社会全体の環境も、それにうまく合わせてつくっていくことだと思います。
―― そうすると、スモールサイズ(小さな組織)のほうが自分の目は届きやすいですし、スモールサイズでの開発・製造・販売を早回しするほうが強いですよね。
柳川 やはり今の時代は、小さな組織のほうが圧倒的にメリットが出る時代だと思います。昔は、大きくないとできないことが結構あって、大きな企業でないと、なかなかお金が借りられず、資金調達ができなかったり、非常に大きな設備投資をしないとビジネスにならなかったりしました。今は、小さな組織でも資金調達がしっかりできますし、別のところに生産委託をすれば、自分たちの思っていることをしっかり社会に示し、売っていくことができるようになっています。
プラットフォーム企業ができてきた結果として、技術だけではなく、いろいろな経済構造の変化が起こりました。ある意味、組織のあり方についてもずいぶん変わってきていて、イノベーションを生み出すエンジンがどこから出てくるのか、という構造が世界全体で変わっているということです。その波が、日本にやってきていると考えたほうがいいと思います。
●大組織の難しさをカバーする小さな会社の面白さ
―― となると、むしろ意思決定が早くて、言語が通じるというか、言語体...