テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
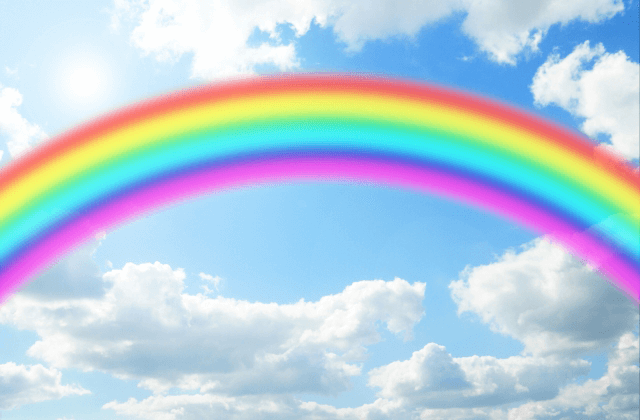
虹は七色ではない?世界で違う色の見方
空中に浮かぶ水滴に太陽光が屈折・反射することによって、地表から空にかけて現れる、美しい色彩の円弧状の光を「虹」といいます。
このうちの“美しい色彩”は、虹の魅力の一つといえます。
現代日本では「虹は7色」が一般的で、さらに虹の7色の区別は「赤(せき)・橙(とう)・黄(おう)・緑(りょく)・青(せい)・藍(らん)・紫(し)」とされています。しかし、「虹は7色」は、世界共通の見方ではありません。
では世界では、虹をどのような色で見ているのでしょうか。
【虹色・色数・国(文化)】
赤・橙・黄・黄緑・緑・青・藍・紫(8色):アフリカ(アル部族)
赤・橙・黄・緑・青・藍・紫(7色):日本、オーストラリア、フランス
赤・橙・黄・緑・青・紫(6色):アメリカ、イギリス
赤・黄・緑・青・紫(5色):ロシア、(ドイツ)
赤・橙・黄・緑・青(5色):ベルギー、(ドイツ)
赤・黄・緑・青(4色):インドネシア(フローレス島)
赤・黄・紫(3色):台湾(ブヌン族)
赤・黒(2色):南アジア(バイガ族)
※色の並び順は、天から地(外側から内側)。
※同じ国であっても、地域によっては異なる場合もある。
※ドイツのように、文献や資料によって色数が同じ場合でも近似の色があいまいな場合もある。
なお、赤から紫まで光が色分かれする理由はそれぞれの色波長が違うからで、中間が黄色になります。そして、赤から紫にかけて波長は短くなり、短い方が曲がりやすくなります。地上に届く太陽光放射の色波長のうち可視光線は一部となりますが、可視光線を外れた波長の、赤の光の先は「赤外線」に、紫の光の先は「紫外線」となっています。
実験によって“色の正体は光”ということを証明したニュートンですが、さらに光の波長を「赤・橙・黄・緑・青・藍・菫(紫)」の7色に分類しました。ちなみにニュートンが7色とした背景には、音階があるといわれています。ニュートンが活躍した当時、音楽は科学的な学問として、西洋の学術界で重要視されていたからです。
ニュートンが“光≒太陽光≒可視光線≒虹”を7色と定義するまで、西洋では一般的に、虹は赤・緑・青の3色や、赤・黄・緑・青・紫の5色とされていました。ニュートンは5色のうちの、青と紫の間に藍を、赤と黄の間に橙の中間色を追加しました。結果として「虹は7色」が、現在に至るまで流布することとなりました。
しかし、虹を見てもわかるように、スペクトルにははっきりとした色の境界はなく、グラデーションとなっています。同様に、スペクトル実験の結果からもわかりますが、光の色が区別されているわけではありません。ニュートンも、実際に明確に分光された7色を見たわけではないでしょう。
そして、例えば色見本やカラーチャート、多色の折り紙や揃いの色鉛筆を見たことのある人などは体験的にわかりやすいかと思いますが、色のグラデーションは見る人によって、無数の色を取り出すことも、またまとめて表現することもできます。
つまり、黄と緑の間を“黄緑”とすることも、逆に青と藍を“青”とまとめることも可能となってきます。実際に可視光線のスペクトルに虹の7色を並べて色味ごとに波長を区切ってみると、極端に青と藍の幅が狭く、7色よりも赤・橙・黄・緑・青・紫の6色の方が、違和感がないようにも映ります。
つまり、バーフィールドおよび渡部は、ゲーテの「色彩は、その色を見る人間があって、はじめて成立する」という視点こそが、光の現象を美しい虹として捉えていること、さらに虹を見る主観は人それぞれであったり国や文化の常識によって違ったり、かつ各人の美学や主観には異なった歴史や文化的背景があることを示唆しつつ、尊重しています。
もちろん、現象としての虹を見るためには視力が必要です。また、ニュートンのように科学的な定義をすることも大切ですし、実際に科学的な反応によって、虹という現象は発生しています。しかし、誰しも自己の視力の範囲でしか情報としての映像を捉えることはできません。そのうえで、像を結んだ現象をどのように認知し、さらにはどうやって表現していくのかは、歴史や文化的な背景、そしてなにより個人によって違います。
とはいえ、色数の違いはあれども、虹という美しい光の現象に、世界中の各地でそれぞれの文化を背景とした名前をつけたこと。その行為から、虹をみたときの心の高揚が、古今東西あったであろうことがうかがえてきます。
なお、虹の要件には、空中の水滴と太陽光の屈折・反射があるため、1)発生機会は雨上がりが多く、2)太陽と反対側に発生し、また3)太陽高度が42度以上のときは地平線に潜ってしまうため空に現れず、4)太陽高度が低いほど高いところに大きくできる――、こととなります。
要件があったそのときは、ぜひ空を見上げ、美しい虹を探してみてください。
このうちの“美しい色彩”は、虹の魅力の一つといえます。
現代日本では「虹は7色」が一般的で、さらに虹の7色の区別は「赤(せき)・橙(とう)・黄(おう)・緑(りょく)・青(せい)・藍(らん)・紫(し)」とされています。しかし、「虹は7色」は、世界共通の見方ではありません。
では世界では、虹をどのような色で見ているのでしょうか。
世界で違う!虹の色と色数
まずは各国の、一般的な虹の色と色数をみてみましょう(なお、同じ国であっても、地域によっては異なる場合もあります)。【虹色・色数・国(文化)】
赤・橙・黄・黄緑・緑・青・藍・紫(8色):アフリカ(アル部族)
赤・橙・黄・緑・青・藍・紫(7色):日本、オーストラリア、フランス
赤・橙・黄・緑・青・紫(6色):アメリカ、イギリス
赤・黄・緑・青・紫(5色):ロシア、(ドイツ)
赤・橙・黄・緑・青(5色):ベルギー、(ドイツ)
赤・黄・緑・青(4色):インドネシア(フローレス島)
赤・黄・紫(3色):台湾(ブヌン族)
赤・黒(2色):南アジア(バイガ族)
※色の並び順は、天から地(外側から内側)。
※同じ国であっても、地域によっては異なる場合もある。
※ドイツのように、文献や資料によって色数が同じ場合でも近似の色があいまいな場合もある。
「虹は7色」の元祖はニュートン?
人間の目に見える光を「可視光線」といいます。太陽光をプリズムで分光すると、“赤から紫までの連続した色で構成された光の帯”が見えます。この“目に見える光の色の帯”すなわち“可視光線の連続した色”を「スペクトル」といい、物理や科学の用語として定着化させた人は、科学者のニュートンといわれています。なお、赤から紫まで光が色分かれする理由はそれぞれの色波長が違うからで、中間が黄色になります。そして、赤から紫にかけて波長は短くなり、短い方が曲がりやすくなります。地上に届く太陽光放射の色波長のうち可視光線は一部となりますが、可視光線を外れた波長の、赤の光の先は「赤外線」に、紫の光の先は「紫外線」となっています。
実験によって“色の正体は光”ということを証明したニュートンですが、さらに光の波長を「赤・橙・黄・緑・青・藍・菫(紫)」の7色に分類しました。ちなみにニュートンが7色とした背景には、音階があるといわれています。ニュートンが活躍した当時、音楽は科学的な学問として、西洋の学術界で重要視されていたからです。
ニュートンが“光≒太陽光≒可視光線≒虹”を7色と定義するまで、西洋では一般的に、虹は赤・緑・青の3色や、赤・黄・緑・青・紫の5色とされていました。ニュートンは5色のうちの、青と紫の間に藍を、赤と黄の間に橙の中間色を追加しました。結果として「虹は7色」が、現在に至るまで流布することとなりました。
しかし、虹を見てもわかるように、スペクトルにははっきりとした色の境界はなく、グラデーションとなっています。同様に、スペクトル実験の結果からもわかりますが、光の色が区別されているわけではありません。ニュートンも、実際に明確に分光された7色を見たわけではないでしょう。
そして、例えば色見本やカラーチャート、多色の折り紙や揃いの色鉛筆を見たことのある人などは体験的にわかりやすいかと思いますが、色のグラデーションは見る人によって、無数の色を取り出すことも、またまとめて表現することもできます。
つまり、黄と緑の間を“黄緑”とすることも、逆に青と藍を“青”とまとめることも可能となってきます。実際に可視光線のスペクトルに虹の7色を並べて色味ごとに波長を区切ってみると、極端に青と藍の幅が狭く、7色よりも赤・橙・黄・緑・青・紫の6色の方が、違和感がないようにも映ります。
ゲーテに鑑みる「虹を“美しく”感じる心」
英語学者・評論家の渡部昇一は、言語学者のオーウェン・バーフィールドの「歴史というものは虹のようなものである。それは近くに寄って、くわしく見れば見えるというものではない。近くに寄れば、その正体は水玉にすぎない」という言葉を紹介し、さらに「バーフィールドは、ゲーテの『色彩論』のほうが、ニュートンの『光学』よりも虹の現象をよく説明するとしている」と述べています。つまり、バーフィールドおよび渡部は、ゲーテの「色彩は、その色を見る人間があって、はじめて成立する」という視点こそが、光の現象を美しい虹として捉えていること、さらに虹を見る主観は人それぞれであったり国や文化の常識によって違ったり、かつ各人の美学や主観には異なった歴史や文化的背景があることを示唆しつつ、尊重しています。
もちろん、現象としての虹を見るためには視力が必要です。また、ニュートンのように科学的な定義をすることも大切ですし、実際に科学的な反応によって、虹という現象は発生しています。しかし、誰しも自己の視力の範囲でしか情報としての映像を捉えることはできません。そのうえで、像を結んだ現象をどのように認知し、さらにはどうやって表現していくのかは、歴史や文化的な背景、そしてなにより個人によって違います。
とはいえ、色数の違いはあれども、虹という美しい光の現象に、世界中の各地でそれぞれの文化を背景とした名前をつけたこと。その行為から、虹をみたときの心の高揚が、古今東西あったであろうことがうかがえてきます。
なお、虹の要件には、空中の水滴と太陽光の屈折・反射があるため、1)発生機会は雨上がりが多く、2)太陽と反対側に発生し、また3)太陽高度が42度以上のときは地平線に潜ってしまうため空に現れず、4)太陽高度が低いほど高いところに大きくできる――、こととなります。
要件があったそのときは、ぜひ空を見上げ、美しい虹を探してみてください。
<参考文献・参考サイト>
・『虹の図鑑』(武田康男文・写真、緑書房)
・『<図説>虹の文化史』(杉山久仁彦著、河出書房新社)
・7色の光が織りなす「虹」 国によって見え方が違う?
https://weathernews.jp/s/topics/201807/240205/
・ニュートンが虹の色を「7色だ」と決めたって、ほんと?
https://global.canon/ja/technology/kids/mystery/m_04_09.html
・『日本、そして日本人の「夢」と矜持(ほこり)』(渡部昇一著、イースト・プレス)
・『光学』(ニュートン著、島尾永康訳、岩波文庫)
・『色彩論』(ゲーテ著、菊地栄一訳、岩波文庫)
・『虹の図鑑』(武田康男文・写真、緑書房)
・『<図説>虹の文化史』(杉山久仁彦著、河出書房新社)
・7色の光が織りなす「虹」 国によって見え方が違う?
https://weathernews.jp/s/topics/201807/240205/
・ニュートンが虹の色を「7色だ」と決めたって、ほんと?
https://global.canon/ja/technology/kids/mystery/m_04_09.html
・『日本、そして日本人の「夢」と矜持(ほこり)』(渡部昇一著、イースト・プレス)
・『光学』(ニュートン著、島尾永康訳、岩波文庫)
・『色彩論』(ゲーテ著、菊地栄一訳、岩波文庫)
人気の講義ランキングTOP20










