テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
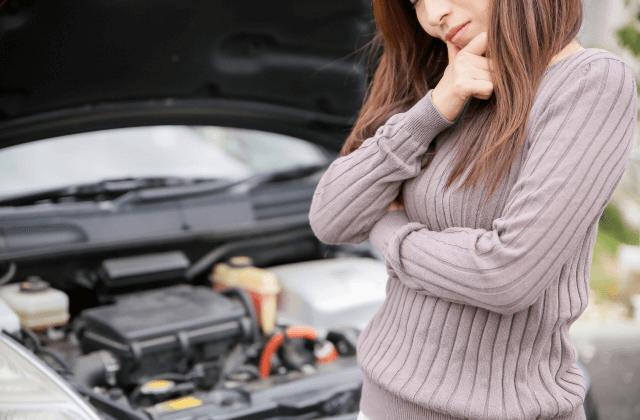
高速道路で最も多いトラブルランキング
長距離の出張や行楽で高速道路を利用する機会が増えた人も多いかと思います。久しぶりの長距離ドライブは、快適の裏側に潜むリスクへの備えを万全に。高速道路で目立つトラブルについて、国土交通省の発表データなどでおさらいしておきましょう。
高速道路上で最も多い故障部位はタイヤ(53.5%)。パンクやバースト(破裂)のほか、空気圧不足により、最悪の場合は事故、そこまでいかなくてもロードサービス(JAFなど)の出動を要請する人が絶えません。
一般道路で起こるタイヤのトラブルは31%程度ですが、高速道路では53.5%。高速連続走行がタイヤへの過負荷をもたらし、空気圧が低下しているとタイヤのたわみ(変形)につながります。大きなたわみが連続すると、タイヤは発熱し、最終的にはバーストしてしまいます(スタンディングウェーブ現象)。
日本自動車タイヤ協会(JATMA)の調査によると、高速道路走行中の乗用車の4分の1が空気圧不足という結果も出ています(2015~2019年に高層道路SAで実施)。釘などの異物が刺さるのは避けようがないアクシデントですが、空気圧点検は1か月程度で定期的に行いましょう。加えてひび割れやキズ、溝の深さなどもチェックしてもらうと安心です。
・2位 冷却水のトラブル
とくに渋滞の多くなる季節に起こりがちなのが、エンジンのオーバーヒート。近年では自動車メーカーによるオーバーヒート対策が施され、真夏の渋滞シーズン以外にはめったに見られなくなったといいます。
それでもデータでは、高速道路上トラブルの5.0%が冷却水によるもの。ラジエータやゴムホース、冷却水を溜めるタンクの劣化などにより冷却水漏れが起こったり、汚損したりすることがあるからです。とくに水量が減った場合は冷却水の温度が上がりやすく、エンジンをうまく冷やせなくなって、走行に支障をきたします。
・3位 潤滑油のトラブル
一般道路ではほとんど意識することのないエンジンオイルも、高速道路上のトラブルでは第3位(3.3%)となります。そのほとんどがオイル交換を怠っていたためのオイル不良です。劣化したオイルでは潤滑や冷却などの機能が低下し、エンジン内部の汚れも除去できないため、エンジン・トラブルにつながるのです。エンジンオイルの量は、高速走行の前に必ずチェックしておきたい項目の一つです。
・4位 オルタネータのトラブル
オルタネータは車の発電機。エンジンの回転を伝達して発電し、走行中に必要な電力を共有し、バッテリーへの充電を行います。オルタネータに異常が出ると、走行中にバッテリー警告灯が点灯したり、カーナビやメーターパネルなどの照明が消えたりします。また、バッテリー交換をしたばかりなのにバッテリーが上がってしまうときもオルタネータの劣化が考えられます。
定期点検時以外は気にすることのないパーツですが、最悪の場合走行不能になってしまうことも。高速道路上でのトラブル発生率は2.6%程度ですが、とくに中古で購入した場合は注意が必要です。
・5位 トランスミッション(AT)のトラブル
今や国産乗用車の99%がAT(オートマチックトランスミッション)になっていると言われます。変速機とも呼ばれ、車を動かしたり停めたりする動作の土台になる大切なパーツ。めったに故障や不具合を起こすことはありませんが、警告灯ランプが点灯する、変速がうまくいかないなどの症状を起こすことも。高速道路上でのトラブル発生は5位(1.7%)に上ります。
同乗者をガードレールの外側へ避難させてから、発煙筒や停止表示器材を車から50メール以上後方に置きます。ただし燃料漏れなどで引火する危険がある場合は、発煙筒は使いません。
後続車に対するアラートが表示できたら、ドライバーもガードレールの外側へ。高速道路には1キロおきに非常電話が設置されているので、それを使うか携帯電話で救援を依頼します。携帯電話でロードサービスを依頼する場合は、路肩にあるキロポストの数字を伝えるようにしましょう。
以上、やむをえず駐停車する際の注意として、「路上に立たない」「車内に残らない」「安全な場所に避難する」の3原則を警察庁は呼びかけています。
高速道路で多いトラブルベスト5 そのシチュエーションと原因
・1位 タイヤのトラブル高速道路上で最も多い故障部位はタイヤ(53.5%)。パンクやバースト(破裂)のほか、空気圧不足により、最悪の場合は事故、そこまでいかなくてもロードサービス(JAFなど)の出動を要請する人が絶えません。
一般道路で起こるタイヤのトラブルは31%程度ですが、高速道路では53.5%。高速連続走行がタイヤへの過負荷をもたらし、空気圧が低下しているとタイヤのたわみ(変形)につながります。大きなたわみが連続すると、タイヤは発熱し、最終的にはバーストしてしまいます(スタンディングウェーブ現象)。
日本自動車タイヤ協会(JATMA)の調査によると、高速道路走行中の乗用車の4分の1が空気圧不足という結果も出ています(2015~2019年に高層道路SAで実施)。釘などの異物が刺さるのは避けようがないアクシデントですが、空気圧点検は1か月程度で定期的に行いましょう。加えてひび割れやキズ、溝の深さなどもチェックしてもらうと安心です。
・2位 冷却水のトラブル
とくに渋滞の多くなる季節に起こりがちなのが、エンジンのオーバーヒート。近年では自動車メーカーによるオーバーヒート対策が施され、真夏の渋滞シーズン以外にはめったに見られなくなったといいます。
それでもデータでは、高速道路上トラブルの5.0%が冷却水によるもの。ラジエータやゴムホース、冷却水を溜めるタンクの劣化などにより冷却水漏れが起こったり、汚損したりすることがあるからです。とくに水量が減った場合は冷却水の温度が上がりやすく、エンジンをうまく冷やせなくなって、走行に支障をきたします。
・3位 潤滑油のトラブル
一般道路ではほとんど意識することのないエンジンオイルも、高速道路上のトラブルでは第3位(3.3%)となります。そのほとんどがオイル交換を怠っていたためのオイル不良です。劣化したオイルでは潤滑や冷却などの機能が低下し、エンジン内部の汚れも除去できないため、エンジン・トラブルにつながるのです。エンジンオイルの量は、高速走行の前に必ずチェックしておきたい項目の一つです。
・4位 オルタネータのトラブル
オルタネータは車の発電機。エンジンの回転を伝達して発電し、走行中に必要な電力を共有し、バッテリーへの充電を行います。オルタネータに異常が出ると、走行中にバッテリー警告灯が点灯したり、カーナビやメーターパネルなどの照明が消えたりします。また、バッテリー交換をしたばかりなのにバッテリーが上がってしまうときもオルタネータの劣化が考えられます。
定期点検時以外は気にすることのないパーツですが、最悪の場合走行不能になってしまうことも。高速道路上でのトラブル発生率は2.6%程度ですが、とくに中古で購入した場合は注意が必要です。
・5位 トランスミッション(AT)のトラブル
今や国産乗用車の99%がAT(オートマチックトランスミッション)になっていると言われます。変速機とも呼ばれ、車を動かしたり停めたりする動作の土台になる大切なパーツ。めったに故障や不具合を起こすことはありませんが、警告灯ランプが点灯する、変速がうまくいかないなどの症状を起こすことも。高速道路上でのトラブル発生は5位(1.7%)に上ります。
高速上でトラブルが起きた際に気を付けることは
高速道路上でトラブルが発生すると焦ってしまいます。まずはハザードランプを点灯させ、路肩に寄せたり、できるだけ広いところまで移動します。同乗者をガードレールの外側へ避難させてから、発煙筒や停止表示器材を車から50メール以上後方に置きます。ただし燃料漏れなどで引火する危険がある場合は、発煙筒は使いません。
後続車に対するアラートが表示できたら、ドライバーもガードレールの外側へ。高速道路には1キロおきに非常電話が設置されているので、それを使うか携帯電話で救援を依頼します。携帯電話でロードサービスを依頼する場合は、路肩にあるキロポストの数字を伝えるようにしましょう。
以上、やむをえず駐停車する際の注意として、「路上に立たない」「車内に残らない」「安全な場所に避難する」の3原則を警察庁は呼びかけています。
<参考サイト>
・政府広報オンライン:高速道路運転中にまさかの事故!高速道路の安全ドライブ3つのポイント
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/5.html
・JATMA:タイヤの空気圧
https://www.jatma.or.jp/tyre_user/tyrepressure.html
・JAF:クルマなんでも質問箱
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-traffic-accident/faq103
・警察庁:高速道路での緊急事態
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/highway/index.html
・政府広報オンライン:高速道路運転中にまさかの事故!高速道路の安全ドライブ3つのポイント
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201307/5.html
・JATMA:タイヤの空気圧
https://www.jatma.or.jp/tyre_user/tyrepressure.html
・JAF:クルマなんでも質問箱
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-accident/subcategory-traffic-accident/faq103
・警察庁:高速道路での緊急事態
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/highway/index.html
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










