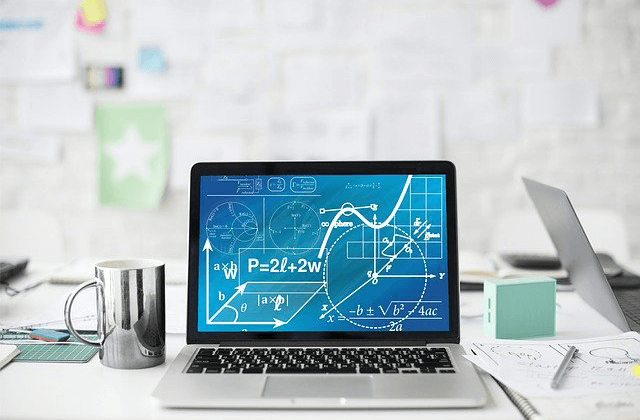
「数理の窓から世界を読みとく」若手研究者たちの感性に注目
皆さんは「数理」と聞いて何を思い浮かべますか。「数学」と似ていますが、ちょっと違います。数理とは「数学を用いてさまざまな研究対象を理論的に解明する方法」のことです。また「数学を共通言語にしてさまざまな事象を理論的に解明する方法」とも言い換えることができます。
「さまざまな研究対象」というのは例えば、「数学」もその対象になります。それから「生命」や「宇宙」や「情報」も研究対象です。2016年に理化学研究所に設立された「数理創造プログラム」(iTHEMS)では、数学、物理学、化学、生物学、情報科学などの数理研究者分野を越えて集まり、宇宙・物質・生命の解明にとどまらず、社会における基本問題の解決をも視野に入れて研究を進めています。
今回は、iTHEMSの若手研究者たちが執筆陣を担った共著『数理の窓から世界を読みとく: 素数・AI.生物・宇宙をつなぐ』 (初田哲男・柴藤亮介編著、岩波書店)をもとに数理の魅力をお伝えします。編著者の一人、初田哲男さんはiTHEMSのプログラムディレクターで、もう一人の編著者・柴藤亮介さんはアカデミスト株式会社の代表取締役です。
本書はiTHEMSとアカデミスト株式会社が共同で開催したオンラインイベント「数理で読み解く科学の世界」の内容をベースにまとめたものになっています。参加した中高生からは「中学生でも興味を持てる内容で感動しました!」「若手研究者の方々がワクワクしている様子が伝わり楽しかったです!」という絶賛の声が寄せられたそうです。
一方で『数理の窓から世界を読みとく:素数・AI.生物・宇宙をつなぐ』(以下、本書)は、知識を生み出すための挑戦を続ける若手研究者たちの「物語」がまとめられています。つまり、研究者たちの主観や感動、発見や解明にいたるストーリーまでまるごと記されているというわけです。
客観が重視される数理や数学、科学の世界に主観や感動が混ざっているというのは想像しにくいかもしれませんが、第一章「『数のふしぎ』のその先へ」を担当した宮崎弘安さんは、数学にこそ感性や自由というものがあることを、驚きを持って紹介しています。
そこで、「感性の数学」の代表例として挙げられているのは「フェルマー予想」です。「フェルマー予想」とは、17世紀を生きたフランスのピエール・ド・フェルマーが残した「nが3以上の自然数なら、xのn乗+yのn乗=zのn乗となる自然数x、y、zは存在しない」という命題です。
ところが、フェルマーはこの命題に対して「私は真に驚くべき証明を見つけたが、この余白はそれを書くには狭すぎる」とだけ本の余白にメモし、この定理の証明そのものは残しませんでした。その後、フェルマー予想は多くの数学者を悩まし続け、なんと証明されたのは300年以上も後のこと。1995年、プリンストン大学のイギリス人数学者アンドリュー・ワイルズが証明しました。
驚くべきは、フェルマーが生きた時代にはこのフェルマー予想を証明する術がなかったということです。計算機もありませんでしたし、現在知られている高度な計算理論もありませんでした。にもかかわらず、なぜそんなことができたのか。フェルマーの偉業は、数学の世界に「単なる論理の積み重ねを超えた何か」があることを私たちに知らせてくれます。数学の研究にも、論理を超えてしまう「人間の感性の力」が不可欠だということではないでしょうか。
「知能」を数理で解き明かすことができるのかという視点に立つと、また別の印象が湧いてきます。実はこの「知能とは何か」という問いに研究者たちはまだ答えることができていません。言い換えれば、「知能とは何か」を探るべくAIの研究は進んでいるともいえるのです。
長らくAIは、うまく動作するモデルが作れたとしても「なぜそれがうまくいったのか」が分からないケースが多かったのです。しかし、その問題も克服されつつあり、「知能とは何か」についての答えにだんだんと接近しつつあるようです。
このような思考ツールがあらかた揃えば、「ヒトの男女比はだいたい、1対1である。これには適応進化的な理由はあるか」ということにも迫ることができます。つまり、数理で生物進化の謎を読みとくこともできるのです。
不思議なことに「暗黒物質」「ダークマター」は、存在自体は分かっているけれども、その正体はまだ分かっていないのです。正体を突き止めるべく考えられた探査方法は大きく3つあり、「直接探査」「間接探査」「速器実験」です。
廣島渚さんはそれぞれの探査方法を五七五で紹介しています。
直接探査「ないのなら 来るまで待とう ダークマター」
間接探査「ないのなら 探しに行こう ダークマター」
速器実験「ないのなら つくってしまえ ダークマター」
それぞれ大体のニュアンスは伝わったでしょうか。暗黒物質の色はいったい何色なのでしょう。興味が高まります。
ということで、ここまで駆け足で、数理と数学、数理とAI、数理と生物、数理と宇宙の関係についてお伝えしてきました。本書のほんの一部を紹介したにすぎませんが、お分かりのように若手研究者たちの原動力になっているのは、なによりも「楽しい」「面白い」という好奇心です。彼らのワクワクする感性がつまった本書を読めば、皆さんの知的好奇心も大いに触発されることでしょう。
「さまざまな研究対象」というのは例えば、「数学」もその対象になります。それから「生命」や「宇宙」や「情報」も研究対象です。2016年に理化学研究所に設立された「数理創造プログラム」(iTHEMS)では、数学、物理学、化学、生物学、情報科学などの数理研究者分野を越えて集まり、宇宙・物質・生命の解明にとどまらず、社会における基本問題の解決をも視野に入れて研究を進めています。
今回は、iTHEMSの若手研究者たちが執筆陣を担った共著『数理の窓から世界を読みとく: 素数・AI.生物・宇宙をつなぐ』 (初田哲男・柴藤亮介編著、岩波書店)をもとに数理の魅力をお伝えします。編著者の一人、初田哲男さんはiTHEMSのプログラムディレクターで、もう一人の編著者・柴藤亮介さんはアカデミスト株式会社の代表取締役です。
本書はiTHEMSとアカデミスト株式会社が共同で開催したオンラインイベント「数理で読み解く科学の世界」の内容をベースにまとめたものになっています。参加した中高生からは「中学生でも興味を持てる内容で感動しました!」「若手研究者の方々がワクワクしている様子が伝わり楽しかったです!」という絶賛の声が寄せられたそうです。
数学には「感性」の力が不可欠
冒頭にも書いた通り、数理の共通言語は「数学」です。数学と聞くと「お勉強」と身構えてしまうかもしれませんが、おそらくそれは学校での勉強や教科書の印象が強いからだと思います。教科書というのは「すでに科学的に明らかにされた事実がわかりやすくまとめられたもの」であり、「知識」を得ることを目的に作られています。一方で『数理の窓から世界を読みとく:素数・AI.生物・宇宙をつなぐ』(以下、本書)は、知識を生み出すための挑戦を続ける若手研究者たちの「物語」がまとめられています。つまり、研究者たちの主観や感動、発見や解明にいたるストーリーまでまるごと記されているというわけです。
客観が重視される数理や数学、科学の世界に主観や感動が混ざっているというのは想像しにくいかもしれませんが、第一章「『数のふしぎ』のその先へ」を担当した宮崎弘安さんは、数学にこそ感性や自由というものがあることを、驚きを持って紹介しています。
そこで、「感性の数学」の代表例として挙げられているのは「フェルマー予想」です。「フェルマー予想」とは、17世紀を生きたフランスのピエール・ド・フェルマーが残した「nが3以上の自然数なら、xのn乗+yのn乗=zのn乗となる自然数x、y、zは存在しない」という命題です。
ところが、フェルマーはこの命題に対して「私は真に驚くべき証明を見つけたが、この余白はそれを書くには狭すぎる」とだけ本の余白にメモし、この定理の証明そのものは残しませんでした。その後、フェルマー予想は多くの数学者を悩まし続け、なんと証明されたのは300年以上も後のこと。1995年、プリンストン大学のイギリス人数学者アンドリュー・ワイルズが証明しました。
驚くべきは、フェルマーが生きた時代にはこのフェルマー予想を証明する術がなかったということです。計算機もありませんでしたし、現在知られている高度な計算理論もありませんでした。にもかかわらず、なぜそんなことができたのか。フェルマーの偉業は、数学の世界に「単なる論理の積み重ねを超えた何か」があることを私たちに知らせてくれます。数学の研究にも、論理を超えてしまう「人間の感性の力」が不可欠だということではないでしょうか。
人工知能の「知能」とは何かに迫る
続いて、田中章詞さんによる第二章「人工知能に絵を描かせる方法」では、「数理の窓」から人工知能(AI)を覗きます。数理とAIが結びつくのはそれほど違和感なく捉えられるでしょう。でもよくみると、AIには「知能」という言葉が使われています。「知能」を数理で解き明かすことができるのかという視点に立つと、また別の印象が湧いてきます。実はこの「知能とは何か」という問いに研究者たちはまだ答えることができていません。言い換えれば、「知能とは何か」を探るべくAIの研究は進んでいるともいえるのです。
長らくAIは、うまく動作するモデルが作れたとしても「なぜそれがうまくいったのか」が分からないケースが多かったのです。しかし、その問題も克服されつつあり、「知能とは何か」についての答えにだんだんと接近しつつあるようです。
数理で生物進化の謎を読みとく
第三章は入谷亮介さんによる「数理で読みとく生物進化」ですが、よく考えてみると数理と生物は意外な組み合わせともいえるでしょう。ここでは「数理モデル」を使いますが、数理モデルは「生物学に限らず、自然科学の研究を行ううえで用いる数学の道具」のことです。それから「進化ゲーム理論」という考え方を用います。つまり、生物の進化を「進化ゲーム」と捉えるのです。ゲーム理論は「人間のインセンティブの力学に基づいて、制度設計の問題点や改善に大きな示唆を与えてくれます」とあり、インセンティブとは「意思決定の動機付け」のことです。このような思考ツールがあらかた揃えば、「ヒトの男女比はだいたい、1対1である。これには適応進化的な理由はあるか」ということにも迫ることができます。つまり、数理で生物進化の謎を読みとくこともできるのです。
ダークマターを五七五で紹介
最後の第四章は廣島渚さんによる「暗黒物質の色は何色? -見えないモノを調べる方法-」ということで、宇宙の話です。宇宙には「暗黒物質」「ダークマター」という見えないモノがたくさん存在しています。けれども、その「見えないモノ」をどうすれば調べることができるのか。不思議なことに「暗黒物質」「ダークマター」は、存在自体は分かっているけれども、その正体はまだ分かっていないのです。正体を突き止めるべく考えられた探査方法は大きく3つあり、「直接探査」「間接探査」「速器実験」です。
廣島渚さんはそれぞれの探査方法を五七五で紹介しています。
直接探査「ないのなら 来るまで待とう ダークマター」
間接探査「ないのなら 探しに行こう ダークマター」
速器実験「ないのなら つくってしまえ ダークマター」
それぞれ大体のニュアンスは伝わったでしょうか。暗黒物質の色はいったい何色なのでしょう。興味が高まります。
ということで、ここまで駆け足で、数理と数学、数理とAI、数理と生物、数理と宇宙の関係についてお伝えしてきました。本書のほんの一部を紹介したにすぎませんが、お分かりのように若手研究者たちの原動力になっているのは、なによりも「楽しい」「面白い」という好奇心です。彼らのワクワクする感性がつまった本書を読めば、皆さんの知的好奇心も大いに触発されることでしょう。
<参考文献>
・『数理の窓から世界を読みとく:素数・AI.生物・宇宙をつなぐ』(初田哲男・柴藤亮介編著、岩波書店)
https://www.iwanami.co.jp/book/b593239.html
<参考サイト>
理化学研究所 数理創造プログラム(iTHEMS)
https://ithems.riken.jp/ja
・『数理の窓から世界を読みとく:素数・AI.生物・宇宙をつなぐ』(初田哲男・柴藤亮介編著、岩波書店)
https://www.iwanami.co.jp/book/b593239.html
<参考サイト>
理化学研究所 数理創造プログラム(iTHEMS)
https://ithems.riken.jp/ja
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子







