テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
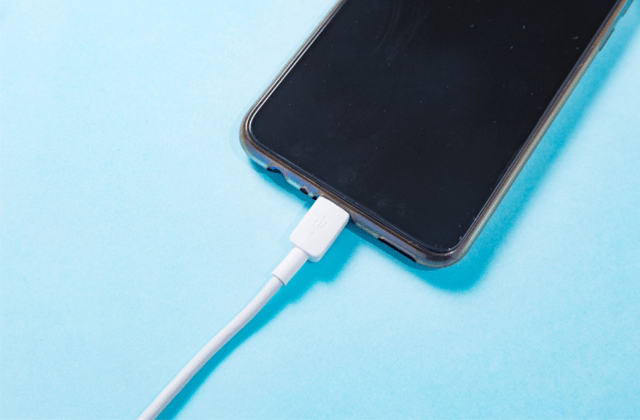
スマホの充電ケーブル「最適な長さ」とは?
スマホの充電ケーブルは、日常生活上の必須アイテムと言えるでしょう。ネットショップから家電量販店、コンビニや100円ショップなどさまざまな場所で売られています。短いケーブルやリールで巻き取るタイプはコンパクトで持ち運びにも便利ですが、状況によっては長いものが重宝する場面もあります。ただし、あまり知られていないかもしれませんが、実は長いケーブルの方が充電時間は長くなるようです。どういうことなのでしょうか、少し詳しくみてみましょう。
さらに、100円ショップで販売されていたリールタイプのケーブル(50cm)だと0.25Aと、かなり電流が少なくなっています。リールタイプは巻き取りやすくするためにケーブルが細くなっていることから、電流も少ないようです。ここまでの結果を見る限り充電時間は、通常の太さのケーブルであれば2mで1mのものの倍の時間が必要になり、100円ショップなどにある細いリール型のケーブルだとおよそ6倍の時間がかかることになります。
おおよそ1mを越えたあとは、長くなればなるほど充電に時間がかかることがわかりました。また同番組の検証では、充電しながらスマホを操作することを加味して、充電ケーブルは「50cmが最適」という回答に辿り着いたようです。充電しながらのスマホ操作はバッテリーへの負荷の観点からやらないに越したことはないのですが、充電中に電話がかかってこないとは限りません。充電スピードも使い勝手も両立させると考えれば、頷ける回答ではないでしょうか。
1m以降でやや充電スピードが落ちる
日経STYLEの記事では15cmから3mまでのケーブルを使い、それぞれの充電時間について計測する実験を行っています。この結果、1m以上のケーブルでは電流が低下しました。詳細を見ると15cmと30cmでは1.48A、50cmでは1.45Aの電流が流れていますが、1mになると1.18Aに落ちます。1.5mでは0.94A、2mでは0.75A、3mでは0.61Aとなっています。つまり、2mのケーブルだと15cmや30cmのケーブルの半分まで電流が低下していることがわかります。すなわち、1m以上の長さのケーブルを使うと充電により時間がかかるということです。さらに、100円ショップで販売されていたリールタイプのケーブル(50cm)だと0.25Aと、かなり電流が少なくなっています。リールタイプは巻き取りやすくするためにケーブルが細くなっていることから、電流も少ないようです。ここまでの結果を見る限り充電時間は、通常の太さのケーブルであれば2mで1mのものの倍の時間が必要になり、100円ショップなどにある細いリール型のケーブルだとおよそ6倍の時間がかかることになります。
最適なケーブルの長さは50cmという話も
また、TBS系列のバラエティ番組「林先生が驚く初耳学」でも同様の実験がなされています。ここでもやはり、30cmと50cmのケーブルは同じ時間で充電されたようです。この2つのケーブルを用いて充電が100%となったとき、他のケーブルでの充電状態を見ると、1mのケーブルでは95%、2mでは83%、3mでは69%、リールタイプの70cmだと55%という結果になっています。おおよそ1mを越えたあとは、長くなればなるほど充電に時間がかかることがわかりました。また同番組の検証では、充電しながらスマホを操作することを加味して、充電ケーブルは「50cmが最適」という回答に辿り着いたようです。充電しながらのスマホ操作はバッテリーへの負荷の観点からやらないに越したことはないのですが、充電中に電話がかかってこないとは限りません。充電スピードも使い勝手も両立させると考えれば、頷ける回答ではないでしょうか。
<参考サイト>
充電時間はケーブルで違う 実験で6倍かかる商品も|NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO31395900V00C18A6000000/
スマホの充電に最適なケーブルの長さとは? 意外な真相に林修&藤田ニコルも驚き|Real Sound
https://realsound.jp/tech/2018/09/post-248638.html
充電時間はケーブルで違う 実験で6倍かかる商品も|NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO31395900V00C18A6000000/
スマホの充電に最適なケーブルの長さとは? 意外な真相に林修&藤田ニコルも驚き|Real Sound
https://realsound.jp/tech/2018/09/post-248638.html
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子
葛飾北斎と応為の見事な「画狂人生」を絵と解説で辿る
テンミニッツ・アカデミー編集部










