テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
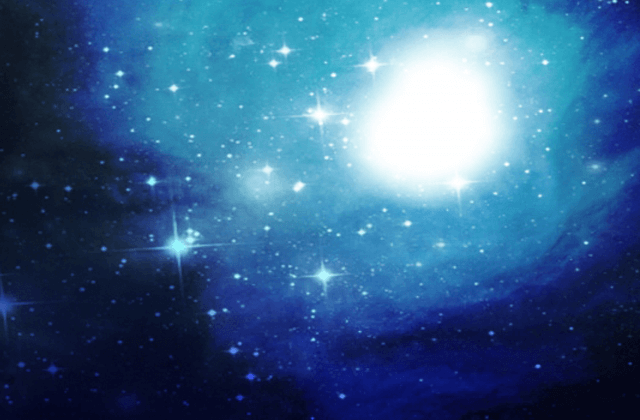
物質進化の謎を解き明かす『宇宙の化学』の物語
遠く果てしない宇宙。その全貌を知ることはできなくても、その果てしなく遠い宇宙と私たちを結んでくれる現象があります。それは化学現象です。
例えば、雨上がりの空に見つけることができるとうれしい「虹」は、水滴や水晶のプリズムを通った太陽光が波長によって分かれる「分光」という化学現象です。
そして、分光は太陽のみならず太陽系全体が何でできているのか、さらには宇宙全体がどのようにしてできたかを教えてくれる現象だと、東京大学先進科学研究機構・准教授の羽馬哲也氏は著書『宇宙の化学 プリズムで読み解く物質進化』(岩波科学ライブラリー)のなかで説いています。
そのために、第1章「ガスの炎とプリズム」では、まずは身近な化学現象の具体例として、ガスの炎を取り上げています。正常に燃焼しているときのガスの炎は青色ですが、単なる青一色ではなく、緑色や紫色の部分も目にすることができます。
ではなぜ、人間はそうした色を見分けることができるのか。それは、目に入った光の波長の異なりを、色として捉えることができるからです。つまり、ガスの炎からは、波長の異なる光が放出されているということです。
本書では、ガスの炎という例を通して、物資から放出される光を波長ごとに分ける「分光」が、ある物質がどのような原子や分子でできているのかを調べるために有用であることを解説しているのです。
そこから、第2章「宇宙からの光」で、地球にもっとも近い恒星である太陽に分光器を向けて、太陽がどのような物質でできているのかを概説。さらに第3章「ビッグバン」では、太陽の光を分光することで、太陽系全体がどのような元素でできているのかがわかると述べています。
また、第4章「原子から分子へ」で、宇宙に存在する280種類以上の分子のなかでもっとも豊富な分子である水素分子に注目し、星間塵(固体の微粒子からなる星間物質)の表面は水分子をはじめとする多様な分子でできた氷で覆われていることを説明しています。
第5章「宇宙における物質進化」では、星間分子のなかでも比較的生成経路が判明しており、なおかつ恒星や惑星系の形成を議論するうえで重要な分子である、水素分子・水分子・メタノール分子について取り上げ、第6章「より複雑な分子へ」では、氷星間塵の化学進化や氷星間塵の光反応について現状の理解を解説。
そして、第7章「宇宙の化学を研究する意味」では、「本書で紹介した星間塵の氷や固体有機物までの話は、太陽系を含むどの惑星系も通ってきた普遍的な化学進化といえるので、太陽系に住む我々が知っておいても損はないのではないか」ということです。
そして、本書を読むことは“分光器を対象に向ける行為”という、魅惑の学びともいえるものです。つまり、分光器を通すことによって、光は分類され美しい色を帯びる。分類して、いまわかることをより正確に区別して深めると同時に、わからないところに美しい色のタグを付けて仮置きし、今後に備える。そうしたことも、分光器を対象に向け分光(分類)すればこそできることです。
なお、本書は東京大学教養学部の講義を元にしています。そのため、初学者にはやや難しく感じる箇所があるかもしれませんが、先人が分光器を宇宙に向けて化学現象を読み解いたように、本書は、現状の「宇宙の化学」を理解するための一助であるとともに、宇宙の未知なる物質を読み解くための、最初の分光器となる一冊です。
例えば、雨上がりの空に見つけることができるとうれしい「虹」は、水滴や水晶のプリズムを通った太陽光が波長によって分かれる「分光」という化学現象です。
そして、分光は太陽のみならず太陽系全体が何でできているのか、さらには宇宙全体がどのようにしてできたかを教えてくれる現象だと、東京大学先進科学研究機構・准教授の羽馬哲也氏は著書『宇宙の化学 プリズムで読み解く物質進化』(岩波科学ライブラリー)のなかで説いています。
化学の観点から“宇宙の物質”の謎を説く
『宇宙の化学 プリズムで読み解く物質進化』(以下、本書)では、宇宙空間でどのようして原子が分子となったり氷星間塵(氷の微粒子からなる星間物質、または氷の微粒子のこと)となったりするのか、さらには微惑星や惑星などを含む多様な星へと進化していくのかといった“宇宙の物質”の謎を、化学の観点から解説しています。そのために、第1章「ガスの炎とプリズム」では、まずは身近な化学現象の具体例として、ガスの炎を取り上げています。正常に燃焼しているときのガスの炎は青色ですが、単なる青一色ではなく、緑色や紫色の部分も目にすることができます。
ではなぜ、人間はそうした色を見分けることができるのか。それは、目に入った光の波長の異なりを、色として捉えることができるからです。つまり、ガスの炎からは、波長の異なる光が放出されているということです。
本書では、ガスの炎という例を通して、物資から放出される光を波長ごとに分ける「分光」が、ある物質がどのような原子や分子でできているのかを調べるために有用であることを解説しているのです。
光や分子を通して、宇宙の化学を研究する
次いで羽馬氏は、分光から「分光学」という一大学問分野が誕生したこと、さらに「分光器を宇宙に向け、宇宙から届く光を分光すれば、宇宙に存在する物質が調べられるのではないか?」と問いかけます。そこから、第2章「宇宙からの光」で、地球にもっとも近い恒星である太陽に分光器を向けて、太陽がどのような物質でできているのかを概説。さらに第3章「ビッグバン」では、太陽の光を分光することで、太陽系全体がどのような元素でできているのかがわかると述べています。
また、第4章「原子から分子へ」で、宇宙に存在する280種類以上の分子のなかでもっとも豊富な分子である水素分子に注目し、星間塵(固体の微粒子からなる星間物質)の表面は水分子をはじめとする多様な分子でできた氷で覆われていることを説明しています。
第5章「宇宙における物質進化」では、星間分子のなかでも比較的生成経路が判明しており、なおかつ恒星や惑星系の形成を議論するうえで重要な分子である、水素分子・水分子・メタノール分子について取り上げ、第6章「より複雑な分子へ」では、氷星間塵の化学進化や氷星間塵の光反応について現状の理解を解説。
そして、第7章「宇宙の化学を研究する意味」では、「本書で紹介した星間塵の氷や固体有機物までの話は、太陽系を含むどの惑星系も通ってきた普遍的な化学進化といえるので、太陽系に住む我々が知っておいても損はないのではないか」ということです。
「宇宙の化学」の分光器となる一冊
「宇宙の化学」の研究はまだ歴史が浅く、これからの分野ということです。だからこそ発展の可能性も大きく、また宇宙の物質を知ることで新しい視点でものごとを見ることができると、羽馬氏は述べています。そして、本書を読むことは“分光器を対象に向ける行為”という、魅惑の学びともいえるものです。つまり、分光器を通すことによって、光は分類され美しい色を帯びる。分類して、いまわかることをより正確に区別して深めると同時に、わからないところに美しい色のタグを付けて仮置きし、今後に備える。そうしたことも、分光器を対象に向け分光(分類)すればこそできることです。
なお、本書は東京大学教養学部の講義を元にしています。そのため、初学者にはやや難しく感じる箇所があるかもしれませんが、先人が分光器を宇宙に向けて化学現象を読み解いたように、本書は、現状の「宇宙の化学」を理解するための一助であるとともに、宇宙の未知なる物質を読み解くための、最初の分光器となる一冊です。
<参考文献>
『宇宙の化学 プリズムで読み解く物質進化』(羽馬哲也著、岩波科学ライブラリー)
https://www.iwanami.co.jp/book/b619873.html
<参考サイト>
東京大学大学院 総合文化研究科 先進科学研究機構/同研究科 広域科学専攻
http://www.hamalab.c.u-tokyo.ac.jp/
先進科学研究機構
http://kis.c.u-tokyo.ac.jp/
『宇宙の化学 プリズムで読み解く物質進化』(羽馬哲也著、岩波科学ライブラリー)
https://www.iwanami.co.jp/book/b619873.html
<参考サイト>
東京大学大学院 総合文化研究科 先進科学研究機構/同研究科 広域科学専攻
http://www.hamalab.c.u-tokyo.ac.jp/
先進科学研究機構
http://kis.c.u-tokyo.ac.jp/
人気の講義ランキングTOP20
昭和陸軍の派閥抗争には三つの要因があった
中西輝政
なぜ変異が必要なのか…現代にも通じる多様性創出の原理
長谷川眞理子










