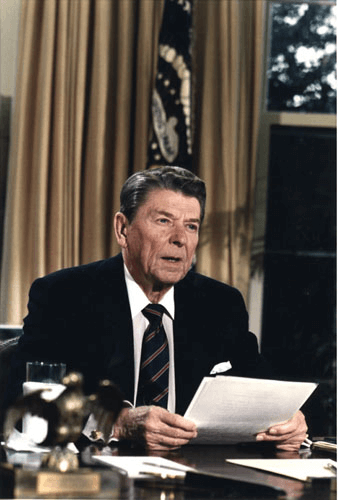●日本の輸出競争力の強さを示す購買力平価
今日の2点目のポイントは、アベノミクスを総括することです。基本的にはアベノミクスの下で、急激な円安が進行して株価も上昇ということが起こっています。そのあたりのメカニズムについて考えてみたいと思います。
今、見ていただいているグラフは、ドル円の購買力平価の動きを示しています。購買力平価は、日本と、このケースでいえばアメリカの物価格差を考慮した上でのドル円相場の適正水準になってきます。これは1973年4月を基準月にしています。1973年は、為替相場が変動相場制に移行した時期に当たります。
一方で物価統計は、スーパーマーケットで売っているりんごのような消費者物価もあれば、企業間で売り買いしている生産者物価、あるいは企業物価もあります。後は自動車のように日本の輸出産業の値段を象徴する輸出物価もあります。今現在、消費者物価で見た購買力平価が大体125円ほど、生産者物価が100円ほど、輸出物価が50円ほどとなっています。これは日本の相対的な輸出競争力の強さを示しているわけなのですが、以上のような水準にあることが示されています。
●生産者物価による上限を抜けるほどの地殻変動的ドル高円安
このグラフの上から3番目の緑の線は何かというと、生産者物価と輸出物価を足して2で割ったものです。生産者物価と輸出物価はそれぞれ100円と50円という水準にありますから、その真ん中の75円ほどのところに位置しています。過去20年ほどを振り返ってみると、基本的にはこの上から3番目の緑の線にあるように、生産者物価と輸出物価の購買力平価が、ドル円の下限になってきたことが分かるかと思います。現に2011~2012年の時もドル円はこの線の上で底入れに転じた格好になったわけです。一方でドル円の上限となってきたのは、上から2番目の生産者物価による購買力平価です。例えば、1998年には147円、2001年には135円、2007年には124円というドル高円安をつけたのですが、その時もことごとくこの生産者物価の購買力平価に行く手を阻まれていた格好になっています。
しかも、こういった生産者物価に過去、届いてきたというのは、アメリカのFRB(連邦準備制度)の政策金利が基本的に日銀の金利よりも4パーセント以上高い時だったのです。そういった状況になって初めて、生産者物価までドル高円安が進行するけれども抜けきれない...