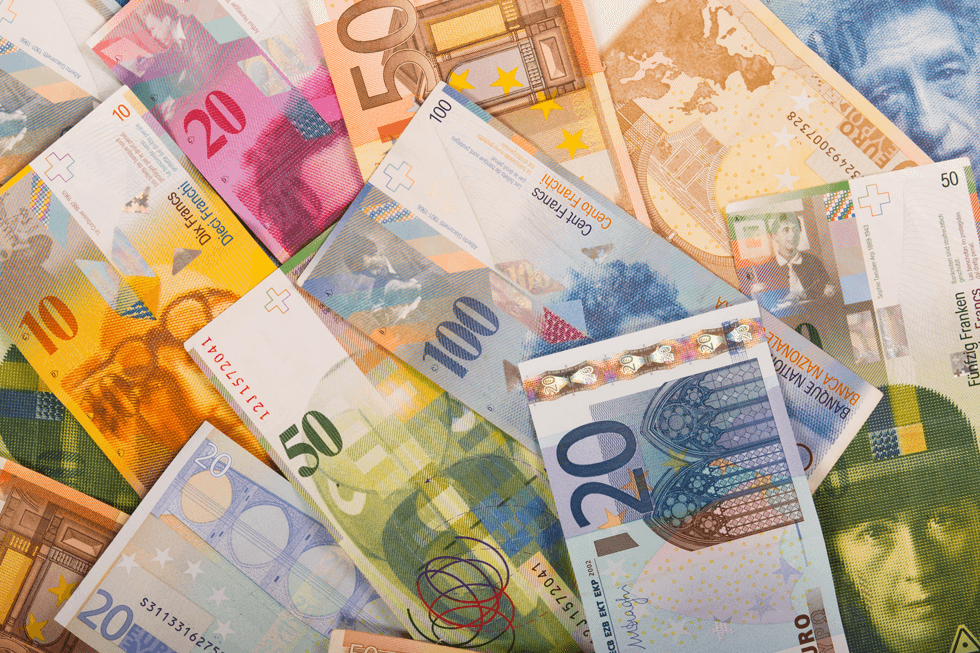●SNBの通貨高抑制策は、2009年から始まっていた
今回のシリーズで、二つ目のポイントは、スイスのユーロペッグ制度が、どのような状況下で導入され、行われてきたのかということです。
第1回で申し上げたとおり、スイス中央銀行(SNB)による対ユーロのスイスフランの上限レート(1ユーロ=1.2スイスフラン)が導入されたのは、2011年9月です。その直接的な背景には、ヨーロッパにおけるソブリン危機によるユーロ安がありましたが、SNBの通貨高抑制策は、実はそれ以前から行われていました。
SNBでは、2009年に通貨高の抑制を図るための上限レート(1ユーロ=1.45スイスフラン)を設けています。この時には、2008年のリーマン危機がもたらした世界的な金融恐慌が起こっていました。その波に突入する中、 何とかスイスフランの通貨高を止めようという動きを示していたのです。
この時に設定された上限レートは、結果的にはその後放棄され、スイスフラン高はまた進行していきます。
●ユーロペッグ制度導入のきっかけは、ソブリン危機
ところが2010年ごろ、ギリシャから始まったソブリン危機がユーロ圏に波及したため、スイスフラン高・ユーロ安を止めないといけないのでないか、という議論が出始めます。そんな中、特に2011年8月に発表されたSNBの通貨高防止策は、かなりまとまったものとして注目されます。
その時、SNBは、一種の量的緩和政策として準備預金を増加させていったり、通貨スワップ市場においてスイスフランの流動性を続けて供給するなどの政策をとることによって、スイスフランの金利を低下させました。実は、この2011年8月の段階で、スイスフランには、一部マイナス金利さえ発生していたのです。
ということで、スイスフラン売り・ユーロ買いへの直接介入をしない通貨高抑制策として、一種の量的緩和とマイナス金利を含めた金利引き下げ策により通貨高を止めようとしていたのが、2011年8月の動きなのです。
ところが、それでもスイスフラン高・ユーロ安には歯止めがかかりません。スイス国民も政治家も、やはりスイスフラン高の方に相当のストレスをためていたことが分かります。
●ヒルデブランド総裁の声明に感銘
このような政治環境や国民的議論を読み取って、2011年9月にSNBは「無制限...