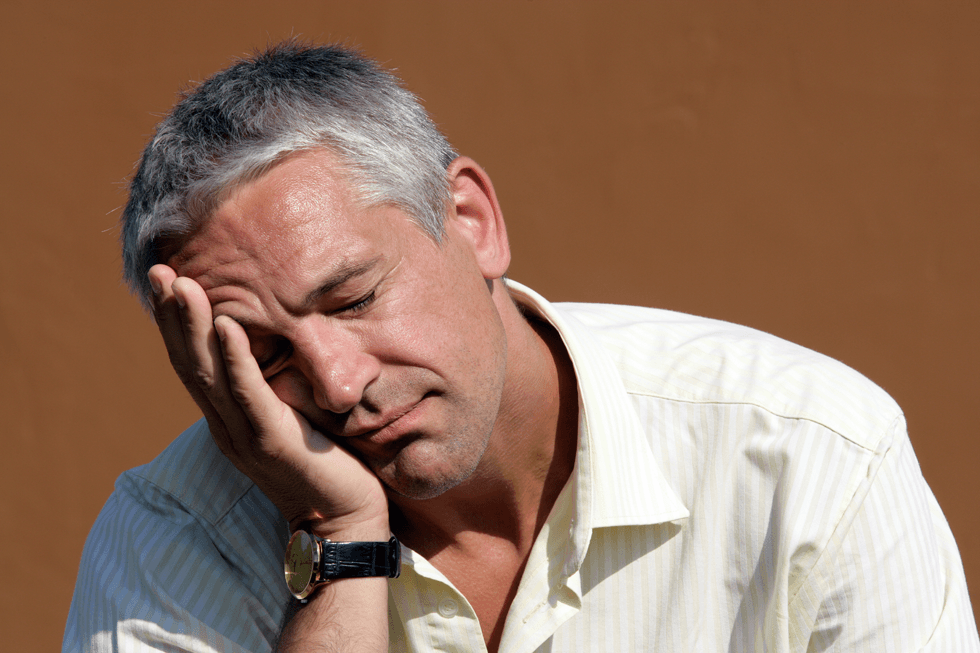●消費者物価指数の微変動に一喜一憂する必要はない
黒田東彦日銀総裁の下、2015年度の末、つまり2016年の3月までに、消費者物価上昇率、インフレ率を2パーセントにもっていくという形でやってきたわけですが、ここにきて、石油価格の大幅下落もあって、目標達成はなかなか難しいだろうという見方が非常に強まってきました。もともと民間のエコノミストは、日銀の目標は多少実現が難しいのではないかという議論をしていたわけですが、先日の日本銀行の政策決定会合の後の黒田東彦総裁の会見では、結果的には、日本銀行もその見方に少し擦り寄ってきたと言えるかもしれません。
具体的には何かというと、石油価格が下がったために、当初想定していたよりも、予想の物価上昇率に対しての数字を少し下げたということ。それから、2016年の3月、つまり2015年度末までに物価上昇率2パーセントにもっていくことは、ひょっとしたらスケジュール通りには実現できない可能性もある、つまり、これは将来必ず実現するけれど、少し時期が後ろにずれるかもしれないということを、日銀総裁はおっしゃったわけです。これが非常に大きな波紋を呼んでいます。
先週、私は香港で大きな金融の会議に出ていたのですが、たまたまその前の週に黒田総裁がスイスのダボスで発言したものですから、その中で「これからもう少しクリエイティブな金融政策運営をする」と表現された部分について、「クリエイティブ」とはどういう意味が考えられるかが、その香港の会議に集まった世界の多くの投資家の間で話題になりました。非常に興味深いことだと思います。
私の個人的な見方を申し上げますと、この問題はそれほど大変な話ではないと考えています。なぜかというと、確かに原油価格の下落は、足元の消費者物価上昇率を少し落としていきます。想定したよりも速いスピードで物価が上がっていくことにはなりにくいかもしれません。しかし、マクロ経済全体から見ると、これは明らかに経済を後押しする要因であるわけですから、これから半年くらいはいざ知らず、1年、あるいは1年半先を見ていくと、むしろ消費等に非常にプラスに働いてくる可能性が強いです。
ですから、足元の消費者物価指数の多少の変動に一喜一憂するより、「これまで日本銀行がやってきた金融緩和策は順調に進んでいる」と見るべきだろうと思います。
...