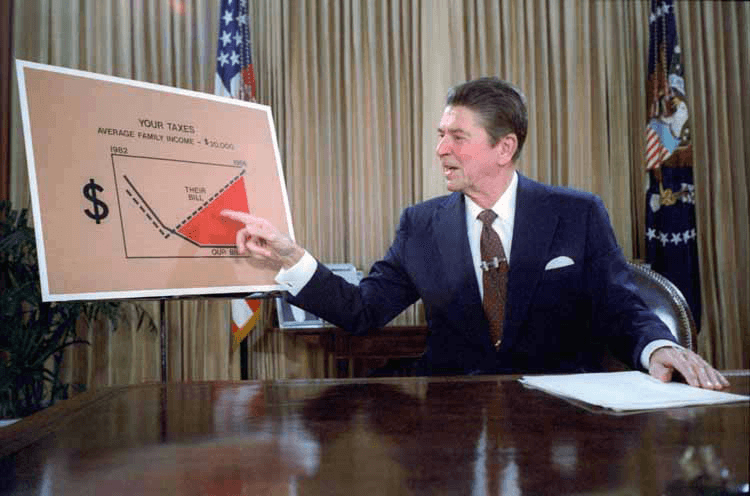●加速する円安を読む三つの観点
皆さん、こんにちは。シティグループ証券の高島修です。
ドル円相場は、1ドル122円台までドル高円安が進み、円安が加速している状態です。そうした中、昨年(2014年)の後半ぐらいから、「もう円は十分に安くなったので、これ以上の円安は害悪である」というような話も、かなり出てきています。今日は、今の円安をどう捉えるべきかについてお話しします。
大きく分けて三つの項目があります。
一つ目は、購買力平価の考え方から、円相場の割高感、割安感を考えます。その中でアベノミクスがどういう意味を持っているのかをお話ししたいと思います。
二つ目は、円の実効相場です。これは少し聞き慣れない言葉だと思いますが、この実効相場から見た割高感、割安感をお話しします。
三つ目に、その実効相場、特に、実質実効円相場が過去最安値圏まで達してきていますので、そういった状況を、論理的にどう捉えるべきかについてお話しします。
●購買力平価は国内外の物価格差を考慮する
まず一点目は、購買力平価で見たドル円相場です。購買力平価とは、国内外の物価格差を考慮した上での為替レートの適正水準を測るものです。「ファンダメンタルズ」や「理論がない」といわれがちな為替相場の中で、一番有名な理論といってもいいと思います。
購買力平価という考え方は、為替相場がまだ基本的には固定されていた1920年代に、スウェーデンの経済学者グスタフ・カッセル氏が提唱したものです。基本的な考え方は、「インフレの通貨は長期的物価の面から安くなり、デフレの通貨は長期的物価の面から強くなる」というものです。
通貨と為替レートは混同されがちな概念なので、整理したいと思います。通貨は、大きく分けて二つの側面を持っています。それが対内価値と対外価値です。対内価値は、いわゆる物価です。1万円札を持ってスーパーマーケットに行ったら、りんごがいくつ買えるか。これが通貨の持つ対内価値です。一方で、対外価値は、ドル円相場をはじめとした為替レートの問題になります。要は、1万円札を持って私が勤務するシティバンクに来ていただくと、USドルがいくら買えるのか、あるいは、ユーロがいくら買えるのか。これが通貨の持つ対外価値です。為替レートは、言うまでもなく、この対外価値を表すものです。同じ通貨で二つの...