テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
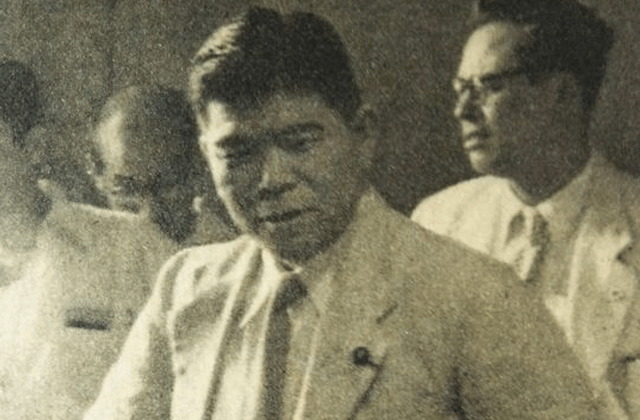
日本に失われた「保守の知恵」とは何か?
10月22日に衆院選が与党・自民党の圧勝で終わりましたが、この機会に、現代の政治から失われた「保守の知恵」について、考えてみませんか。評論家・佐高信氏が語る内容が、そのヒントです。
終戦後の第1次吉田内閣で、内閣政務次官を務めたのが大野伴睦です。いわゆる党人派で「政治は義理と人情だ」がモットー。岐阜羽島出身で、故郷に誘致した新幹線駅前に夫婦の銅像が建っていることでも有名ですが、佐高氏が『大野伴睦回想録』の中から取り上げているエピソードは、日本共産党の戦後の表看板となった野坂参三にまつわるもの。
まだ日中の国交が回復しない時代、当時日本共産党議長だった野坂氏が中国訪問を希望したものの、ビザが下りずどうにもならないことがありました。戦前からの知り合いということからか、野坂氏は大野氏に仲介を頼み、大野氏は外務省に橋渡しをしたのです。
「なぜ共産党のトップの面倒を見るのか」と騒ぐ自民党の若手に対して、大野氏は一言、「もともと赤の人間を、赤の国にやってもどうということはない」。これで自民党は共産党に大きな貸しをつくったわけです。そこまで計算したかどうか不明ながら、思想の違いを認めるという点でおおらかに対応した姿勢を、佐高氏は「保守の知恵」と呼ぶのです。
「最初は気に染まない嫁をまわりから押し付けられて、しぶしぶもらった。しかし40年経って、その嫁も立派な子も産んでくれたし、最初は嫌いな嫁だと思ったけれども、段々その気持ちも変わってくる」
憲法を「嫁」にたとえるあたりが「ミッチー節」と呼ばれたゆえんですが、あえて泥くさい表現を使って提案を受け入れた渡辺氏に、田中氏はやはり「保守の知恵」を感じたと言います。それに比べると、ミッチーの長男である渡辺喜美氏が「希望の党」からの衆院選立候補を断念せざるをえなかった経緯は、まさに杓子定規と言えるのではないでしょうか。
日中関係と日米関係を「二次方程式」にたとえ、日中国交回復に「保守の知恵」を生かした政治家を懐かしむ佐高氏は、「分かりやすさ」ばかりが尊重される時代のもとで、「底深い知恵」が消されていく風潮、時代に応じた変節を許さない「危なさ」を危惧しています。それは果たして、政治の世界だけに限ったことでしょうか。
保守の知恵1:違いを批判しない
価値観は多様化しているはずなのに「不寛容」になり、ささいなことでイラつくようになったと言われるのが、現代社会の特徴です。今回、「国難突破解散」のネーミングで衆議院を解散する際に安倍首相がいくつもの「大義」を持ち出したことにも、炎上を恐れての周到な準備が感じられました。しかし、戦後の衆院史上で最も有名な解散といえば1953年、吉田茂首相の失言が発端となった「バカヤロー」解散でしょう。終戦後の第1次吉田内閣で、内閣政務次官を務めたのが大野伴睦です。いわゆる党人派で「政治は義理と人情だ」がモットー。岐阜羽島出身で、故郷に誘致した新幹線駅前に夫婦の銅像が建っていることでも有名ですが、佐高氏が『大野伴睦回想録』の中から取り上げているエピソードは、日本共産党の戦後の表看板となった野坂参三にまつわるもの。
まだ日中の国交が回復しない時代、当時日本共産党議長だった野坂氏が中国訪問を希望したものの、ビザが下りずどうにもならないことがありました。戦前からの知り合いということからか、野坂氏は大野氏に仲介を頼み、大野氏は外務省に橋渡しをしたのです。
「なぜ共産党のトップの面倒を見るのか」と騒ぐ自民党の若手に対して、大野氏は一言、「もともと赤の人間を、赤の国にやってもどうということはない」。これで自民党は共産党に大きな貸しをつくったわけです。そこまで計算したかどうか不明ながら、思想の違いを認めるという点でおおらかに対応した姿勢を、佐高氏は「保守の知恵」と呼ぶのです。
保守の知恵2:持論に固執しすぎない
立党30年にあたる1985年、自民党内に綱領改正の委員会が設置されました。新しい綱領から「改憲」の文字を外す動きに取り組んだのは、田中秀征氏。1990年代の新党ブームに火をつけた「新党さきがけ」の理論的指導者、細川政権で首相特別補佐、小泉政権で経済企画庁長官を歴任した彼は、渡辺美智雄の説得に当たります。70年代前半、石原慎太郎氏とともにバリバリの「反共の闘士」として青嵐会を引っ張ったタカ派の中心人物だけに、体当たりの覚悟で臨んだところ、返ってきた反応は意外なものでした。「最初は気に染まない嫁をまわりから押し付けられて、しぶしぶもらった。しかし40年経って、その嫁も立派な子も産んでくれたし、最初は嫌いな嫁だと思ったけれども、段々その気持ちも変わってくる」
憲法を「嫁」にたとえるあたりが「ミッチー節」と呼ばれたゆえんですが、あえて泥くさい表現を使って提案を受け入れた渡辺氏に、田中氏はやはり「保守の知恵」を感じたと言います。それに比べると、ミッチーの長男である渡辺喜美氏が「希望の党」からの衆院選立候補を断念せざるをえなかった経緯は、まさに杓子定規と言えるのではないでしょうか。
日中関係と日米関係を「二次方程式」にたとえ、日中国交回復に「保守の知恵」を生かした政治家を懐かしむ佐高氏は、「分かりやすさ」ばかりが尊重される時代のもとで、「底深い知恵」が消されていく風潮、時代に応じた変節を許さない「危なさ」を危惧しています。それは果たして、政治の世界だけに限ったことでしょうか。
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










