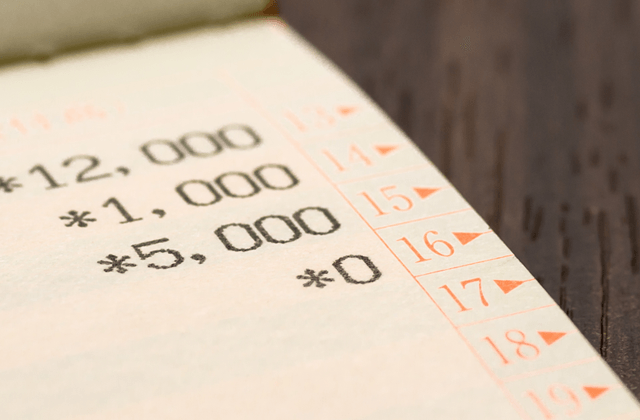
年収1000万でも1割が「貯蓄ゼロ」ってホント?
金融広報中央委員会が発表した2017年の「家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯)」(以下、「世論調査」)によると、金融資産(貯蓄)を持たない世帯の割合は過去最高の31.2%(前年は30.9%)となっています。
その一方で、平均寿命の延びや超高齢社会の進展により、いわゆる「老後資金」の必要額はますます増大しています。今回は、貯蓄と定年にまつわる、お金と働き方についてまとめてみました。
<年収別の金融資産ゼロ世帯の割合と金融資産保有額>
・収入はない:金融資産ゼロ60.7%、平均値852万円・中央値0万円
・年収300万円未満:金融資産ゼロ39.1%、平均値887万円・中央値153万円
・年収300~500万円未満:金融資産ゼロ29.6%、平均値1027万円・中央値400万円
・年収500~750万円未満:金融資産ゼロ24.3%、平均値1138万円・中央値520万円
・年収750~1000万円未満:金融資産ゼロ16.7%、平均値1747万円・中央値1130万円
・年収1000~1200万円未満:金融資産ゼロ11.5%、平均値2464万円・中央値1700万円
・年収1200万円以上:金融資産ゼロ9.9%、平均値4634万円・中央値2670万円
※金融資産を保有していない世帯を含む。
※中央値:資料を大きさの順に並べたとき、全体の中央にくる値(資料の個数が偶数のときは中央にある二つの値の平均値)。
この結果をみると、年収1200万円以上の世帯でも約1割が貯蓄ゼロいう結果がわかります。そして、世帯所得の平均といわれる約546万円のゾーンにあたる年収500~750万未満の世帯でも、約2.5割が貯蓄ゼロという厳しい結果が示されています。
ちなみに、全体の平均値は1151万円、中央値は380万円となっています。これらのデータから、「貯蓄のある・なし」の二極化が進んでいる状況だということがわかります。
ここで世界にも目を向けてみましょう。実は定年制は万国共通ではありません。アメリカ、カナダ、イギリスなどのように、定年制が禁じられている国もあります。また、定年制がある国でもその年齢はさまざまです。ドイツでは日本同様の深刻な高齢化により67歳まで引き上げが実施され、さらになる引き上げも検討されているそうです。
他方、マレーシアやタイのように経済発展の著しい国では、労働力やノウハウ確保のために定年の引き上げが実施されています。
その後、戦争時期など一時的な中断を経ながらも、終身雇用や年功序列型賃金制度と関連した、いわゆる「日本的経営」とともに普及していきました。また、普及の過程で社会情勢の変化や労働組合の要求などに応じて定年年齢も上がっていき、1955(昭和30)~65(昭和40)年頃にかけて、60歳を定年とする企業が大半を占めるようになりました。
現状の日本社会は、さらなる高齢化の進展、健康寿命や平均寿命の伸長と定年年齢のバランスが取れていないこと、人手不足などからも定年年齢の引き上げの要請が高まっています。そうした社会情勢や要請をうけて、政府は2019年度から段階的に「65歳定年」へ延長する検討に入り、多くの企業での検討や取り組みも始まっています。
60歳までに定年後のための十分な貯蓄は難しくても、例えば、健康寿命が続くかぎり現役時代を延長し、多少は減ったとしても収入を得る生活を長く続けることができれば、生活の質を担保し、安心した日々を送れるはずです。
人生100年時代といわれる現代、「生涯現役」を貫く準備と覚悟が必要かもしれません。
その一方で、平均寿命の延びや超高齢社会の進展により、いわゆる「老後資金」の必要額はますます増大しています。今回は、貯蓄と定年にまつわる、お金と働き方についてまとめてみました。
「貯蓄ゼロ」の厳しい現実と二極化
まずは世論調査から、「年収別の金融資産ゼロ世帯の割合と金融資産保有額」を抜粋し、比較してみましょう。<年収別の金融資産ゼロ世帯の割合と金融資産保有額>
・収入はない:金融資産ゼロ60.7%、平均値852万円・中央値0万円
・年収300万円未満:金融資産ゼロ39.1%、平均値887万円・中央値153万円
・年収300~500万円未満:金融資産ゼロ29.6%、平均値1027万円・中央値400万円
・年収500~750万円未満:金融資産ゼロ24.3%、平均値1138万円・中央値520万円
・年収750~1000万円未満:金融資産ゼロ16.7%、平均値1747万円・中央値1130万円
・年収1000~1200万円未満:金融資産ゼロ11.5%、平均値2464万円・中央値1700万円
・年収1200万円以上:金融資産ゼロ9.9%、平均値4634万円・中央値2670万円
※金融資産を保有していない世帯を含む。
※中央値:資料を大きさの順に並べたとき、全体の中央にくる値(資料の個数が偶数のときは中央にある二つの値の平均値)。
この結果をみると、年収1200万円以上の世帯でも約1割が貯蓄ゼロいう結果がわかります。そして、世帯所得の平均といわれる約546万円のゾーンにあたる年収500~750万未満の世帯でも、約2.5割が貯蓄ゼロという厳しい結果が示されています。
ちなみに、全体の平均値は1151万円、中央値は380万円となっています。これらのデータから、「貯蓄のある・なし」の二極化が進んでいる状況だということがわかります。
老後資金と日本と世界の定年問題
一般的に老後資金は夫婦で3000万円以上が必要だといわれています。しかし、データからは現役世代にそれだけのお金を貯蓄するのはとても大変で難しいことがうかがえます。そして、現在多くの企業や自治体で採用している「60歳定年」を文字通りに受け入れてしまうと、いわゆる「老後破綻」となる世帯が相当数生まれてしまいそうです。ここで世界にも目を向けてみましょう。実は定年制は万国共通ではありません。アメリカ、カナダ、イギリスなどのように、定年制が禁じられている国もあります。また、定年制がある国でもその年齢はさまざまです。ドイツでは日本同様の深刻な高齢化により67歳まで引き上げが実施され、さらになる引き上げも検討されているそうです。
他方、マレーシアやタイのように経済発展の著しい国では、労働力やノウハウ確保のために定年の引き上げが実施されています。
日本型定年制の改革
日本の定年制は明治時代に誕生しました。荻原勝氏の『定年制の歴史』(日本労働協会)によると、日本で最初に退職年齢を定めたのは海軍が設立した海軍火薬製造所で、1887(明治20)年に制定された「職工規定」に、「年齢満五十五年ヲ停年」と規定されています。その後、戦争時期など一時的な中断を経ながらも、終身雇用や年功序列型賃金制度と関連した、いわゆる「日本的経営」とともに普及していきました。また、普及の過程で社会情勢の変化や労働組合の要求などに応じて定年年齢も上がっていき、1955(昭和30)~65(昭和40)年頃にかけて、60歳を定年とする企業が大半を占めるようになりました。
現状の日本社会は、さらなる高齢化の進展、健康寿命や平均寿命の伸長と定年年齢のバランスが取れていないこと、人手不足などからも定年年齢の引き上げの要請が高まっています。そうした社会情勢や要請をうけて、政府は2019年度から段階的に「65歳定年」へ延長する検討に入り、多くの企業での検討や取り組みも始まっています。
人生100年時代、「生涯現役」のススメ
ただし、定年制の改革を待っている間に定年になってしまえば、貯金を使う生活を余儀なくされてしまうかもしれません。また、さらなる社会情勢の変化によって、現在は機能しているセーフティネットも十分には機能しなくなることも考えられます。「老後破綻」にならないためには、まずは自発的に特定の企業や職種にこだわらない働き方の見直しや、定年後のセカンドライフを含めた収入確保や資金運用の設計が必要ではないでしょうか。60歳までに定年後のための十分な貯蓄は難しくても、例えば、健康寿命が続くかぎり現役時代を延長し、多少は減ったとしても収入を得る生活を長く続けることができれば、生活の質を担保し、安心した日々を送れるはずです。
人生100年時代といわれる現代、「生涯現役」を貫く準備と覚悟が必要かもしれません。
<参考文献・参考サイト>
『定年制の歴史』(荻原勝著、日本労働協会)
・家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成29年調査結果
https://www.shiruporuto.jp/public/data/movie/yoron/futari/2017/
『定年制の歴史』(荻原勝著、日本労働協会)
・家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 平成29年調査結果
https://www.shiruporuto.jp/public/data/movie/yoron/futari/2017/
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







