テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
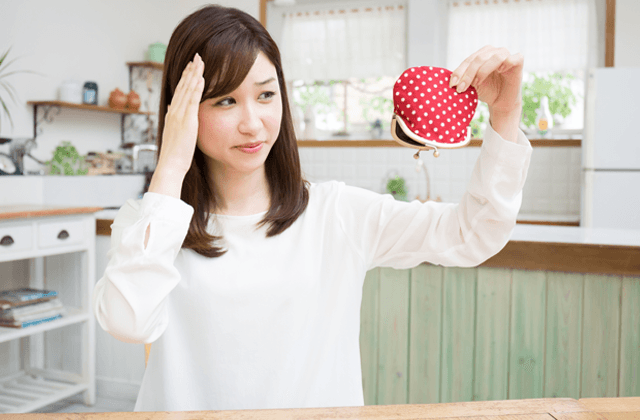
「お金を貯められない人」がやっている行動とは?
そろそろ貯蓄したいなあと考えている方も多いのではないでしょうか。安定した生活のためには、少ない額でも貯蓄を持つところがスタートです。わかっているけれど、なぜだかうまくいかないという方、またどうしたらいいのか分からないという方、ここで確認しましょう。
もちろん、安くなっているので買い物としてはオトクです。ですが、「安いから買う」では出費は増える一方です。消費に対して「計画性」がありません。もし、お金を貯めたい、と考えているならば、「安いから買う」は必要ありません。「安い」ことと「必要」ということは違います。「安い」ものではなく「必要」なものを買うという意識が貯蓄の第一歩です。
また、ビニール傘が家に溜まっている、なんとなくコンビニに寄ってしまう、ATMで頻繁にお金を引き出しているという方も要注意。これらの行動にも計画性がありません。さらにお金やモノの管理ができていません。こういった常態が継続すると「必要」の意識は薄らいでしまいます。
さらに大事なのは、リストアップしたモノの売り場以外に立ち寄らないこと。またリストアップしていたものの近くでも別のモノが赤く「セール」と書かれていたら要注意。それは必要ないという意識をしっかり保ち、目をそらしましょう。お金を貯めると決めたならば、衝動を伴うエリアには近づかないことです。
「千里の道も一歩から」「ローマは一日にして成らず」「塵も積もれば山となる」。これらは、よく聞く言葉ですが、お金を貯めるためには最良の発想だと思われます。しかしこれはお金を使わないことや、何でも安く済ませるということではありません。何にお金を使うか、何を安く済ませるか自己管理して計画性を持つこと。これが、結果的に無理のない貯蓄につながります。
それでも、どうしても計画性が持てないという方は、銀行で毎月一定額の積み立て預金や、証券会社で積み立て投資信託を設定することをお勧めします。使えるお金を自分で制限して強制的に貯蓄に回す方法です。積み立て預金の場合、たとえば月に5000円ずつでも、1年後には6万円にはなります。さらにこの先もしかすると金利が上がるかもしれません。はじめは意識を変えるところで少々きついかもしれません。しかし時間が経つにつれて豊かになれる、と考えれば、案外ワクワクするものではないでしょうか。
お金を貯められない人がやっている行動
スーパーでレジに並んでいるときに見かけるワゴンセール。赤いシールで「半額!」と目に入るとついカゴに入れていませんか。また、靴屋さんで試着して鏡を見ていると、「今なら2足セットで3割引!」という貼り紙を見つけて2足目を探していませんか。さらにはデパートのセール会場の人込みで製品よりも値段や割引率に惹かれて商品を買っていませんか。もちろん、安くなっているので買い物としてはオトクです。ですが、「安いから買う」では出費は増える一方です。消費に対して「計画性」がありません。もし、お金を貯めたい、と考えているならば、「安いから買う」は必要ありません。「安い」ことと「必要」ということは違います。「安い」ものではなく「必要」なものを買うという意識が貯蓄の第一歩です。
また、ビニール傘が家に溜まっている、なんとなくコンビニに寄ってしまう、ATMで頻繁にお金を引き出しているという方も要注意。これらの行動にも計画性がありません。さらにお金やモノの管理ができていません。こういった常態が継続すると「必要」の意識は薄らいでしまいます。
買い物に行く前に必要なモノをリストアップ
貯蓄は衝動の戦いです。といってもやはり買い物は楽しいしストレス解消にもなります。大事なことは、「必要」なものを買うための意思を固めること。そのために買い物をするときには買うモノをスマホにリストアップしておくことをお勧めします。さらに大事なのは、リストアップしたモノの売り場以外に立ち寄らないこと。またリストアップしていたものの近くでも別のモノが赤く「セール」と書かれていたら要注意。それは必要ないという意識をしっかり保ち、目をそらしましょう。お金を貯めると決めたならば、衝動を伴うエリアには近づかないことです。
何にお金を使うべきか
生活するために必要なモノやコトは多くあります。心身を健康に保つ食事、美容、文化的活動、運動、大切な人と過ごすための時間などなど。うまくやりくりできれば、貯蓄のためとはいえこれらの費用を削る必要はないでしょう。もっといえば、むしろこういった場面でしっかりお金を使えるように、「今必要でない出費」や「衝動に任せた出費」を適切に抑えることがポイントなのです。「千里の道も一歩から」「ローマは一日にして成らず」「塵も積もれば山となる」。これらは、よく聞く言葉ですが、お金を貯めるためには最良の発想だと思われます。しかしこれはお金を使わないことや、何でも安く済ませるということではありません。何にお金を使うか、何を安く済ませるか自己管理して計画性を持つこと。これが、結果的に無理のない貯蓄につながります。
それでも、どうしても計画性が持てないという方は、銀行で毎月一定額の積み立て預金や、証券会社で積み立て投資信託を設定することをお勧めします。使えるお金を自分で制限して強制的に貯蓄に回す方法です。積み立て預金の場合、たとえば月に5000円ずつでも、1年後には6万円にはなります。さらにこの先もしかすると金利が上がるかもしれません。はじめは意識を変えるところで少々きついかもしれません。しかし時間が経つにつれて豊かになれる、と考えれば、案外ワクワクするものではないでしょうか。
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










