テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
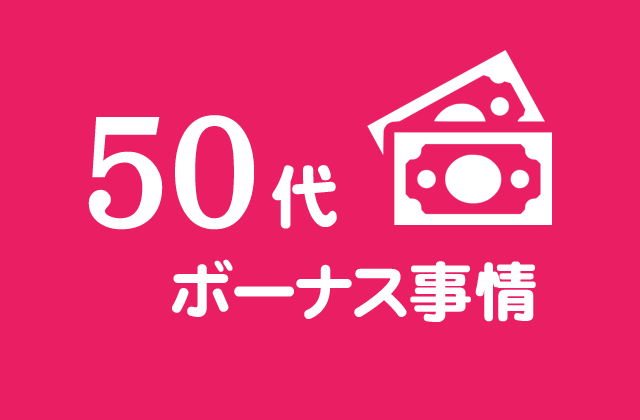
年収ピークの50代、驚くべきボーナスの実態
2019年に日本生命が契約者を対象とした「夏のボーナス」アンケートによると、2019年の夏、50代の人がもらったボーナスは男性88.2万円、女性43.4万円で、男女平均では76.7万円でした。
厚生労働省の資料によると、大卒の新入社員を含む20~24歳の平均金額は39.3万円。単純計算すると夏・冬それぞれの支給額は約19.7万円です。20代後半になると、年間で約67万と平均金額が大きく上昇し、その後も平均金額は右肩上がりで、50~54歳になると年間のボーナス支給額は平均128.8万円とピークを迎え、55~59歳で122.4万円と減衰していく傾向にあります。
これは、50代半ばで役職定年などを迎えることなどがその原因です。定年は60歳から65歳まで延長される企業が増えていても、50代後半以降の収入はなかなか厳しいということができそうです。
[50代後半になってもボーナスが上がる産業]
※産業:50~54歳/55~59歳
・教育・学習支援業:180.2万円/195.9万円
・鉱業,採石業,砂利採取業:142.9万円/453.3万円
・医療,福祉:85.0万円/85.2万円
・運輸・郵便業:73.4万円/79.1万円
・他に分類されないサービス業:63.2万円/64.4万円
このように、50代後半になっても賞与の伸びが止まらない産業もある一方、減額の著しい産業もあります。
[50代後半でボーナスがかなり減る産業]
※産業:50~54歳/55~59歳
・金融業、保険業:221.5万円/159.2万円
・宿泊業、飲食サービス業:46.2万円/41.1万円
・不動産業、物品賃貸業:164.1万円/136.3万円
金融業、保険業での減額はかなり大きく、50代後半でボーナスがかなり減る産業については、やはり役職定年に関係しているように推察されます。
50代後半になっても住宅ローンなどが続いている場合は、厳しい現実と言わざるをえない状況です。
50代のボーナス
ボーナスの支給額は毎年変動します。ここ5年間の平均は35万円以上、特に2018年のボーナスは、夏冬ともに38万円以上と、1~3万円ほど増額の傾向にあります。厚生労働省の資料によると、大卒の新入社員を含む20~24歳の平均金額は39.3万円。単純計算すると夏・冬それぞれの支給額は約19.7万円です。20代後半になると、年間で約67万と平均金額が大きく上昇し、その後も平均金額は右肩上がりで、50~54歳になると年間のボーナス支給額は平均128.8万円とピークを迎え、55~59歳で122.4万円と減衰していく傾向にあります。
これは、50代半ばで役職定年などを迎えることなどがその原因です。定年は60歳から65歳まで延長される企業が増えていても、50代後半以降の収入はなかなか厳しいということができそうです。
50代でボーナス支給の多い産業、少ない産業は?
厚生労働省の分類による16の産業種別で、50代のボーナス実態を調べてみました。全産業の平均は93.1万円(42.9歳/12.4年勤務)となっています。[50代後半になってもボーナスが上がる産業]
※産業:50~54歳/55~59歳
・教育・学習支援業:180.2万円/195.9万円
・鉱業,採石業,砂利採取業:142.9万円/453.3万円
・医療,福祉:85.0万円/85.2万円
・運輸・郵便業:73.4万円/79.1万円
・他に分類されないサービス業:63.2万円/64.4万円
このように、50代後半になっても賞与の伸びが止まらない産業もある一方、減額の著しい産業もあります。
[50代後半でボーナスがかなり減る産業]
※産業:50~54歳/55~59歳
・金融業、保険業:221.5万円/159.2万円
・宿泊業、飲食サービス業:46.2万円/41.1万円
・不動産業、物品賃貸業:164.1万円/136.3万円
金融業、保険業での減額はかなり大きく、50代後半でボーナスがかなり減る産業については、やはり役職定年に関係しているように推察されます。
50代後半になっても住宅ローンなどが続いている場合は、厳しい現実と言わざるをえない状況です。
<参考サイト>
・ニッセイ「夏のボーナス」に関する調査結果(2019年6月28日)
https://www.nissay.co.jp/news/2019/pdf/20190628.pdf
・厚生労働省:平成30年賃金構造基本統計調査
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001113395&tclass2=000001113397&tclass3=000001113412
・ニッセイ「夏のボーナス」に関する調査結果(2019年6月28日)
https://www.nissay.co.jp/news/2019/pdf/20190628.pdf
・厚生労働省:平成30年賃金構造基本統計調査
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450091&tstat=000001011429&cycle=0&tclass1=000001113395&tclass2=000001113397&tclass3=000001113412
人気の講義ランキングTOP20










