テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
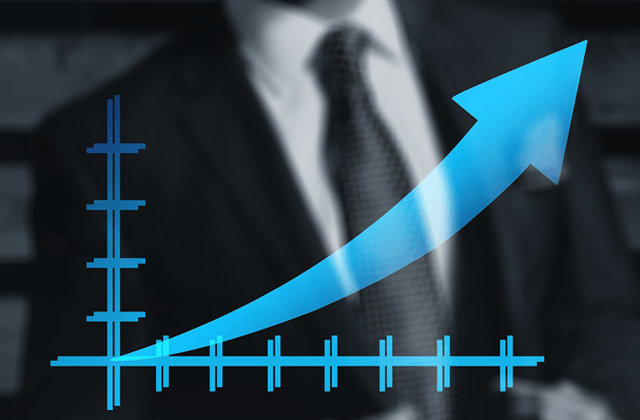
マックに王将…なぜあの会社は復活できたのか?
マックやマクドの愛称で親しまれる大手ファーストフード店の「日本マクドナルド」に、“餃子推し”の中華チェーン店といえばまず思い浮かぶ「餃子の王将」。どちらも知名度の高い社会インフラともいえるような飲食店ですが、さまざまなトラブルによって大きな売上げ減少に陥った過去があります。
また、マックや王将以外にも、危機的営業状況に陥りながらも復活した会社もあれば、残念ながら倒産した会社や業績悪化から回復できない会社も多々あります。その違いはどこにあるのでしょうか。マックや王将の復活劇をたどりつつ、考えてみたいと思います。
2013年から社長に就任していたサラ・カサノバ社長は「再建計画をやり切るのが私の責任」と述べ、「会社のカルチャー(文化)」の変革を決意します。具体的には職位に関係ない話し合いやワークショップを何度も開催し「マクドナルド スタッフ宣言」を決めるなど人材の採用と教育の強化を遂行、さらには47都道府県すべての訪問や店での聞き取り調査とそれらを受けた店舗改装やメニューの見直しなど、徹底した「ゲンバ」からの改革をおこないました。
ほかにもツイッターを使った消費者参加型プロモーション、アンケートアプリ「KODO(コド)」の開発やクーポン配布、不採算店舗の大規模な閉鎖、「マックカフェ バイ バリスタ」といった特別店の展開など大胆な改革を行います。そして2017年、8年ぶりの新商品となる「グラン」シリーズを発表。発売5日で300万食を販売する大ヒット商品となり、日本マクドナルド復活の象徴となりました。
しかしその後は市場の変化をよく読み、「鶏の唐揚げ」「酢豚」「炒飯」といった定番メニューを小皿で“ジャストサイズメニュー”として100~300円台でも提供したり、アルコールメニューにも工夫を加えたりと、「ちょい飲み」できる中華居酒屋としての機能を強化し、居酒屋需要も集めていきます。
また、2016年には創業の地である京都市内に女性向けのバルスタイルをイメージした新業態となる店舗「GYOZA OHSHO」をオープンしたり「にんにくゼロ餃子」を発売したりといったことでも一定の成果を得て、従来の客層とは違った新たな餃子シェアの獲得にも成功。徐々に売上げを回復していきます。
そして業績回復の決め手となったのは、店舗社員の教育を担うために2017年に新設された店長・副店長のための研修場としての「王将大学」と、店長の調理レベル向上を目的とした「王将調理道場」の存在が大きいと考えられています。これらの社内教育部門において再研修や学び合いを行うことにより、店舗や人材の管理といったノウハウだけでなく、飲食業の基本となる「QSC(品質・サービス・清潔さ)」の徹底といった理念の共有と社内融和を高めつつ、切磋琢磨する社風の醸成に成功しているといいます。
経営学者で慶應義塾大学商学部教授の菊澤研宗氏は『組織の不条理』において、「組織の本質は限定合理性である」と説き、合理的に行動することによってかえって組織が非効率や不正な事態に導かれて淘汰されていく「不条理な事例(合理的で非効率で非倫理的事例)」として、北海道拓殖銀行と大沢商会の倒産や山一証券の自主廃業などを挙げつつ、ひるがえって「条理な事例(合理的で効率的で倫理的事例)」での失敗から回復した例として、味の素の創業者一族の所有と経営の分離政策、ソニーのカンパニー制でのコスト節約の仕組みなどを取り上げています。
営利を目的とする会社である以上、合理性や効率性を高めることは当然ですが、それだけを求めすぎると、「会社内」の合理や効率がなによりも優先されることによって逆に不合理や非効率に陥ったり、それ以上に不正を行ってしまったり危機を見逃したりすることにもなりかねません。
そうならないためにも、広い視野を持って時代の動向をよく見極め、現場の声を傾聴しつつ人材教育を怠らないなど、時間や手間をかけた取り組みも必要になってきます。マックや王将など低迷や失敗から工夫と努力で復活した会社には、会社という組織にとっても、ビジネスパーソンという個人にとっても学べるべき点が多々あるのではないでしょうか。
また、マックや王将以外にも、危機的営業状況に陥りながらも復活した会社もあれば、残念ながら倒産した会社や業績悪化から回復できない会社も多々あります。その違いはどこにあるのでしょうか。マックや王将の復活劇をたどりつつ、考えてみたいと思います。
「ゲンバ」改革から誕生した「グラン」シリーズ
日本マクドナルドの危機の兆しは2011年の東日本大震災後の頃から始まり、2012年頃から売上げ減少が目立つようになってきたといいます。そして2014年の期限切れの鶏肉使用問題で赤字転落となり、さらに2015年の異物混入問題で大打撃を受け300億円を超える過去最悪の赤字を計上してしまいます。2013年から社長に就任していたサラ・カサノバ社長は「再建計画をやり切るのが私の責任」と述べ、「会社のカルチャー(文化)」の変革を決意します。具体的には職位に関係ない話し合いやワークショップを何度も開催し「マクドナルド スタッフ宣言」を決めるなど人材の採用と教育の強化を遂行、さらには47都道府県すべての訪問や店での聞き取り調査とそれらを受けた店舗改装やメニューの見直しなど、徹底した「ゲンバ」からの改革をおこないました。
ほかにもツイッターを使った消費者参加型プロモーション、アンケートアプリ「KODO(コド)」の開発やクーポン配布、不採算店舗の大規模な閉鎖、「マックカフェ バイ バリスタ」といった特別店の展開など大胆な改革を行います。そして2017年、8年ぶりの新商品となる「グラン」シリーズを発表。発売5日で300万食を販売する大ヒット商品となり、日本マクドナルド復活の象徴となりました。
ニーズへの対応強化と「王将大学」の開設
一方、餃子の王将を運営する王将フードサービスの危機は、東証1部上場企業に導いた“中興の祖”ともいわれる大東隆行四代目社長が、2013年に本社前で何者かに射殺されたことによって勃発します。また、2014年頃から宇都宮や浜松を代表するご当地餃子の流行や餃子をメインとする居酒屋の台頭など餃子市場に変化が興りましたが、この時期、餃子の王将はその変化に乗り遅れ、売上げ減少に陥ります。しかしその後は市場の変化をよく読み、「鶏の唐揚げ」「酢豚」「炒飯」といった定番メニューを小皿で“ジャストサイズメニュー”として100~300円台でも提供したり、アルコールメニューにも工夫を加えたりと、「ちょい飲み」できる中華居酒屋としての機能を強化し、居酒屋需要も集めていきます。
また、2016年には創業の地である京都市内に女性向けのバルスタイルをイメージした新業態となる店舗「GYOZA OHSHO」をオープンしたり「にんにくゼロ餃子」を発売したりといったことでも一定の成果を得て、従来の客層とは違った新たな餃子シェアの獲得にも成功。徐々に売上げを回復していきます。
そして業績回復の決め手となったのは、店舗社員の教育を担うために2017年に新設された店長・副店長のための研修場としての「王将大学」と、店長の調理レベル向上を目的とした「王将調理道場」の存在が大きいと考えられています。これらの社内教育部門において再研修や学び合いを行うことにより、店舗や人材の管理といったノウハウだけでなく、飲食業の基本となる「QSC(品質・サービス・清潔さ)」の徹底といった理念の共有と社内融和を高めつつ、切磋琢磨する社風の醸成に成功しているといいます。
会社経営は「合理と効率」だけでは足りない
マックや王将だけでなく、日々さまざまな会社で、興隆や低迷、復活や倒産が起こっています。その中にはマックや王将のような、多くの人が知っている大企業も少なくありません。経営学者で慶應義塾大学商学部教授の菊澤研宗氏は『組織の不条理』において、「組織の本質は限定合理性である」と説き、合理的に行動することによってかえって組織が非効率や不正な事態に導かれて淘汰されていく「不条理な事例(合理的で非効率で非倫理的事例)」として、北海道拓殖銀行と大沢商会の倒産や山一証券の自主廃業などを挙げつつ、ひるがえって「条理な事例(合理的で効率的で倫理的事例)」での失敗から回復した例として、味の素の創業者一族の所有と経営の分離政策、ソニーのカンパニー制でのコスト節約の仕組みなどを取り上げています。
営利を目的とする会社である以上、合理性や効率性を高めることは当然ですが、それだけを求めすぎると、「会社内」の合理や効率がなによりも優先されることによって逆に不合理や非効率に陥ったり、それ以上に不正を行ってしまったり危機を見逃したりすることにもなりかねません。
そうならないためにも、広い視野を持って時代の動向をよく見極め、現場の声を傾聴しつつ人材教育を怠らないなど、時間や手間をかけた取り組みも必要になってきます。マックや王将など低迷や失敗から工夫と努力で復活した会社には、会社という組織にとっても、ビジネスパーソンという個人にとっても学べるべき点が多々あるのではないでしょうか。
<参考文献>
・『組織の不条理』(菊澤研宗著、中公文庫)
・『組織の不条理』(菊澤研宗著、中公文庫)
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










