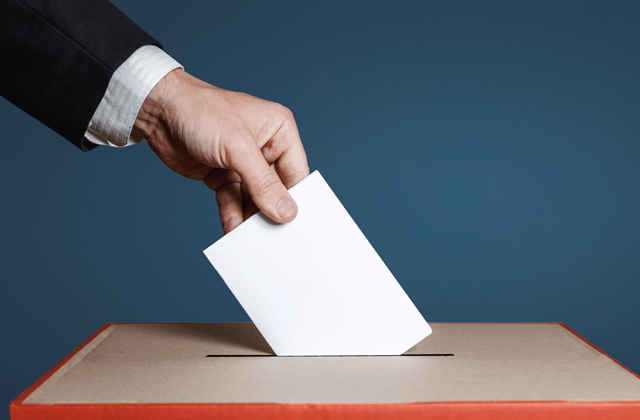
日本の選挙の投票率は海外と比較して低いのか?
2017年10月22日、選挙権が18歳に引き下げられて初めてとなる衆議院議員総選挙がおこなわれ、翌日、総務省より「投票率53.68%」の結果が発表されました。この投票率は、衆議院議員総選挙で戦後最低だった一つ前の2014年の52.66%をわずかに上回るだけの、戦後2番目の投票率の低さでした。
また同様に、2016年7月10日に選挙権が18歳に引き下げられて初めておこなわれた参議院議員通常選挙も「投票率54.70%」という結果で、衆参両院とも50%台という結果でした。なお、2010年代に入ってからはずっと、衆参両院ともに50%台で停滞している状態です。
そのため近年では、選挙のたびに「投票率の低さ」がメディアで叫ばれることとなっています。しかし日本の選挙の投票率は、海外と比較して本当に低いのでしょうか。各国の投票率と比較しつつ、検証してみたいと思います。
このデータでは、投票率とともにデータ集計時点での最新の選挙開催年のデータが記載されています。例えば日本の順位と投票率と選挙開催年は「日本52.66%(2014年)158位」となっており、この値は先述したとおり、戦後最低の衆議院総選挙の投票率になります。以降は「国名・投票率(選挙開催年)順位」の順に記載していきます。なお、近い値が列挙されることも多々あるため、順位はあくまでも参考的な目安としてください。
さて、上述したように、日本の投票率の順位は196ヵ国中158位でした。これはかなり低い順位になります。しかし、国によって国土面積や風土や人口、さらには政体や法律、経済状況や選挙方法も大きく違うため、一概に順位だけでは比較しにくいかもしれません。そこで比較対象として、日本以外のG7の6ヵ国をピックアップしてみたいと思います。
投票率の高い順に、イタリア75.19%(2013年)59位、ドイツ71.53%(2013年)84位、カナダ68.49%(2015年)97位、イギリス66.12%(2015年)107位、フランス55.40%(2012年)148位、アメリカ42.50%(2014年)185位、となっていました。こうしてみると、実はアメリカの方が日本よりも投票率が低く、またフランスともそれほど差がないことがわかります。
なお、イタリアが高い理由は後述します。ちなみに、日本の前後は、リトアニア52.93%(2012年)157位と、バーレーン52.60%(2014年)159位でした。
ベスト10は以下のように、ラオス99.69%(2011年)1位、ベトナム99.51%(2011年)2位、ルワンダ98.80%(2013年)3位、ナウル96.91 %(2013年)4位、ギニア96.45%(2004年)5位、シンガポール93.56 %(2004年)6位、オーストラリア93.23%(2013年)7位、エチオピア93.22%(2015年)8位、マルタ92.95%(2013年)9位、トルクメニスタン91.33%(2013年)10位、になります。
これらの国はどうして投票率が高いのでしょうか。その理由の一つに「義務投票制度と罰則適用」があります。例えば義務投票制を怠った者には、上記の国のうちナウルとオーストラリアでは罰金が課され、シンガポールでは選挙権の制限として“選挙人名簿からの抹消”がなされます。ちなみにオーストラリアでは1924年に義務投票制度が導入され、それ以降投票率が90%を下回ったことはありません。
なお、他にも義務投票制度を採用し、罰則適用が厳格な国に、ルクセンブルグ91.15%(2013年)11位/罰金、ベルギー89.37%(2014年)18位/罰金・選挙権の制限、フィジー84.60%(2014年)31位/罰金・入獄、キプロス78.70%(2011年)46位/罰金・入獄などがあり、概ね投票率が高くなっています。またトルコのように義務投票制度を採用しつつも罰則適用が厳格でなかったり、イタリアのように義務投票制度を採用しつつも罰則が定められていなかったりする国もあります。
ただし、驚異的な高投票率であり、有権者がほぼ全員投票していることになるベスト3のラオス・ベトナム・ルワンダは、いずれも罰則規定どころか義務投票制でもありません。また他の投票率の高い国々も、各国によって選挙制度に違いがあるとは思いますが、やはりその結果からは、国民一人ひとりの基礎的な政治への関心の高さがうかがえます。
その中でも今回は特に、スウェーデンを取り上げてみたいと思います。実はスウェーデンは若者の政治への関心や主権意識が高いことでも有名です。その背景には、充実した基礎教育があります。日本の小学校の教科書と比較しながらみていきましょう。
日本の小学校の高学年にあたるスウェーデンの「基礎学校」4~6年の学ぶ教科書では、選挙だけでなく政治に関わる記述も多く、さらに具体的に「民主的な選挙とは、どのようなものでしょうか?」の見出しで「投票は自主的なものです。そして、それは独裁制の国に住む人々がもっていない民主制の権利です。<中略>人々は、ある政党の主張のすべてに賛成できなくても、彼らがもっとも重要であると思う問題についてよい意見をもっているとすれば、その政党に投票します」と書かれています。
ところが、同年代の日本の小学校6年の教科書では、例えば「国会のはたらき」のなかで、「国会での話し合いをするのは、選挙で選ばれた国会議員です。<中略>わたしたちは、自分たちの代表者として国会議員を選ぶことで、政治に参加しているのです」や、「選挙権」を「国民に認められた権利で、国民が政治に参加し、願いを実現するうえで、とても大切なこと」のようにしか書かれていません。
このように、スウェーデンの国民は子どもの頃から民主的な選挙や政党政治の本質や利点・欠点を学びつつ、選挙を「自分の意見を表明できる機会」として捉えて、積極的に活用しているといえるのではないでしょうか。初等教育からの教育の違いも、後の大きな投票率の格差を生んでいるのかもしれません。
さらにスウェーデンの教科書は、「スウェーデンの政党は協力します」と見出しで高らかと宣言し、「国会の各政党は、さまざまな問題について異なる意見をもっていますが、お互いに協力し合っています。<中略>妥協とは、どの相手も完全には自分の望み通りにならない形で合意に達することです。全員が少しずつ譲歩して、全員が少しずつ自分の望みを達成するのです」と述べています。
ここで展開される“妥協”は、ともすれば各論が気に入らないために総論ごと否定し、話し合いや関わり合いを断って論争や討議を避けがちな姿勢や風潮とは真逆な、積極的な論理構築の態度であり、前向きな強い意思を感じます。また、民主主義や選挙の至らなさや矛盾を認めつつも、それを乗り越えて万民の創意や工夫によって、よりよい未来を作れる可能性が民主主義や選挙にあることも示してくれています。
シルバー民主主義が進み、若者は政治に興味を失う一方といわれる日本ですが、本来、投票権は民主主義において、何ものにも代えがたい尊い権利です。近い将来、義務や罰則のような制度を用いる必要に陥らないよう、投票権を十分に活かしきるために、民主的な選挙や政党政治の本質に立ち戻って学び直し、意識を改める必要があるのではないでしょうか。
また同様に、2016年7月10日に選挙権が18歳に引き下げられて初めておこなわれた参議院議員通常選挙も「投票率54.70%」という結果で、衆参両院とも50%台という結果でした。なお、2010年代に入ってからはずっと、衆参両院ともに50%台で停滞している状態です。
そのため近年では、選挙のたびに「投票率の低さ」がメディアで叫ばれることとなっています。しかし日本の選挙の投票率は、海外と比較して本当に低いのでしょうか。各国の投票率と比較しつつ、検証してみたいと思います。
日本の投票率および日本に似た国との比較
まずは、民主主義および選挙支援の研究を行う国際機関「民主主義・選挙支援国際研究所(IDEA)」が、2016年に公表した『Voter Turnout Trends around the World』に記載された196ヵ国の投票率データで、各国の国民議会選挙の投票率を比較してみたいと思います。このデータでは、投票率とともにデータ集計時点での最新の選挙開催年のデータが記載されています。例えば日本の順位と投票率と選挙開催年は「日本52.66%(2014年)158位」となっており、この値は先述したとおり、戦後最低の衆議院総選挙の投票率になります。以降は「国名・投票率(選挙開催年)順位」の順に記載していきます。なお、近い値が列挙されることも多々あるため、順位はあくまでも参考的な目安としてください。
さて、上述したように、日本の投票率の順位は196ヵ国中158位でした。これはかなり低い順位になります。しかし、国によって国土面積や風土や人口、さらには政体や法律、経済状況や選挙方法も大きく違うため、一概に順位だけでは比較しにくいかもしれません。そこで比較対象として、日本以外のG7の6ヵ国をピックアップしてみたいと思います。
投票率の高い順に、イタリア75.19%(2013年)59位、ドイツ71.53%(2013年)84位、カナダ68.49%(2015年)97位、イギリス66.12%(2015年)107位、フランス55.40%(2012年)148位、アメリカ42.50%(2014年)185位、となっていました。こうしてみると、実はアメリカの方が日本よりも投票率が低く、またフランスともそれほど差がないことがわかります。
なお、イタリアが高い理由は後述します。ちなみに、日本の前後は、リトアニア52.93%(2012年)157位と、バーレーン52.60%(2014年)159位でした。
投票率の高い国と「義務投票制度」の関係
ではいよいよ、日本とは対照的な投票率の高い国もみてみましょう。ベスト10は以下のように、ラオス99.69%(2011年)1位、ベトナム99.51%(2011年)2位、ルワンダ98.80%(2013年)3位、ナウル96.91 %(2013年)4位、ギニア96.45%(2004年)5位、シンガポール93.56 %(2004年)6位、オーストラリア93.23%(2013年)7位、エチオピア93.22%(2015年)8位、マルタ92.95%(2013年)9位、トルクメニスタン91.33%(2013年)10位、になります。
これらの国はどうして投票率が高いのでしょうか。その理由の一つに「義務投票制度と罰則適用」があります。例えば義務投票制を怠った者には、上記の国のうちナウルとオーストラリアでは罰金が課され、シンガポールでは選挙権の制限として“選挙人名簿からの抹消”がなされます。ちなみにオーストラリアでは1924年に義務投票制度が導入され、それ以降投票率が90%を下回ったことはありません。
なお、他にも義務投票制度を採用し、罰則適用が厳格な国に、ルクセンブルグ91.15%(2013年)11位/罰金、ベルギー89.37%(2014年)18位/罰金・選挙権の制限、フィジー84.60%(2014年)31位/罰金・入獄、キプロス78.70%(2011年)46位/罰金・入獄などがあり、概ね投票率が高くなっています。またトルコのように義務投票制度を採用しつつも罰則適用が厳格でなかったり、イタリアのように義務投票制度を採用しつつも罰則が定められていなかったりする国もあります。
ただし、驚異的な高投票率であり、有権者がほぼ全員投票していることになるベスト3のラオス・ベトナム・ルワンダは、いずれも罰則規定どころか義務投票制でもありません。また他の投票率の高い国々も、各国によって選挙制度に違いがあるとは思いますが、やはりその結果からは、国民一人ひとりの基礎的な政治への関心の高さがうかがえます。
小学生の教科書に書かれた「選挙」の違い
上記で紹介した国以外にも、罰則規定や義務投票制投票率がなくとも投票率の高い国々があります。例えば北欧諸国がそれで、デンマーク85.89%(2015年)25位、スウェーデン85.81%(2014年)26位、アイスランド81.44%(2013年)35位、ノルウェー78.23%(2013年)47位、フィンランド66.85%(2015年)102位となっています。その中でも今回は特に、スウェーデンを取り上げてみたいと思います。実はスウェーデンは若者の政治への関心や主権意識が高いことでも有名です。その背景には、充実した基礎教育があります。日本の小学校の教科書と比較しながらみていきましょう。
日本の小学校の高学年にあたるスウェーデンの「基礎学校」4~6年の学ぶ教科書では、選挙だけでなく政治に関わる記述も多く、さらに具体的に「民主的な選挙とは、どのようなものでしょうか?」の見出しで「投票は自主的なものです。そして、それは独裁制の国に住む人々がもっていない民主制の権利です。<中略>人々は、ある政党の主張のすべてに賛成できなくても、彼らがもっとも重要であると思う問題についてよい意見をもっているとすれば、その政党に投票します」と書かれています。
ところが、同年代の日本の小学校6年の教科書では、例えば「国会のはたらき」のなかで、「国会での話し合いをするのは、選挙で選ばれた国会議員です。<中略>わたしたちは、自分たちの代表者として国会議員を選ぶことで、政治に参加しているのです」や、「選挙権」を「国民に認められた権利で、国民が政治に参加し、願いを実現するうえで、とても大切なこと」のようにしか書かれていません。
このように、スウェーデンの国民は子どもの頃から民主的な選挙や政党政治の本質や利点・欠点を学びつつ、選挙を「自分の意見を表明できる機会」として捉えて、積極的に活用しているといえるのではないでしょうか。初等教育からの教育の違いも、後の大きな投票率の格差を生んでいるのかもしれません。
さらにスウェーデンの教科書は、「スウェーデンの政党は協力します」と見出しで高らかと宣言し、「国会の各政党は、さまざまな問題について異なる意見をもっていますが、お互いに協力し合っています。<中略>妥協とは、どの相手も完全には自分の望み通りにならない形で合意に達することです。全員が少しずつ譲歩して、全員が少しずつ自分の望みを達成するのです」と述べています。
ここで展開される“妥協”は、ともすれば各論が気に入らないために総論ごと否定し、話し合いや関わり合いを断って論争や討議を避けがちな姿勢や風潮とは真逆な、積極的な論理構築の態度であり、前向きな強い意思を感じます。また、民主主義や選挙の至らなさや矛盾を認めつつも、それを乗り越えて万民の創意や工夫によって、よりよい未来を作れる可能性が民主主義や選挙にあることも示してくれています。
シルバー民主主義が進み、若者は政治に興味を失う一方といわれる日本ですが、本来、投票権は民主主義において、何ものにも代えがたい尊い権利です。近い将来、義務や罰則のような制度を用いる必要に陥らないよう、投票権を十分に活かしきるために、民主的な選挙や政党政治の本質に立ち戻って学び直し、意識を改める必要があるのではないでしょうか。
<参考文献・参考サイト>
・『話したくなる世界の選挙』(コンデックス情報研究所編、清水書院)
・『小学社会 6下』(有田和正ほか著、教育出版)
・『新編 新しい社会6下』(北俊夫ほか著、東京書籍)
・『スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む』(ヨーラン・スバネリッド著、鈴木賢志・明治大学国際日本学部鈴木ゼミ編訳、新評論)
・『Voter Turnout Trends around the World』
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
・「義務投票制を採用している国」
https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/senkyo/school.files/w-gimu.pdf
・総務省:国政選挙における年代別投票率について
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/
・総務省:国政選挙における投票率の推移
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/ritu/
・『話したくなる世界の選挙』(コンデックス情報研究所編、清水書院)
・『小学社会 6下』(有田和正ほか著、教育出版)
・『新編 新しい社会6下』(北俊夫ほか著、東京書籍)
・『スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む』(ヨーラン・スバネリッド著、鈴木賢志・明治大学国際日本学部鈴木ゼミ編訳、新評論)
・『Voter Turnout Trends around the World』
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/voter-turnout-trends-around-the-world.pdf
・「義務投票制を採用している国」
https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/senkyo/school.files/w-gimu.pdf
・総務省:国政選挙における年代別投票率について
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/nendaibetu/
・総務省:国政選挙における投票率の推移
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/sonota/ritu/
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







