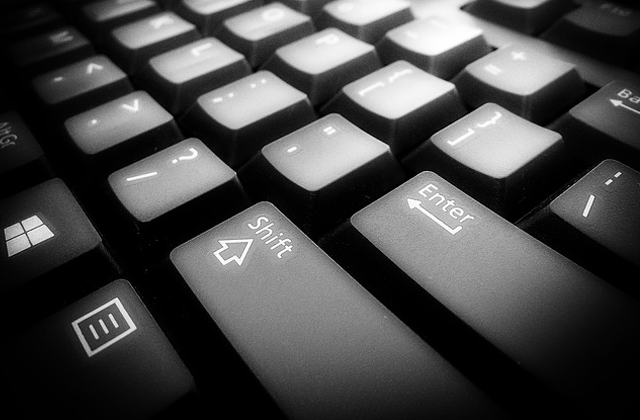
「社畜」になりやすい人の特徴は?
シナリオ通りに進めば働き方改革はみんなを幸せにするはずですが、実際の職場からは「残業規制をまともに守ると、下請けにしわ寄せが集まる」「時間内に業務を終わらせるため、職場の雰囲気がピリピリしている」と、あまりかんばしくない声も聞こえます。
さらに、大きな問題として、自称・他称を問わず「社畜」の人たちの意識をどうすればいいのかということがあります。まず、仕事熱心な社員と社畜との線引きについて、考えてみましょう。
この言葉、1990年の流行語としてあげられたのが始まりだというので、まさに平成とともに生き延びてきたわけです。会社に飼われる「家畜」になぞらえているところから、自らの意思を放棄し、生殺与奪の権利を飼い主(雇用主)に預けてしまうような人を指しているのは明らかですね。
具体的にいうと、たいして意欲や忠誠心もないのにサービス残業や休日出勤、自宅への持ち帰り作業を言われるがままこなしてしまったり、上司の理不尽な要求に応じたりしてしまう人。要するに「会社に都合のいい人」が社畜として揶揄されてきたわけですが、昨今では「私は社畜」アピールする人が増えているため、自虐的な言い訳として用いられることも多くなっています。
さらに、「趣味がない」「家に帰っても特にすることが無い」人は要注意。どんな仕事にも達成感がつきもので、無趣味な人たちのプライドをくすぐってくれるからです。同様に「関心や視野が狭い」「頭が硬い」と自覚のある人、「大事なのは時間よりもお金」と割り切りがちな人は、気がつくと残業を前提としたスケジュールになり、心身を痛めつける「ドMな自虐傾向」が顔を出すことが考えられます。
職場での精神状態として、「仕事をがんばる自分に酔っている」ことはありませんか。仕事につきものの達成感が自家中毒を起こしている状態です。そこまでいかなくても、社畜には「怒られるのが嫌」だったり「他人からの評価を気にしすぎる」など、「見栄っ張り」が多いと言われます。理不尽な要求に対しても、Noを言えないのはそのため。本当は嫌なサービス残業、持ち帰り仕事を続けていると、「忙しさが善」という歪んだ価値観にどっぷり浸ってしまい、ついには思考停止に陥ります。
社畜と言っても特別な人ではないこと、誰でも足をとられがちなワナであることがわかりますよね。なかには「自分に自信がない割にプライドが高く、失敗を恐れている」などの厳しい指摘もありますが、慣れない仕事・ハードルの高い業務に挑むときには誰だってそうなりがちです。
「残業は進んで引き受けない」「有給休暇をとる」「休憩時間は必ず休む」など、働く人間として当然の権利を行使するときには、心の中で自分を「外国人」と見なしてみてはいかがでしょうか。あっさり割り切ることが決して反感を買うわけではない事実に気がつくことでしょう。
上司や同僚の言いなりになっている自覚がある人は、「仕事以外の雑談のとき、上司や同僚に反論してみる」ことをお勧めします。たとえばプロ野球やサッカーではどこがひいきなのか、今朝のニュースをチェックしてどんな感想を持ったのか。そんなことまで、目の前の相手に唯々諾々と従う必要はまったくないのです。
思考停止から抜け出した途端、会社に行くのが憂うつになってしまったときは、その原因がどこにあるかを自己分析してみるのも手です。仕事そのものが原因の場合、社内外のコミュニケーションに原因がある場合、自分のメンタル不調が原因の場合、自分の体調不良が原因の場合と大きく4つに分けて、原因を探っていきましょう。
自分のモチベーションを管理するのは自分次第。健康的な会社ライフを過ごしましょう!
さらに、大きな問題として、自称・他称を問わず「社畜」の人たちの意識をどうすればいいのかということがあります。まず、仕事熱心な社員と社畜との線引きについて、考えてみましょう。
社畜とは「会社に飼い慣らされている人」?
「社畜とは、主に日本で、社員として勤めている会社に飼い慣らされ、自分の意思と良心を放棄し、サービス残業や転勤も厭わない奴隷(家畜)と化した賃金労働者の状態を揶揄したものである。「会社+家畜」から来た造語かつ俗語で、「会社人間」や「企業戦士」などよりも、外部から馬鹿にされる意味合いを持つ。」(Wikipedia)この言葉、1990年の流行語としてあげられたのが始まりだというので、まさに平成とともに生き延びてきたわけです。会社に飼われる「家畜」になぞらえているところから、自らの意思を放棄し、生殺与奪の権利を飼い主(雇用主)に預けてしまうような人を指しているのは明らかですね。
具体的にいうと、たいして意欲や忠誠心もないのにサービス残業や休日出勤、自宅への持ち帰り作業を言われるがままこなしてしまったり、上司の理不尽な要求に応じたりしてしまう人。要するに「会社に都合のいい人」が社畜として揶揄されてきたわけですが、昨今では「私は社畜」アピールする人が増えているため、自虐的な言い訳として用いられることも多くなっています。
社畜になりやすい人の特徴は?
社畜になりやすい人の特徴として、まず「職場に仲のいい同僚がいない」「パートナーがいない」「会社の外に友達がいない」などの孤独の問題が挙げられます。今の状況を打ち明け、共有できる相手がいないと、社畜的な行動は歯止めが効かなくなっていきます。さらに、「趣味がない」「家に帰っても特にすることが無い」人は要注意。どんな仕事にも達成感がつきもので、無趣味な人たちのプライドをくすぐってくれるからです。同様に「関心や視野が狭い」「頭が硬い」と自覚のある人、「大事なのは時間よりもお金」と割り切りがちな人は、気がつくと残業を前提としたスケジュールになり、心身を痛めつける「ドMな自虐傾向」が顔を出すことが考えられます。
職場での精神状態として、「仕事をがんばる自分に酔っている」ことはありませんか。仕事につきものの達成感が自家中毒を起こしている状態です。そこまでいかなくても、社畜には「怒られるのが嫌」だったり「他人からの評価を気にしすぎる」など、「見栄っ張り」が多いと言われます。理不尽な要求に対しても、Noを言えないのはそのため。本当は嫌なサービス残業、持ち帰り仕事を続けていると、「忙しさが善」という歪んだ価値観にどっぷり浸ってしまい、ついには思考停止に陥ります。
社畜と言っても特別な人ではないこと、誰でも足をとられがちなワナであることがわかりますよね。なかには「自分に自信がない割にプライドが高く、失敗を恐れている」などの厳しい指摘もありますが、慣れない仕事・ハードルの高い業務に挑むときには誰だってそうなりがちです。
脱・社畜を思い立ったら、やるべきこと
狭い日本、お互いに足の引っ張りあいをするのはやめて、社畜から抜け出す方法を試してみましょう。ただし脱社畜するからといって、会社を辞める必要はありません。仕事熱心な社員でありつつ、主体的に動けるようにすればいいのです。「残業は進んで引き受けない」「有給休暇をとる」「休憩時間は必ず休む」など、働く人間として当然の権利を行使するときには、心の中で自分を「外国人」と見なしてみてはいかがでしょうか。あっさり割り切ることが決して反感を買うわけではない事実に気がつくことでしょう。
上司や同僚の言いなりになっている自覚がある人は、「仕事以外の雑談のとき、上司や同僚に反論してみる」ことをお勧めします。たとえばプロ野球やサッカーではどこがひいきなのか、今朝のニュースをチェックしてどんな感想を持ったのか。そんなことまで、目の前の相手に唯々諾々と従う必要はまったくないのです。
思考停止から抜け出した途端、会社に行くのが憂うつになってしまったときは、その原因がどこにあるかを自己分析してみるのも手です。仕事そのものが原因の場合、社内外のコミュニケーションに原因がある場合、自分のメンタル不調が原因の場合、自分の体調不良が原因の場合と大きく4つに分けて、原因を探っていきましょう。
自分のモチベーションを管理するのは自分次第。健康的な会社ライフを過ごしましょう!
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部







