テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
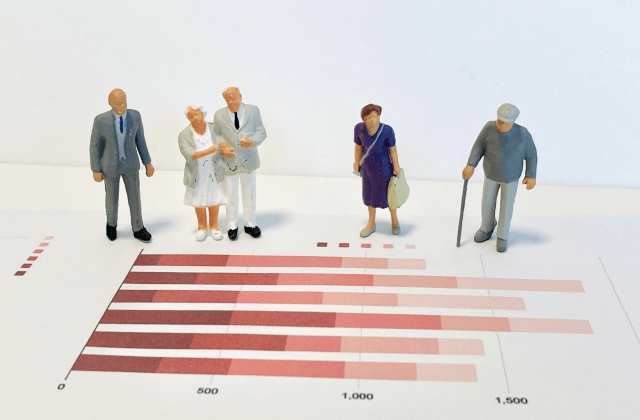
なぜ女性の方が長生きなのか?
2022年7月に厚生労働省が発表した「令和3(2021)年簡易生命表」によると、2021年の日本人の平均寿命は男性81.47歳/女性87.57歳と、男女差は6.1歳となっています。
世界的にも男性より女性の方が平均寿命は長いようです。では、なぜ女性の方が長生きなのでしょうか?理由や要因を探ってみたいと思います。
「エストロゲン(エストロジェン)」と呼ばれる女性ホルモンには脂質代謝という働きがあり、十分に分泌されている期間(生理開始から閉経まで)は、コレステロール値を男性より低い値に抑えられます。余分なコレステロールを抑えることは血栓をつくらないことにつながり、動脈硬化や心血管系の病気の発症リスクの低下につながっています。また、エストロゲンはストレス耐性や免疫力を高める働きもあるといわれています。
(2)善玉ホルモン「アディポネクチン」の分泌量の多さ
脂肪細胞から分泌される善玉ホルモンの「アディポネクチン」には、動脈硬化をおさえる作用があります。アディポネクチンは男女ともに分泌されているホルモンですが、女性の血液中には男性の2倍以上の量が分泌されています。
(3)基礎代謝が低い→活性酸素の産生が少ない→老化の進行が遅い
活性酸素(呼吸によって体内に取り込まれた酸素の一部が通常よりも活性化された状態になること)は身体にとって必要なものであると同時に、過剰になると細胞傷害をもたらします。しかし、基礎代謝(生命を維持するために必要な最小のエネルギー)が低いとエネルギーを生み出すための酸素の消費量が少ないため、活性酸素ができにくくなります。そのため、男性より活性酸素の産生が少ない女性の方が、老化の進行が遅いといわれています。
(4)社会・文化的要因
女性の方が、思慮深い(男性の方が危険な行動をとりやすい)、健康に対する意識が高い(食生活や定期検診など日頃から自身の健康を気にした行動をとる)、社会的なネットワークをつくるのが上手い(適切な人間関係を築きつつ死に至るストレスともいえる孤独に陥りにくい)――など、社会・文化的要因からも女性の方が長生きしやすいといわれています。
(5)妊娠・出産による死亡リスクの低下
戦後に女性の寿命が著しく延びた要因として、周産期医療や女性医学の発展が挙げられます。妊娠・出産は成人女性の高死亡リスクを優位に高める大きな要因であり、また、適切な周産期を過ごせないことはその後の健康、ひいては寿命を損ねることにも直結します。妊娠・出産によるリスクが低下したことが、女性の長寿につながっています。
なぜ疾患にも性差があるのかといえば、例えば上記で紹介したエストロゲンとアディポネクチンの作用が心疾患や脳血管疾患の発症のリスクをおさえることや、生活習慣が良好でストレス耐性や免疫力も強い女性の方がかんの発症を抑制したりすることなどがあると考えられています。
では、長生きした女性はどのように生き、どのような死を迎えるのでしょうか。医学博士で特に脳の性差を専門とする田中(貴邑冨)久子氏が「男はがんで壮絶に死ぬが、女は老衰で枯れ木のように死ぬ」と述べているように、たとえリスクの高い病気に罹患せずに長生きできた女性であったとしても、加齢によるリスクは避けられません。
また、女性は加齢とともに骨粗鬆症やアルツハイマー病の発症率が男性よりも有意に高くなる傾向があるとされています。長生きは素晴らしいことですが、骨粗鬆症で寝たきりになったりアルツハイマー病や認知症を発症したりしては、QOL(クオリティ・オブ・ライフ;生活の質)を著しく下げることにもなりかねません。
「倒れない男性・枯れない女性」となるためにも、性差の特性を尊重したり性差の特徴から学びあったりすることが、今日と未来を生きるすべての人々に求められています。
世界的にも男性より女性の方が平均寿命は長いようです。では、なぜ女性の方が長生きなのでしょうか?理由や要因を探ってみたいと思います。
女性の方が長生きである5つの理由
(1)女性ホルモン「エストロゲン」の働き「エストロゲン(エストロジェン)」と呼ばれる女性ホルモンには脂質代謝という働きがあり、十分に分泌されている期間(生理開始から閉経まで)は、コレステロール値を男性より低い値に抑えられます。余分なコレステロールを抑えることは血栓をつくらないことにつながり、動脈硬化や心血管系の病気の発症リスクの低下につながっています。また、エストロゲンはストレス耐性や免疫力を高める働きもあるといわれています。
(2)善玉ホルモン「アディポネクチン」の分泌量の多さ
脂肪細胞から分泌される善玉ホルモンの「アディポネクチン」には、動脈硬化をおさえる作用があります。アディポネクチンは男女ともに分泌されているホルモンですが、女性の血液中には男性の2倍以上の量が分泌されています。
(3)基礎代謝が低い→活性酸素の産生が少ない→老化の進行が遅い
活性酸素(呼吸によって体内に取り込まれた酸素の一部が通常よりも活性化された状態になること)は身体にとって必要なものであると同時に、過剰になると細胞傷害をもたらします。しかし、基礎代謝(生命を維持するために必要な最小のエネルギー)が低いとエネルギーを生み出すための酸素の消費量が少ないため、活性酸素ができにくくなります。そのため、男性より活性酸素の産生が少ない女性の方が、老化の進行が遅いといわれています。
(4)社会・文化的要因
女性の方が、思慮深い(男性の方が危険な行動をとりやすい)、健康に対する意識が高い(食生活や定期検診など日頃から自身の健康を気にした行動をとる)、社会的なネットワークをつくるのが上手い(適切な人間関係を築きつつ死に至るストレスともいえる孤独に陥りにくい)――など、社会・文化的要因からも女性の方が長生きしやすいといわれています。
(5)妊娠・出産による死亡リスクの低下
戦後に女性の寿命が著しく延びた要因として、周産期医療や女性医学の発展が挙げられます。妊娠・出産は成人女性の高死亡リスクを優位に高める大きな要因であり、また、適切な周産期を過ごせないことはその後の健康、ひいては寿命を損ねることにも直結します。妊娠・出産によるリスクが低下したことが、女性の長寿につながっています。
「倒れない男性・枯れない女性」となるために
ところで、疾患の罹患率にも性差があることはご存知でしょうか。例えば、日本人の三大疾患ともいえる「悪性腫瘍(がん)」「心疾患」「脳血管疾患」は、すべて女性より男性の罹患率や死亡率が高くなっています。なぜ疾患にも性差があるのかといえば、例えば上記で紹介したエストロゲンとアディポネクチンの作用が心疾患や脳血管疾患の発症のリスクをおさえることや、生活習慣が良好でストレス耐性や免疫力も強い女性の方がかんの発症を抑制したりすることなどがあると考えられています。
では、長生きした女性はどのように生き、どのような死を迎えるのでしょうか。医学博士で特に脳の性差を専門とする田中(貴邑冨)久子氏が「男はがんで壮絶に死ぬが、女は老衰で枯れ木のように死ぬ」と述べているように、たとえリスクの高い病気に罹患せずに長生きできた女性であったとしても、加齢によるリスクは避けられません。
また、女性は加齢とともに骨粗鬆症やアルツハイマー病の発症率が男性よりも有意に高くなる傾向があるとされています。長生きは素晴らしいことですが、骨粗鬆症で寝たきりになったりアルツハイマー病や認知症を発症したりしては、QOL(クオリティ・オブ・ライフ;生活の質)を著しく下げることにもなりかねません。
「倒れない男性・枯れない女性」となるためにも、性差の特性を尊重したり性差の特徴から学びあったりすることが、今日と未来を生きるすべての人々に求められています。
<参考文献・参考サイト>
・『男が知りたい女のからだ』(河野美香著、講談社ブルーバックス)
・『がんで男は女の2倍死ぬ』(田中-貴邑冨久子著、朝日新書)
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・令和3年簡易生命表の概況 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life21/index.html
・老いにみる男女の違い | 健康長寿ネット
https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/Aging-and-Gender/oi-danjyochigai.html
・女性の方が寿命が長い3つの理由 | カンタン健康生活習慣
https://kenko.sawai.co.jp/healthy/201603.html
・女性の方が長生きな理由、男性は不慮の事故が多い - アスレシピ
https://athleterecipe.com/column/45/articles/202112170000499
・基礎代謝~女性が長生きする理由~|一般社団法人日本家族計画協会
http://www.jfpa.info/wh/body_information/detail/index.php?aid=59
・活性酸素と酸化ストレス | e-ヘルスネット(厚生労働省)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-04-003.html
・『男が知りたい女のからだ』(河野美香著、講談社ブルーバックス)
・『がんで男は女の2倍死ぬ』(田中-貴邑冨久子著、朝日新書)
・『デジタル大辞泉』(小学館)
・令和3年簡易生命表の概況 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life21/index.html
・老いにみる男女の違い | 健康長寿ネット
https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/Aging-and-Gender/oi-danjyochigai.html
・女性の方が寿命が長い3つの理由 | カンタン健康生活習慣
https://kenko.sawai.co.jp/healthy/201603.html
・女性の方が長生きな理由、男性は不慮の事故が多い - アスレシピ
https://athleterecipe.com/column/45/articles/202112170000499
・基礎代謝~女性が長生きする理由~|一般社団法人日本家族計画協会
http://www.jfpa.info/wh/body_information/detail/index.php?aid=59
・活性酸素と酸化ストレス | e-ヘルスネット(厚生労働省)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-04-003.html
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部










