テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
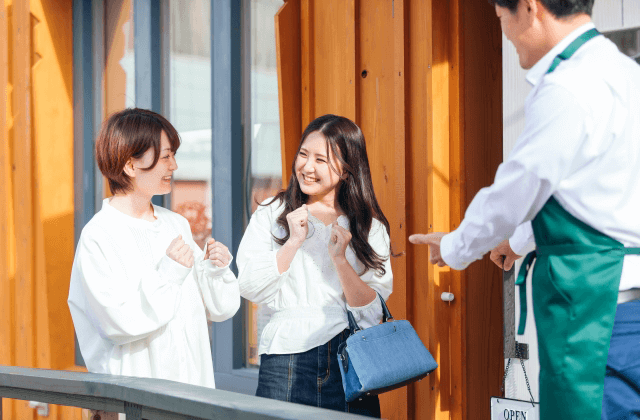
人数の数え方「○人」「○名」はどう違う?
人数を数える時、通常は「○人」といった数え方になります。しかし場合によっては「○名」と数える時もあれば、「第三者」の「○者」、「お三方」の「○方」といった呼び分けもあります。
人間でも、場面によって数え方が違う。では人間に似た生き物……おとぎ話に登場する人魚や天使、妖精たちだったらどうでしょうか。
今回は、そんな“人”の数え方の秘密に迫ります。
たとえば人気のお店の行列を見た時、どのくらいの人が並んでいるのか、その人数を数える時は「○人」を使います。
いっぽう、順番待ちのリストの記名欄には「○名様」と記載されており、順番が来るとお店の人が「○名様でお待ちの××様~」と呼びかけてきます。何となくですが「○人」よりも「○名」のほうが、改まった言い方に聞こえますよね。
またイベント会場ですと、実際にパフォーマンスに参加する人は「○名」と数えるのに対し、入場者数や観客については「入場者数は約3,000人」などといったように「○人」と数えます。
つまり「○名」と数える時は“相手が誰か特定できる”時。また、相手に対して“敬意を表する”場面に使われます。
いっぽう「○人」と数えるのは“相手が誰か特定できない”時。単純に頭数を数えたい場合に使います。また新聞や広報誌など、特に改まる必要のない場面も「○人」を使うことが多いです。
また、エレベーターのように収容人数に制限がある場所では「定員○人」ではなく「定員○名」と記していることがあります。こちらも、利用者に対し敬意を示す意味で使われていると考えられます。ただ実際は「人」「名」で使い分けが曖昧で、形式表現にとどまっていることもあるようです。
しかし、なぜわざわざ「人」「名」で使い分けるようになったのでしょうか。
実は江戸時代までは数え方は「人」のみで、「名」が使われ始めたのは明治期に入ってからとされています。「名」という数え方が生まれたきっかけは明治政府が定めた『戸籍法』。これにより国民一人一人の名前や性別、年齢などが記録され、そこから名前の「名」の数え方が用いられるようになりました。
富国強兵をうたう明治政府は、戸籍にもとづいて健康な成人男性を徴兵し、軍隊を編成しました。さらに「軍の報告書において隊員の人数は『名』と記すこと」と定めたのです。これは江戸時代から進化し、より組織だった近代的な軍隊になったということを、数え方を変えることで示そうとしたのだと考えられています。こうして「名」の数え方(=個人を特定する数え方)が浸透していきました。
普通、動物であれば「○匹」と数えますよね。しかし「姿形が人と似ている」「人と同じ言葉を話す」「人のような感情がある」など、より人に近く、身近に感じる場合は「○人」と数えます。
つまり、人間のように表情豊かで言葉を話し、人間に恋をすることもある人魚は「○人」という数え方になるのです。
これは、人にとって“どのような存在であるか”も関係しています。鬼や悪魔のように、たとえ姿形は多少人に似ていたとしても、人に対して害をなす邪悪な存在であれば「○匹(または○体)」を使い、逆に天使や妖精のように友好的、好意的に思える存在に対しては「○人」を使う……といった具合です。
ちなみに私たち日本人にも身近な神様(神道)の数え方は「○柱」です。詳細は割愛しますが、古来より日本人は樹木に対する畏敬の念があり「木には神様が宿っている」と考えられてきたためといわれています。
たとえば学校で行う「三者面談」という言葉があります。これは学校の教員、親、子どもの3人がそろって、それぞれの立場から話し合うというもの。つまり「者」は“その人が置かれた立場”を指す意味の単位となります。
関係する当事者以外の人を指す「第三者」や、人はみなそれぞれ立場や状況、考え方が違うことを意味する「三者三様」も、同じ考え方です。
そして「方」は、3人を示す「お三方」などのように使います。これは「3人」を丁寧に読んだ敬語表現で、同じく1人なら「お一方(おひとかた)」、2人なら「お二方(おふたかた)」になります。
もともと「方」は方角、場所、方法などさまざまに使われるため、それがいつしか人を数える時にも用いられるようになったと考えられます。「○人」をより丁寧にするための言葉なので、「お三方」=「3名様」と言い換えることができます。
自分が相手をどう見ているか、どのような印象を持っているかで、数え方は変わってくるのですね。
人間でも、場面によって数え方が違う。では人間に似た生き物……おとぎ話に登場する人魚や天使、妖精たちだったらどうでしょうか。
今回は、そんな“人”の数え方の秘密に迫ります。
「○人」「○名」はどう使い分けているのか
まずは「○人」「○」名について、それぞれの数え方をする場面を思い出してみましょう。たとえば人気のお店の行列を見た時、どのくらいの人が並んでいるのか、その人数を数える時は「○人」を使います。
いっぽう、順番待ちのリストの記名欄には「○名様」と記載されており、順番が来るとお店の人が「○名様でお待ちの××様~」と呼びかけてきます。何となくですが「○人」よりも「○名」のほうが、改まった言い方に聞こえますよね。
またイベント会場ですと、実際にパフォーマンスに参加する人は「○名」と数えるのに対し、入場者数や観客については「入場者数は約3,000人」などといったように「○人」と数えます。
つまり「○名」と数える時は“相手が誰か特定できる”時。また、相手に対して“敬意を表する”場面に使われます。
いっぽう「○人」と数えるのは“相手が誰か特定できない”時。単純に頭数を数えたい場合に使います。また新聞や広報誌など、特に改まる必要のない場面も「○人」を使うことが多いです。
また、エレベーターのように収容人数に制限がある場所では「定員○人」ではなく「定員○名」と記していることがあります。こちらも、利用者に対し敬意を示す意味で使われていると考えられます。ただ実際は「人」「名」で使い分けが曖昧で、形式表現にとどまっていることもあるようです。
しかし、なぜわざわざ「人」「名」で使い分けるようになったのでしょうか。
実は江戸時代までは数え方は「人」のみで、「名」が使われ始めたのは明治期に入ってからとされています。「名」という数え方が生まれたきっかけは明治政府が定めた『戸籍法』。これにより国民一人一人の名前や性別、年齢などが記録され、そこから名前の「名」の数え方が用いられるようになりました。
富国強兵をうたう明治政府は、戸籍にもとづいて健康な成人男性を徴兵し、軍隊を編成しました。さらに「軍の報告書において隊員の人数は『名』と記すこと」と定めたのです。これは江戸時代から進化し、より組織だった近代的な軍隊になったということを、数え方を変えることで示そうとしたのだと考えられています。こうして「名」の数え方(=個人を特定する数え方)が浸透していきました。
人魚の数え方は「○匹」?「○人」?
それでは本題である、人魚など“人に似ている”生物の数え方についてです。普通、動物であれば「○匹」と数えますよね。しかし「姿形が人と似ている」「人と同じ言葉を話す」「人のような感情がある」など、より人に近く、身近に感じる場合は「○人」と数えます。
つまり、人間のように表情豊かで言葉を話し、人間に恋をすることもある人魚は「○人」という数え方になるのです。
これは、人にとって“どのような存在であるか”も関係しています。鬼や悪魔のように、たとえ姿形は多少人に似ていたとしても、人に対して害をなす邪悪な存在であれば「○匹(または○体)」を使い、逆に天使や妖精のように友好的、好意的に思える存在に対しては「○人」を使う……といった具合です。
ちなみに私たち日本人にも身近な神様(神道)の数え方は「○柱」です。詳細は割愛しますが、古来より日本人は樹木に対する畏敬の念があり「木には神様が宿っている」と考えられてきたためといわれています。
「者」「方」の使い方
「人」「名」のほかにも「者」「方」といった数え方もありますが、それぞれの使い方はどうでしょうか。たとえば学校で行う「三者面談」という言葉があります。これは学校の教員、親、子どもの3人がそろって、それぞれの立場から話し合うというもの。つまり「者」は“その人が置かれた立場”を指す意味の単位となります。
関係する当事者以外の人を指す「第三者」や、人はみなそれぞれ立場や状況、考え方が違うことを意味する「三者三様」も、同じ考え方です。
そして「方」は、3人を示す「お三方」などのように使います。これは「3人」を丁寧に読んだ敬語表現で、同じく1人なら「お一方(おひとかた)」、2人なら「お二方(おふたかた)」になります。
もともと「方」は方角、場所、方法などさまざまに使われるため、それがいつしか人を数える時にも用いられるようになったと考えられます。「○人」をより丁寧にするための言葉なので、「お三方」=「3名様」と言い換えることができます。
自分が相手をどう見ているか、どのような印象を持っているかで、数え方は変わってくるのですね。
<参考サイト>
・人を数える「人」と「名」は何が違うの?→「名前を特定できている」か「いないか」(NHK チコちゃんに叱られる!)
https://xn--h9jua5ezakf0c3qner030b.com/21138.html
・広報Q&A 表記について知りたい(公益社団法人 日本広報協会)
https://www.koho.or.jp/useful/qa/hyouki/hyouki02.html
・人を数える時に使う「人」と「名」の差 2018年4月10日(TBS この差って何ですか?)
https://www.tbs.co.jp/konosa/old/20180410.html
・人を数える「人」と「名」は何が違うの?→「名前を特定できている」か「いないか」(NHK チコちゃんに叱られる!)
https://xn--h9jua5ezakf0c3qner030b.com/21138.html
・広報Q&A 表記について知りたい(公益社団法人 日本広報協会)
https://www.koho.or.jp/useful/qa/hyouki/hyouki02.html
・人を数える時に使う「人」と「名」の差 2018年4月10日(TBS この差って何ですか?)
https://www.tbs.co.jp/konosa/old/20180410.html
人気の講義ランキングTOP20










