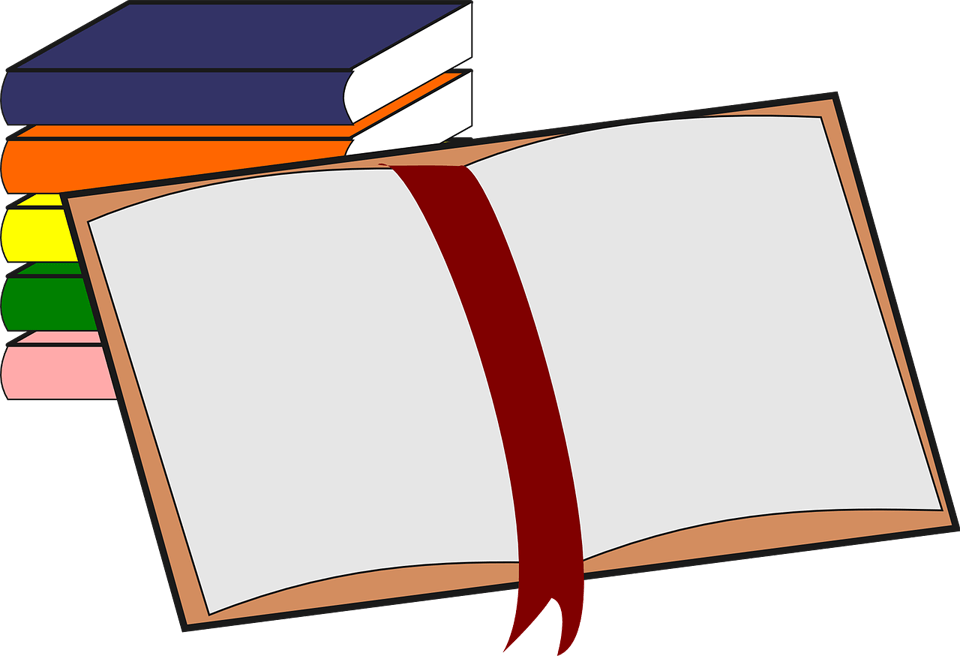●小説は正しく理解するための情報を提供し、考える機会を生むもの
―― 真山さんが描かれている小説は、日本や世界で闇になっている部分を暴いていくようなものが多いように思います。
真山 恐らくそれが、真山仁という小説家の評価だと思うのですが、実際は少し違います。(暴いていくために)戦っているわけではありません。戦うというよりもむしろ、できたらその扉を開けたくない人たちや光を当ててほしくない人たちに、「すいません、全部、見せてもらえませんか」と頼むのです。「偏った批判をするために書くのではありません。よいことも問題となる部分もすべてみせてほしい」と言います。そうして、原発の問題も書きましたし、『オペレーションZ』という小説では財務省や政治の問題も書きました。
今まで書いてきた小説ではさまざまなことを明るみに出しましたが、最初に評価してくださるのは、むしろその扉を開けてほしくなかっただろう人たちです。『ハゲタカ』でも、「この小説を読んで救われた」と最初に言ってくださったのは、外資系の投資銀行の人たちです。原発事故の問題に関連した小説『ベイジン』を書いた時、最初に泣きながら握手を求められたのは、原発で働いている人からでした。原発という所がどういうところで、何が危険で、そのために何をしているかということを「息子に胸張って初めて言える」とおっしゃっていました。
日本人は敵対構図が好きなので、原発村といえば「悪を暴く」となりがちです。確かに全部が善ではないでしょうが、全部が悪でもありません。そもそも世の中を善悪で考えること自体が、私は間違っていると思います。立場が逆転すれば善が悪になるわけですから。
ポイントは善悪を伝えることや白黒つけることではありません。暴くというより、正しく理解するための情報を提供して、「読者は考えてください。当事者も考えましょう」と提案するということです。
物語をつくるときに、善悪を付ける風習が日本にはあります。常に対峙するという対立構造として、良い人と悪い人をつくると、確かにそれは面白いのですが、面白いのであれば、現実はそんなに単純なものではない。
●小説は「人はなぜ生きるのか」を問い続けるヒントだ
真山 一言でいうと、小説は人がなぜ生きるのかを問い続けるヒントになるものだと思います。架空の人間を、現実に起きている社会の中...