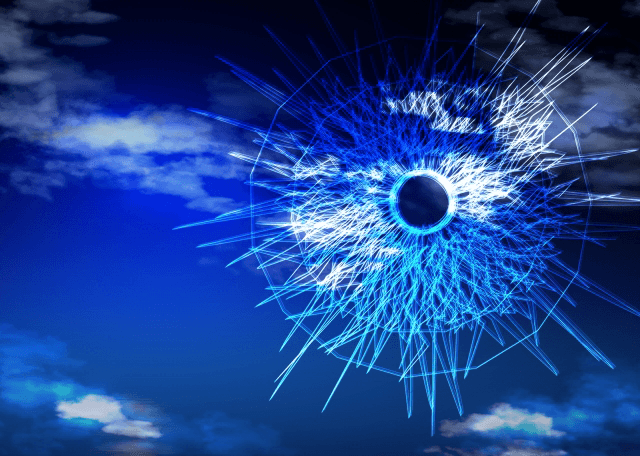●中東の崩壊プロセスは、ソ連崩壊のリプレイ
皆さん、こんにちは。前の2回に引き続き、中東で起きているパラダイムシフトとも言うべき大きな変動の性格について、引き続きお話ししてみたいと思います。
前の回で私は、中東において冷戦構造が再燃しつつある可能性と、そうした構造の出現に注意を払う必要性についてお話をしました。と言いましても、中東の状況が冷戦と全く同じだと申し上げたいわけではありません。ロシアとアメリカは、シリアを踏み台にしてお互いの手打ちをしました。自らは傷つかないように、シリアのようなかたちで代理的な争いを繰り広げるようになった。イラクの国内が三つに分裂していく現在の構図は、やはりそうした流れの中で捉えなければいけないだろうということです。
そうすると、皮肉なことですが、中東の古いシステムが崩壊するさまは、あたかもソ連が崩壊していった時のプロセスを再現しているかのように見えてならないのです。
●凄絶なユーゴスラビア型をなぞる中東情勢
ソ連の崩壊では、ロシア、ウクライナ、ベラルーシなどの国々が自立化するのと前後して、バルト3国が分離独立しました。中央アジアではカザフスタンやウズベキスタンといった「~スタン」を名乗るイスラム・トルコ系(タジキスタンだけはイラン系)が次々に独立し、カフカース(コーカサス)では最初にアゼルバイジャンが、続いてキリスト教の歴史を背負ってきたアルメニアとグルジアという国々も独立を果たします。このようなプロセスを経て、ソ連は分解し、崩壊していきました。その廃墟の上に、新しい国家が誕生したのです。
そして今、私たちはリビアやイエメンの混迷、シリア・イラクが事実上分解していくプロセスに直面しています。これらを通して見えてくるのは、中東地域における分離・独立運動が、チェコ・スロバキアのような平和なタイプでは収まらず、ユーゴスラビアのような暴力的タイプで進行しているのではないかということです。
チェコとスロバキアは、それぞれが円満に分離することになりました。しかしユーゴスラビアは、セルビア、クロアチアをはじめ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボ、モンテネグロ、マケドニアなどが独立し分離していくために、非常に壮絶な闘いを必要とし、凄絶な内戦を経験しなければなりませんでした。
ユーゴスラビアはいわば中東のモデルです...