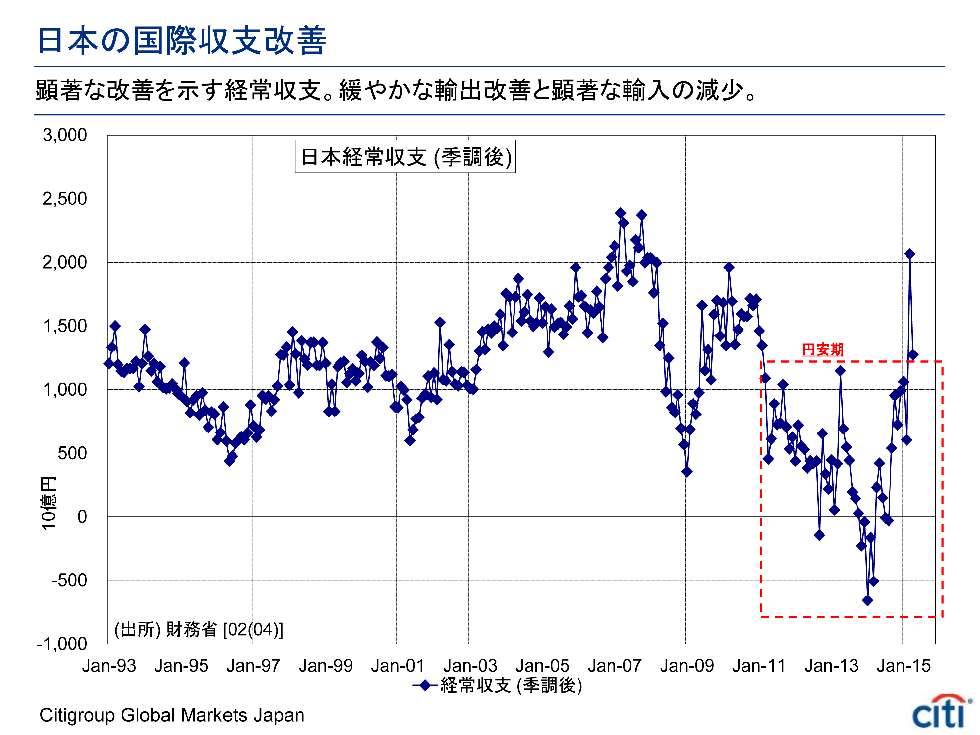●実質実効円相場はかなり円安になっている
本日の二つ目のテーマということになってきますが、では実質的な円安は進んでいるのかどうか、それに関してIMF(国際通貨基金)がどういう考え方を持っているのかを示してみたいと思います。
いま皆さんに見ていただいているグラフは、名目実効円相場と実質実効円相場の動きを示しています。名目実効円相場は、ドル円だけではなく、ユーロ円、韓国ウォン円、人民元円といった、さまざまな日本の貿易相手国通貨に対する全体としての日本円の名目為替レートの指数になってきます。一方、実質実効円相場は、赤い折れ線グラフになりますが、日本と海外のインフレ格差の累積を加味したものになってきます。
約3年前はドル円相場が75円台をつけた時ですが、そこまでドル安、円高が進んだことで、円の名目実効相場は過去最高水準の円高を記録していました。ところが、そこから日本と海外のインフレ格差を加味した実質実効円相場はというと、ドル円相場が75円をつけて、名目実効円相場が過去最高値だったにもかかわらず、おおむね過去の平均水準ほどのところにとどまっていたのです。これは日本がデフレになった分、名目為替レートに対して実質為替レートが円安方向に押し下げられていることを示唆していました。
そこから3年弱、急激な円安が進んだことによって、実質実効円相場は過去平均水準から一段と下がってきて、今は、変動相場制に移行した後、最安値近辺になっています。その意味において、2015年6月10日の黒田総裁が指摘した「実質実効円相場はかなり円安になっている」というのは、事実だということです。
●実質実効円相場の下げは問題ではない
では、アメリカやIMFが、この実質実効円相場が下がっていること自体を問題視しているのかというと、直接的には問題ではないと思っています。
前回、アメリカやIMFがドル高や円安に対して包囲網を狭めてきていることについて申し上げましたが、実は、2012年8月、当時は円安ではなく円高だったのですが、その円高の中で、実質実効円相場は、先ほどお話しした通り、過去の平均水準に近いという議論が行われており、さまざまなマーケット参加者や一部経済学者の間でも、過去の平均水準にすぎない実質実効円相場の状態なので、円高はまだ深刻な状況ではないという意見が結構出ていたので...