テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
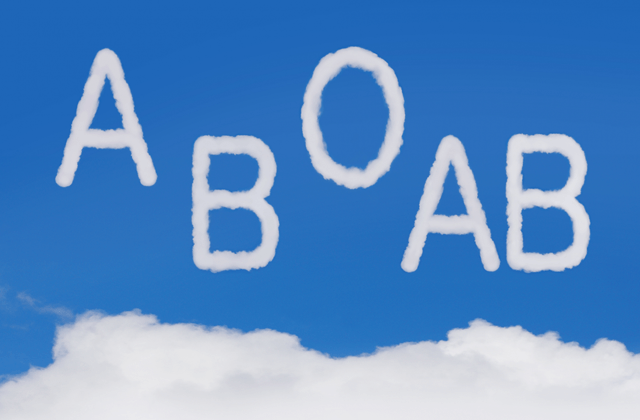
なぜ血液型と性格は関係あると思ってしまうのか?
血液型で人間性が決まるなんて
あなたは「血液型による性格診断」を信じていますか?たとえば「A型だから几帳面」といった感じに。血液型による性格診断は血液型別の本などが発売されて、ブームにもなりましたが、最近では、血液型と性格は根拠なく結びつけられている、という話をよく耳にします。それでは、血液型による性格診断とはいったいどういうことなのか。今回はそんな血液型と性格の謎について調べていきます。関係ない説が濃厚?
2014年、縄田健悟氏の論文「血液型と性格の無関連性―日本と米国の大規模社会調査を用いた実証的論拠―」によると、血液型と性格の関連性がない可能性を示すものとして、松井豊氏によって、1980年代、4回にわたって行われた実験が大きな意味を持つと記されています。そこでは、血液型と性格のあいだには特別な関連性は見られなかったとのことでした。では、そもそも、いつごろから血液型と性格は関係がある、とされたのでしょうか。一説には1927年、教育学者の古川竹二氏が発表した論文『血液型による気質の研究』からだといわれています。古川氏は知識重視の入試方法に疑問を抱き、性格によっても判断されるべきだという考えのもと、血液型の性格分類の研究を始めました。
のちにこの研究がテレビ番組によって広められ、それを見た視聴者が血液型と性格の関係を信じるようになったということです。
海外では信じられないこと
ところで、血液型の話で盛り上がるのは日本だけ、という話をよく耳にしますが、実際のところはどうなのでしょうか。そもそも、海外では自分の血液型を知らないという人が多く、性格との関係も気にしません。日本人が何かと血液型の話を持ち出すのに違和感、不快感を示している人もいるといいます。不快感の一番の原因は、やはり差別的なイメージがあるからでしょう。血液型で性格や人柄を決めつけて、相手に不快な思いをさせる「ブラハラ(ブラッドタイプ・ハラスメント)」は嫌がらせからいじめにまで発展する場合もあります。
謎の「当たっている感」バーナム効果
ただ、「根拠がない」といわれているにもかかわらず、「当たってる」と思うことはありませんか。これは、なぜなのでしょうか。これを心理学の領域では、「バーナム効果」といいます。これはアメリカの心理学者・ポール・ミール氏が提唱したもので、誰にでも当てはまりそうな内容を指摘されたとき、「自分のことかもしれない」と思い込んでしまう心理のことです。「今、迷っていますね」「先が見えませんか」と聞かれると、多くの人が頷くでしょう。それはまさに「自分にも当てはまる」と思い込んでしまっているのです。そのため、「血液型が〇〇だとその人は××」というイメージがあると、自分も「そういうところがある」と当てはめてしまいます。それが「当たっている感」につながっているのです。
それでも話題になるのはなぜなのか
しかし、ここまで「関連性はない」とされながらも、話題にのぼってしまうのはなぜでしょうか。考えられる理由の一つは、人間は「〇〇系」と分類することが好きだ、ということ。もう一つは、「傾向」という「可能性」をどこかで信じているからでしょう。NEWSポストセブンの『「血液型と性格に関係なし」に7万人調べた血液型研究家反論」』という記事では、
“九州大学の講師が、「血液型と性格との関係に科学的根拠はない」との論文を発表。日米1万人を対象に調査を行って執筆されたこの論文は、血液型性格診断が大好きな日本人にショックを与えた。しかし、統計学による血液型の傾向を研究する血液研究家の金澤正由樹さんはこう話す。「これまで、7万人以上の血液型を調べ、統計を取った結果を見ると、やはり血液型と性格は、関係があると思います」”
と書かれています。
また、血液型の話は、話し下手な人が話のきっかけをつかむテクニックとしてもたびたび紹介されており、関係の如何を問わず、ポジティブな面で活かされています。いずれにしても、血液型と性格に関する議論は今後も続いていきそうです。
<参考サイト>
・縄田健悟氏論文:血液型と性格の無関連性―日本と米国の大規模社会調査を用いた実証的論拠―
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy/advpub/0/advpub_85.13016/_pdf
・NEWSポストセブン:「血液型と性格に関係なし」に7万人調べた血液型研究家反論
http://www.news-postseven.com/archives/20141022_281167.html
・縄田健悟氏論文:血液型と性格の無関連性―日本と米国の大規模社会調査を用いた実証的論拠―
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjpsy/advpub/0/advpub_85.13016/_pdf
・NEWSポストセブン:「血液型と性格に関係なし」に7万人調べた血液型研究家反論
http://www.news-postseven.com/archives/20141022_281167.html
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










