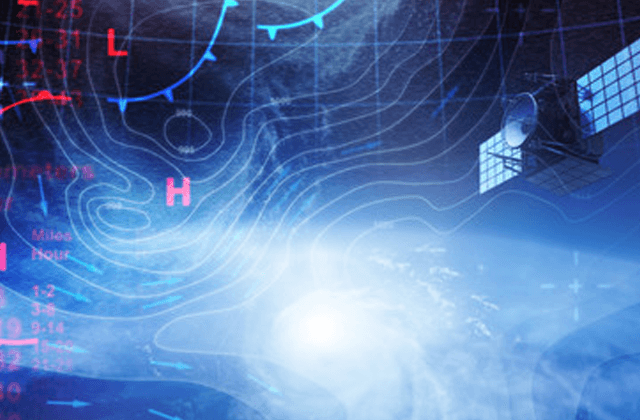
『見えない大気を見る』から考える「異常気象」の意味
今年の夏は「異常気象」が異常に連発していたことをみなさん、ご存知ですか。
「日本列島で観測された異常気象…平均湿度85%、今夏は89年ぶりの高湿度だった!?」という記事を報じた「週プレNEWS」によると、たとえば、7月初旬に九州北部に襲った集中豪雨により、福岡県朝倉市で観測史上最大となる雨量を記録、また、東京でも8月に40年ぶりに連続21日間の雨を観測し、都内で2時間に約1000発の雷が観測された日(8月19日)もありました。その他にも、たくさんの異常気象が報告されています。
地球温暖化問題は、その対策の国際的枠組であるパリ協定からトランプ大統領が脱退を表明したことで最近も話題を呼びました。
注目すべきは、気象予報が政治とも強く結びついているという点です。
地球全体の気温が4度上昇すると言われても、あまりピンとこないかもしれません。そこで具体的な例を挙げると、8月の「野外での運動禁止日数」、すなわち「暑くて熱中症にかかってしまう危険が高いなどの理由で野外では運動しない方がよいとされる一か月の日数」が、東京においては今のところ2日間なのですが、2050年代には15日間に増加すると予測されています。つまり、1か月の半分は外出するのが億劫になるほどの猛暑日となるのです。
ところで、『見えない大気を見る 身近な天気から、未来の気候まで』の著者・日下博幸先生は筑波大学計算科学研究センターの教授で、2002年から2004年までただ一人の日本人として、アメリカ国立大気研究所にて、気象予測のための次世代シミュレーションモデルWRF(ワーフ)の開発プロジェクトに参加。また、2011年には国際都市気候学会(IAUC)の日本人唯一の理事に選出された、いわば日本の気象学者のトップランナーなのです。
こうした華々しい経歴を見ると、本書は、アカデミックで難解な本なのかなと思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。それどころか、実は児童書なのです。なお、児童書ではありますが、大人も意外と知らない風や虹や雲の正体から、AIなどの最新テクノロジーを用いた気象予測の未来まで、大人でも十分にワクワク楽しめる内容になっています。
先述した通り、環境も政治も経済も横断する気象予報の知識は、ビジネスパーソンにとっても目が話せない分野となっているといえるでしょう。もし、これから気象予報について楽しく学びたいという方にとって、本書はとっておきの入門書になることでしょう。
「日本列島で観測された異常気象…平均湿度85%、今夏は89年ぶりの高湿度だった!?」という記事を報じた「週プレNEWS」によると、たとえば、7月初旬に九州北部に襲った集中豪雨により、福岡県朝倉市で観測史上最大となる雨量を記録、また、東京でも8月に40年ぶりに連続21日間の雨を観測し、都内で2時間に約1000発の雷が観測された日(8月19日)もありました。その他にも、たくさんの異常気象が報告されています。
そもそも「異常気象」とは?
ところで、そもそも「異常気象」とはどういったことを指すのでしょうか。『見えない大気を見る 身近な天気から、未来の気候まで』(日下博幸著、くもん出版)によると、異常気象とは「一生の間でまれにしか経験しないような、めったに起こらない天気、気象、天候のこと」。また「気象庁では、三十年に一回発生するかしないかくらいの現象のこと」と定義しているのだそうです。気象予報は、政治とも強く結びついている
「一生の間でまれにしか経験しないような、めったに起こらない」はずなのに、なぜ、これほどまでに異常気象が連発するのか。一概には言い切れませんが、その理由としては、「ヒートアイランド現象」や「地球温暖化」を挙げることができます。地球温暖化問題は、その対策の国際的枠組であるパリ協定からトランプ大統領が脱退を表明したことで最近も話題を呼びました。
注目すべきは、気象予報が政治とも強く結びついているという点です。
50年後、東京の8月の熱中症の危険日だらけ
さて、先述の『見えない大気を見る 身近な天気から、未来の気候まで』では、地球温暖化現象に対して、私たちが取るべき対策を実行できなければ、100年後に地球全体の気温が4度上昇すると伝えています。地球全体の気温が4度上昇すると言われても、あまりピンとこないかもしれません。そこで具体的な例を挙げると、8月の「野外での運動禁止日数」、すなわち「暑くて熱中症にかかってしまう危険が高いなどの理由で野外では運動しない方がよいとされる一か月の日数」が、東京においては今のところ2日間なのですが、2050年代には15日間に増加すると予測されています。つまり、1か月の半分は外出するのが億劫になるほどの猛暑日となるのです。
気象予報がビジネスパーソンの基礎教養に
異常気象と温暖化について述べてきましたが、実は気象予報は環境分野だけのテーマではありません。トランプ大統領と温暖化に関するニュースは政治分野ですし、経済分野においても、AIと結びついた気象予報は成長産業として、いま大きな注目を浴びています。ところで、『見えない大気を見る 身近な天気から、未来の気候まで』の著者・日下博幸先生は筑波大学計算科学研究センターの教授で、2002年から2004年までただ一人の日本人として、アメリカ国立大気研究所にて、気象予測のための次世代シミュレーションモデルWRF(ワーフ)の開発プロジェクトに参加。また、2011年には国際都市気候学会(IAUC)の日本人唯一の理事に選出された、いわば日本の気象学者のトップランナーなのです。
こうした華々しい経歴を見ると、本書は、アカデミックで難解な本なのかなと思われる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。それどころか、実は児童書なのです。なお、児童書ではありますが、大人も意外と知らない風や虹や雲の正体から、AIなどの最新テクノロジーを用いた気象予測の未来まで、大人でも十分にワクワク楽しめる内容になっています。
先述した通り、環境も政治も経済も横断する気象予報の知識は、ビジネスパーソンにとっても目が話せない分野となっているといえるでしょう。もし、これから気象予報について楽しく学びたいという方にとって、本書はとっておきの入門書になることでしょう。
<参考文献・参考サイト>
・『見えない大気を見る 身近な天気から、未来の気候まで』(日下博幸著、くもん出版)
http://kumonshuppan.com/ehon/ehon-syousai/?code=34551
・「週プレNEWS」
http://wpb.shueisha.co.jp/2017/09/04/91192/2/
<関連サイト>
・筑波大学 日下博幸研究室ホームページ
http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~kusakaken/
・『見えない大気を見る 身近な天気から、未来の気候まで』(日下博幸著、くもん出版)
http://kumonshuppan.com/ehon/ehon-syousai/?code=34551
・「週プレNEWS」
http://wpb.shueisha.co.jp/2017/09/04/91192/2/
<関連サイト>
・筑波大学 日下博幸研究室ホームページ
http://www.geoenv.tsukuba.ac.jp/~kusakaken/
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







