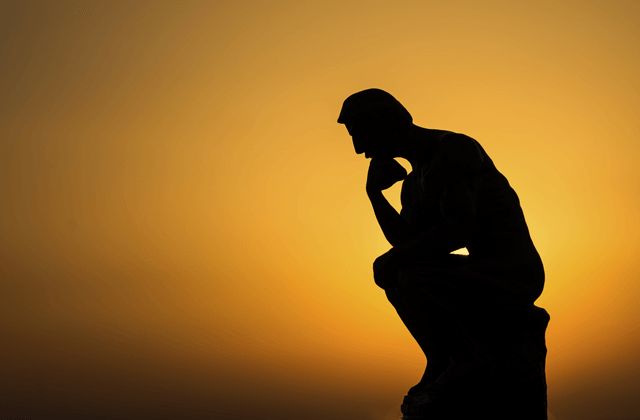
日本人の「労働生産性」が低い理由
経済協力開発機構(OECD)が世界各国の生産性に関するデータをまとめた「生産性指標総覧」というものがあります。今回、この中で注目したいのは「労働生産性」です。2017年5月に発表されたデータによると、先進7か国のG7諸国内で最も高いのはアメリカ、最も低いのは日本。日本の労働生産性はOECD全体の平均も下回っていました。
実は、日本の労働生産性については、以前から効率化の必要性が指摘されてきました。しかし、日本とアメリカを比較しながらデータをよく見ると、日本の労働生産性の低さは効率と別のところに原因があることがわかります。
経済学における生産性の計算式は「アウトプット÷インプット」で、これを労働生産性に当てはめると「付加価値(原材料や燃料から新たに生み出された価値)÷時間」となります。同じ付加価値を保って働く時間を減らせば労働生産性は上がるので、効率がいいということになります。
この観点から日本とアメリカを比較すると、日本の年間労働時間は1990年に2100時間だったものが2015年には1700時間まで減っているのに対し、アメリカはほとんど変わらず1800時間前後のまま。それならば日本の労働生産性は向上してアメリカとの差は縮まっているはずなのに、実際にはG7中最下位です。つまり、労働生産性は働く時間を減らして業務を効率化しただけでは向上しないのです。
日本国内の都道府県別一人当たりの労働生産性を比較すると、2013年のデータになりますが、京都が沖縄県の約1.85倍もあります。しかし、沖縄県の労働者が東京都の労働者より効率の悪い働き方をしているとはいえません。ここまで大きな差が出るのは、生み出された付加価値を回転させる経済構造が存在するか否かにあるのです。
労働者が業務を効率化して何かを生産しても、消費されなければ無駄になるだけで付加価値は生まれません。そして、消費を促す経済構造や市場を整えるのは企業の上層部や国の仕事です。日本はこれから人口が減り、市場はさらに縮小します。これに伴って消費も減少するので、せっかく業務を効率化しても売上は上がらず、消費されないものばかり増えていきます。これでは賃金も上がらないので、労働者のモチベーションは下がるばかり。そうして、市場が縮小し消費が冷え込む中で労働者個人に効率化を求めるのはもはや限界があり、そんな状況のなか「日本人の労働生産性が低い」と表現するのはナンセンスと言わざるを得ません。
最近、日本の若者は将来に希望が持てないとよくいわれますが、こうした空気を敏感に肌で感じているからではないでしょうか。
もちろん日本には、先述したように市場の縮小や人口減少など構造的な問題があります。そのうえでもし日本人がもっと自分の職場に愛着を持てるようになれば、仕事もより楽しくなって労働生産性が向上していく可能性があると考えられないでしょうか。いずれにしても、労働生産性を向上させるという課題をクリアしていくのは簡単なことではないということですね。
日本の労働生産性の低さは効率と別のところに原因がある
このため「日本人のワークスタイルは効率が悪い」という論調の報道が2017年に世間を騒がせるようになり、政府が推進する働き方改革でも労働生産性の向上が大きなテーマとなっているのです。実は、日本の労働生産性については、以前から効率化の必要性が指摘されてきました。しかし、日本とアメリカを比較しながらデータをよく見ると、日本の労働生産性の低さは効率と別のところに原因があることがわかります。
経済学における生産性の計算式は「アウトプット÷インプット」で、これを労働生産性に当てはめると「付加価値(原材料や燃料から新たに生み出された価値)÷時間」となります。同じ付加価値を保って働く時間を減らせば労働生産性は上がるので、効率がいいということになります。
この観点から日本とアメリカを比較すると、日本の年間労働時間は1990年に2100時間だったものが2015年には1700時間まで減っているのに対し、アメリカはほとんど変わらず1800時間前後のまま。それならば日本の労働生産性は向上してアメリカとの差は縮まっているはずなのに、実際にはG7中最下位です。つまり、労働生産性は働く時間を減らして業務を効率化しただけでは向上しないのです。
日本国内の都道府県別一人当たりの労働生産性を比較すると、2013年のデータになりますが、京都が沖縄県の約1.85倍もあります。しかし、沖縄県の労働者が東京都の労働者より効率の悪い働き方をしているとはいえません。ここまで大きな差が出るのは、生み出された付加価値を回転させる経済構造が存在するか否かにあるのです。
労働者が業務を効率化して何かを生産しても、消費されなければ無駄になるだけで付加価値は生まれません。そして、消費を促す経済構造や市場を整えるのは企業の上層部や国の仕事です。日本はこれから人口が減り、市場はさらに縮小します。これに伴って消費も減少するので、せっかく業務を効率化しても売上は上がらず、消費されないものばかり増えていきます。これでは賃金も上がらないので、労働者のモチベーションは下がるばかり。そうして、市場が縮小し消費が冷え込む中で労働者個人に効率化を求めるのはもはや限界があり、そんな状況のなか「日本人の労働生産性が低い」と表現するのはナンセンスと言わざるを得ません。
最近、日本の若者は将来に希望が持てないとよくいわれますが、こうした空気を敏感に肌で感じているからではないでしょうか。
日本人労働者のモチベーションを上げるには
それでは、日本はどう変われば労働生産性が向上するでしょうか。近年、欧米では「社員のエンゲージメント」という概念が重視されています。これは社員の企業に対する愛着であり、企業と社員がお互いに貢献して成長し合う関係のこと。『日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?』(ロッシェル・カップ著)によると、社員のエンゲージメントが高い国は労働生産性も高い傾向にあるのですが、日本は労働生産性同様に社員のエンゲージメントも諸外国より低いということです。もちろん日本には、先述したように市場の縮小や人口減少など構造的な問題があります。そのうえでもし日本人がもっと自分の職場に愛着を持てるようになれば、仕事もより楽しくなって労働生産性が向上していく可能性があると考えられないでしょうか。いずれにしても、労働生産性を向上させるという課題をクリアしていくのは簡単なことではないということですね。
<参考サイト>
・『日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?』(ロッシェル・カップ著、 クロスメディア・パブリッシング)
・OECD:生産性の伸びが継続的に鈍ると、生活水準が下がる
https://www.oecd.org/tokyo/newsroom/continued-slowdown-in-productivity-growth-weighs-down-on-living-standards-japanese-version.htm
・『日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?』(ロッシェル・カップ著、 クロスメディア・パブリッシング)
・OECD:生産性の伸びが継続的に鈍ると、生活水準が下がる
https://www.oecd.org/tokyo/newsroom/continued-slowdown-in-productivity-growth-weighs-down-on-living-standards-japanese-version.htm
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







