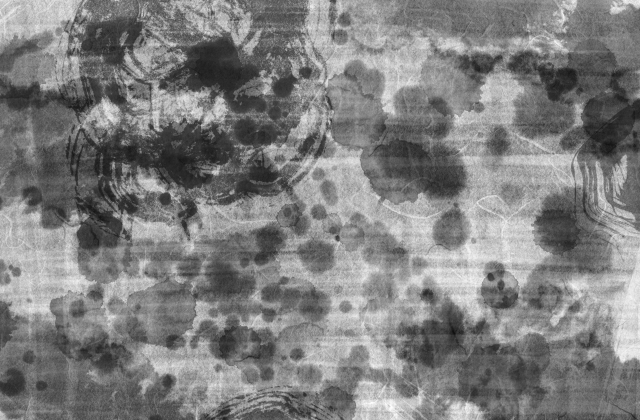
日本画を描くために必要な「写意」と「写生」
小さい頃の思い出の場所を大人になってから訪ねると、大変な大木と思っていた木が実はそれほどでもなかったり、ものすごく急な坂道と思っていたものが、案外ゆるやかだったりという経験を、誰しも持っていることと思います。これは、幼い時にそのものを見た気もちが、映像のなかに投影されているからなのかもしれません。
「写意」とは、実、つまりありのままを写す「写実」に対して、「意を写す」こと。ものの意味や本質に迫り、描き写そうとする手法です。
こう聞くと、幼い頃に木を仰ぎ見て「なんて大きな木だろう」「てっぺんまで登ったらどんなにか遠くまで見渡すことができるだろう」と思い、そのことが実物以上の大樹と記憶させていたというのは、幼いながらこの「写意」を行っていたのではないかと思えてきます。
ですから、同じように対象物をしっかりと捉えていても、写真と写生は本質的に違うものだと川嶋氏は指摘します。写真は「真実を写す」と書くだけあって、ものの形態をそっくり写し取り、持ち帰っていつでも取り出すことができます。そして、全てをありのままに写し取る。ここが少々厄介であって、たとえば美しい花のそばに落ちている空き缶や、すがすがしい風景のなかに映りこむゴミといったものも、克明に記録してしまいます。
元来、人の目というのは見たいものだけにピントを合わせたり、見たくないものはぼかしたり見えなくしてしまったりと、ある意味都合よくできていますから、そうした「意」から生まれたものを写す写生と写真とは大きく異なっているのです。
すると、学生は自ずと真剣にものを見ようとし、その上で描こうとします。時には誤った線、ためらった描き方が出てくるかもしれないけれど、川嶋氏は「そうしたものもしっかりと写生として家に持ち帰りなさい」と教えているそうです。すぐにリセットするのではなく、迷ったり、迷った挙句に出てきたものを持ち帰って、それごと描き出してみる。ここに写意の本質があるからです。
旅行で写真を撮って、後で見返すと「こんな風景だったっけ?」と思ったりしたことはありませんか。スマホやデジカメに保存されているから、と実は肉眼ではよく見ていなかったりするものです。一度、こうしたツールに頼らず自分の目で見ることに徹底してみてはどうでしょう。いわば、心の筆で写生をしてみるのです。細部まで克明に写すことはできなくても、そうして目に焼き付けた景色はどんな写真、画像にも劣らぬ鮮明な印象を胸に刻み込んでくれることでしょう。
日本画の特徴の一つである写意とは
京都市立芸術大学 美術学部日本画研究室教授であり、自身も日本画家である川嶋渉氏によると、このように気もちを写し取ったり自分なりのものの見方や意見を反映させることを絵画の手法として「写意」といい、日本画を含む東洋絵画では非常に大切にされてきたのだそうです。「写意」とは、実、つまりありのままを写す「写実」に対して、「意を写す」こと。ものの意味や本質に迫り、描き写そうとする手法です。
こう聞くと、幼い頃に木を仰ぎ見て「なんて大きな木だろう」「てっぺんまで登ったらどんなにか遠くまで見渡すことができるだろう」と思い、そのことが実物以上の大樹と記憶させていたというのは、幼いながらこの「写意」を行っていたのではないかと思えてきます。
そこに生まれた何かを写し取るのが本来の「写生」
この写意のために必要なこととして、最も重視されるのが「写生」だ、と川嶋氏は言います。小学校の図画の時間等に写生をした経験は皆さんお持ちだと思いますが、「写生」本来の意味は、実はもう少し深いところにあります。すなわち、写生とは現場に出向き、対象物にしっかりと対峙してその姿を写し取るだけでなく、その時に生まれた何かを写し取る。この「生まれた何かを写す」、ここに「写生」の本来があります。ほころび始めた蕾を見て「長い冬も終わって春が近づいているんだな」と喜びを感じる。その時、花の香りを含んだ風を感じて深々と呼吸する。そのようなものまで写し取ろうとするのが本当の写生なのです。ですから、同じように対象物をしっかりと捉えていても、写真と写生は本質的に違うものだと川嶋氏は指摘します。写真は「真実を写す」と書くだけあって、ものの形態をそっくり写し取り、持ち帰っていつでも取り出すことができます。そして、全てをありのままに写し取る。ここが少々厄介であって、たとえば美しい花のそばに落ちている空き缶や、すがすがしい風景のなかに映りこむゴミといったものも、克明に記録してしまいます。
元来、人の目というのは見たいものだけにピントを合わせたり、見たくないものはぼかしたり見えなくしてしまったりと、ある意味都合よくできていますから、そうした「意」から生まれたものを写す写生と写真とは大きく異なっているのです。
本質的なものの見方を養うために「鉛筆禁止」
日本画を描くには、こうした写意、写生が非常に重要であるため、川嶋氏はものを見る時にすぐにスマホに頼ってしまう学生に対して、授業のやり方を変えたそうです。それは半年間は「鉛筆禁止」。その代わりに「筆で描く」ことに徹底するという方法です。鉛筆を使えば、消しゴムですぐに間違った線、気に入らない線を消すことができる。こうした担保を排除して、やり直しの効かない筆で描くことを、学生に教えました。すると、学生は自ずと真剣にものを見ようとし、その上で描こうとします。時には誤った線、ためらった描き方が出てくるかもしれないけれど、川嶋氏は「そうしたものもしっかりと写生として家に持ち帰りなさい」と教えているそうです。すぐにリセットするのではなく、迷ったり、迷った挙句に出てきたものを持ち帰って、それごと描き出してみる。ここに写意の本質があるからです。
旅行で写真を撮って、後で見返すと「こんな風景だったっけ?」と思ったりしたことはありませんか。スマホやデジカメに保存されているから、と実は肉眼ではよく見ていなかったりするものです。一度、こうしたツールに頼らず自分の目で見ることに徹底してみてはどうでしょう。いわば、心の筆で写生をしてみるのです。細部まで克明に写すことはできなくても、そうして目に焼き付けた景色はどんな写真、画像にも劣らぬ鮮明な印象を胸に刻み込んでくれることでしょう。
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







