テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
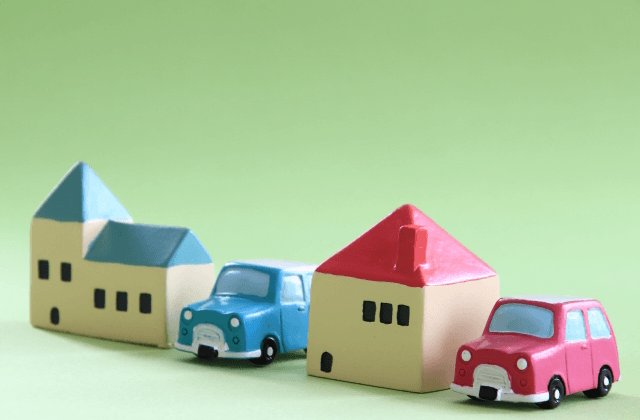
世帯あたりの車の保有台数が最も多い都道府県は?
保有台数が最も多いのは愛知県ですが…
自動車関連の情報提供や統計作成を行う自動車検査登録情報協会(自検協)がまとめた「わが国の自動車保有動向」平成30年版が、2018年10月22日に発表されました。この統計によると、都道府県別の軽自動車を含む自家用乗用車の普及状況で保有台数が最も多いのは愛知県。保有台数のトップ3は以下のようになっています。1位:愛知県(416万4071台)
2位:埼玉県(319万5629台)
3位:東京都(311万4811台)
愛知県は2位の埼玉県を100万台近く上回ってダントツの1位です。さすが、世界の売上高でも常に上位にランクインするトヨタ自動車のお膝元ですね。トヨタ自動車の乗用車は国内で広く愛用されており、同統計のメーカー別保有台数によれば全体の47.39%と、ほぼ半数を占めています。
しかし当然ながら、都道府県別の保有台数は人口が多いところほど多くなりますよね。このため、より個人レベルでの自動車の保有状況を知るには、1世帯当たりの保有台数のほうが参考になります。では、そのトップ5を見てみましょう。
1位:福井県(1.746台)
2位:富山県(1.694台)
3位:山形県(1.677台)
4位:群馬県(1.634台)
5位:栃木県(1.611台)
単純な都道府県別の保有台数とはまったく違うことがわかりますね。東海地方や首都圏は含まれず、北陸地方や北関東が多くなっており、車がないと移動に不便な地域ほど保有率が高いようです。
また、総務省統計局が毎年発表している「明日への統計」の2018年版には、このランキングと関連しそうな興味深い統計が出ています。それは持ち家住宅率。最も高いのは富山県の79.4%で、さらに3位には76.6%で山形県、4位には76.5%で福井県がランクインしています。この結果と照らし合わせてみると、自動車を自宅に駐車しておける環境が整っていることも保有率の高さにつながっているのかもしれません。
逆に世帯あたりが最も少ない都道府県は?
それでは、逆に世帯あたりの保有台数が少ないワースト5はどのようになっているでしょうか。その結果は以下になります。43位:兵庫県(0.915台)
44位:京都府(0.825台)
45位:神奈川県(0.714台)
46位:大阪府(0.648台)
47位:東京都(0.439台)
大都市を擁する都道府県が軒並みランクインしていることがわかります。中でも東京都は0.5台にも満たずダントツのワースト1位。2世帯に1台もない計算になります。しかし都内は鉄道網が発達しており、運行本数もとても多くなっていますよね。さらにタクシーは呼び出しをしなくても、道路の横で少し待てばすぐつかまえられます。移動手段が充実しているので、自動車がなくても特に不便を感じない人が多いのでしょう。
実は、「明日への統計」2018年版の持ち家住宅率ワースト1位も東京都で、なんと45.8%。地価が高く土地が狭いこともあって駐車場の確保が難しいため、自動車を持つとむしろ面倒が増えてしまうパターンも珍しくありません。自動車が生活に欠かせない地域もあれば、逆に邪魔になってしまう地域もあるのですね。
一人あたりの保有台数はまた違った結果に
世帯あたりの自動車保有台数ランキングを見てきましたが、この統計では一人あたりの保有台数も発表されています。そのトップ5は以下のようなもの。1位:群馬県(0.691台)
2位:栃木県(0.671台)
3位:茨城県(0.667台)
4位:富山県(0.663台)
5位:山梨県(0.660台)
世帯あたりの保有台数とはかなり違う結果になっています。この理由は、北陸地方よりも北関東に単身世帯が多いからと考えられます。たとえば、世帯あたりの統計なら4人世帯でも単身世帯でも1台保有していたら1台とカウントされます。しかし、一人あたりの統計では単身世帯が1台保有していたら1台ですが、4人世帯が1台保有していたら0.25台というカウントになりますよね。つまり、最も多くの人が自動車を愛用している都道府県は群馬県といえるでしょう。
このように上位は結果に違いが出た一人あたりの保有台数ですが、ワースト5位は世帯あたりのランキングとまったく同じ結果に。最下位・東京都の保有台数はわずか0.228台でした。こんなにも世帯や個人の保有台数が少ないのに、都道府県別の保有台数では3位に入っている東京都には驚きですね。いかに東京都に人口が集中しているかもわかる統計になっているのではないでしょうか。
<参考サイト>
・自動車検査登録情報協会 わが国の自動車保有動向
https://www.airia.or.jp/publish/statistics/trend.html
・自動車検査登録情報協会 都道府県別の自家用乗用車の普及状況
https://www.airia.or.jp/publish/file/r5c6pv000000m224-att/r5c6pv000000m22j.pdf
・総務省統計局 今年度実施予定の主要統計調査
https://www.stat.go.jp/info/guide/asu/2018/pdf/2018asu_1.pdf
・統計メモ帳 単独世帯割合
https://ecitizen.jp/ssds/Indicators/_A06205
・くるまえらびドットコム えっ、その県?!自家用車保有率がトップな県って?
https://www.kurumaerabi.com/car_mag/list/20/
・自動車検査登録情報協会 わが国の自動車保有動向
https://www.airia.or.jp/publish/statistics/trend.html
・自動車検査登録情報協会 都道府県別の自家用乗用車の普及状況
https://www.airia.or.jp/publish/file/r5c6pv000000m224-att/r5c6pv000000m22j.pdf
・総務省統計局 今年度実施予定の主要統計調査
https://www.stat.go.jp/info/guide/asu/2018/pdf/2018asu_1.pdf
・統計メモ帳 単独世帯割合
https://ecitizen.jp/ssds/Indicators/_A06205
・くるまえらびドットコム えっ、その県?!自家用車保有率がトップな県って?
https://www.kurumaerabi.com/car_mag/list/20/
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子










