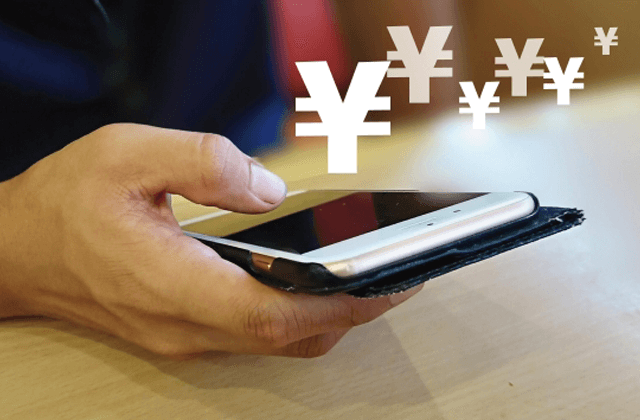
ネットで横行する「転売行為」の実情
インターネットだけでなくパソコンやスマートフォンの普及といったハード面の充実、さらにはECサイトだけでなくオークションサイトやフリマアプリの活況のようなソフト面の拡充によって、商取引、つまりは売買行為のスタイルや方法は、ここ数十年の間に加速度的に多様な進化を遂げてきました。
少し前なら組織的に行う必要があった取引であっても個人や少人数でも比較的に簡単に行えるようになったため、特に増加し、ある側面においては横行しているとさえいえる「転売行為」の実情、今回は取り上げてみたいと思います。
1)自分で使ったり所有したりことを目的とした購入ではなく、付加価値が上がりそうな商品を仕入れて価格を上乗せして高く売るといった、利益を上げることを目的に「転売目的で購入した商品によって常習的に転売を行う」場合
2)本来は自分で使ったり使用したりすることを目的とした商品購入ではあるが、例えば抽選制のチケット販売での良席確保やブラインド仕様のグッズの中から目当てのグッズが出るまでの「大量購入のため発生した不要物を転売する」場合
3)自分で使ったり所有したりすることを目的としてチケットやグッズを購入したものの都合がつかなくなったり不要となったりしてしまったため、「(本来なら自分のために購入した商品を)気持ちや状況的にやむを得ず無料や適正価格で譲る(転売する)」場合
そして、1)と2)のようなことを行う人こそが、いわゆる「転売ヤー」と呼ばれている人に該当し、社会問題となっています。
1)「転売行為」自体が経済行為の根幹である自由競争が行われた結果であるとはいい難く、そもそも不正取引ともいえる。政府が放置することによって被害が広がると、法治国家の根本を揺るがしかねない危険性すらある。
2)「転売行為」によって健全な商取引が行われないことは、社会不安を引き起こすことにもつながりやすい。そして社会不安が蔓延してしまうと、公共の福祉の侵害など深刻な事態にもつながりかねない。
3)「転売行為」により価格が高騰して適正価格が崩壊したり生活必需品ですら安定した購入ができなかったりすると、消費者が著しい不利益を被る。
4)「転売行為」の弊害による経済損失だけでなく、防止策を行うことにより、販売者側に費用的にも技術的にも余計な負担や困難が生じる。
5)「転売行為」対策に使われたコストは、最終的には価格転嫁されたり税金で補填されることになったりする可能性が高く、結局は消費者かつ納税者でもある市井の人々の負担となる。さらに製造企業や販売企業が廃業となるなど、社会的な損失となったりする場合もある。
1)法律や条例での適切な規制
自由な市場が保持されることは資本主義の根幹でもありますが、同時に“真に”自由な市場を護ることは民主主義の根幹でもあります。「転売行為」が犯罪的かつ公共の利益を損なう行為である以上、適切な規制は必要ですし、今後ますます高度化・複雑化されると予想される「転売行為」対策には、政府や自治体が主導となり、法律や条例で適切に規制をすることもさらに重要になってくると思われます。
例えば、新型コロナによる緊急事態宣言時には、1973年に制定された国民生活安定緊急措置法(第一次オイルショックによる急激な物価上昇と、それによって生じたトイレットペーパー騒動などの社会不安を受けて制定)に基づき、マスクの「転売行為」が禁止されました。
また、2019年6月14日から施行された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称:チケット不正転売禁止法)など、法的な対策も増えてきています。
2)販売者側の企業努力
政府が適正な商取引となるよう公正な立場で市場を見守る責務があると同様に、企業にも安定的かつ敵席価格で商品を供給する責務または努力義務があります(なお、便宜上“企業”としていますが、販売者である以上、個人であっても本質的には責務や努力義務は同様です)。
例えば、技術やコスト面で可能である商品は、安易に限定品とせず供給量を増やす(例:プレミアがつきそうなフィギュアなどのグッズを、あえて限定商品としなかったり完全予約製造としたりする)。
需要が供給量を著しく上回る商品は、公正性を担保して抽選販売とする(例:人気のゲーム機やゲームソフト、ライブやイベントのチケットなどは、先着とせずに予約期間をもうけて抽選販売とする)。
正しく適切な情報を都度発信し、消費者の不安の解消に努める(例:トイレットペーパー不足の情報が出た際に、ウェブやSNSなどを活用して在庫が十分にあることを迅速に広報する)、などがあります。
3)消費者の意識向上
しかしながらもっとも根本的かつ汎用的なことは、消費者の立場に立った際の市井の人々一人ひとりが経済に関する正しい知識を持つことです。
例えば、安易に「転売行為」に加担することによって、組織的な犯罪集団と接点を持つ危険性もあります。また、たとえそのときは「転売行為」の恩恵を受けたと感じたとしても、循環が本質の経済行為である以上、大きな意味での損失を被ることにもなりかねません。
不正行為をする人々への対策は、残念ながらいたちごっこの性質をもっています。しかしながら、対策をしなければ、被害は広がり不利益は止まりません。社会状況に応じて変わっていく情報を適切に更新することによって、一人ひとりが消費者としての意識を向上させ、社会全体で「転売行為」を対策することが、今こそ求められています。
少し前なら組織的に行う必要があった取引であっても個人や少人数でも比較的に簡単に行えるようになったため、特に増加し、ある側面においては横行しているとさえいえる「転売行為」の実情、今回は取り上げてみたいと思います。
「転売行為」の実態
まずは「転売行為」の実態をみていきましょう。「転売行為」の実態は、以下のように大別することができます。1)自分で使ったり所有したりことを目的とした購入ではなく、付加価値が上がりそうな商品を仕入れて価格を上乗せして高く売るといった、利益を上げることを目的に「転売目的で購入した商品によって常習的に転売を行う」場合
2)本来は自分で使ったり使用したりすることを目的とした商品購入ではあるが、例えば抽選制のチケット販売での良席確保やブラインド仕様のグッズの中から目当てのグッズが出るまでの「大量購入のため発生した不要物を転売する」場合
3)自分で使ったり所有したりすることを目的としてチケットやグッズを購入したものの都合がつかなくなったり不要となったりしてしまったため、「(本来なら自分のために購入した商品を)気持ちや状況的にやむを得ず無料や適正価格で譲る(転売する)」場合
そして、1)と2)のようなことを行う人こそが、いわゆる「転売ヤー」と呼ばれている人に該当し、社会問題となっています。
「転売行為」の弊害
次に「転売行為」によって引き起こされえる弊害をみていきましょう。「転売行為」の弊害は、以下のように大別することができます。1)「転売行為」自体が経済行為の根幹である自由競争が行われた結果であるとはいい難く、そもそも不正取引ともいえる。政府が放置することによって被害が広がると、法治国家の根本を揺るがしかねない危険性すらある。
2)「転売行為」によって健全な商取引が行われないことは、社会不安を引き起こすことにもつながりやすい。そして社会不安が蔓延してしまうと、公共の福祉の侵害など深刻な事態にもつながりかねない。
3)「転売行為」により価格が高騰して適正価格が崩壊したり生活必需品ですら安定した購入ができなかったりすると、消費者が著しい不利益を被る。
4)「転売行為」の弊害による経済損失だけでなく、防止策を行うことにより、販売者側に費用的にも技術的にも余計な負担や困難が生じる。
5)「転売行為」対策に使われたコストは、最終的には価格転嫁されたり税金で補填されることになったりする可能性が高く、結局は消費者かつ納税者でもある市井の人々の負担となる。さらに製造企業や販売企業が廃業となるなど、社会的な損失となったりする場合もある。
「転売行為」の対策
以上、「転売行為」の実態と弊害をみてきました。では、「転売行為」には対策はないのでしょうか?結論から述べると、簡単なことではありませんが、「転売行為」の対策はあります。以下の3つの視点から考えてみましょう。1)法律や条例での適切な規制
自由な市場が保持されることは資本主義の根幹でもありますが、同時に“真に”自由な市場を護ることは民主主義の根幹でもあります。「転売行為」が犯罪的かつ公共の利益を損なう行為である以上、適切な規制は必要ですし、今後ますます高度化・複雑化されると予想される「転売行為」対策には、政府や自治体が主導となり、法律や条例で適切に規制をすることもさらに重要になってくると思われます。
例えば、新型コロナによる緊急事態宣言時には、1973年に制定された国民生活安定緊急措置法(第一次オイルショックによる急激な物価上昇と、それによって生じたトイレットペーパー騒動などの社会不安を受けて制定)に基づき、マスクの「転売行為」が禁止されました。
また、2019年6月14日から施行された「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称:チケット不正転売禁止法)など、法的な対策も増えてきています。
2)販売者側の企業努力
政府が適正な商取引となるよう公正な立場で市場を見守る責務があると同様に、企業にも安定的かつ敵席価格で商品を供給する責務または努力義務があります(なお、便宜上“企業”としていますが、販売者である以上、個人であっても本質的には責務や努力義務は同様です)。
例えば、技術やコスト面で可能である商品は、安易に限定品とせず供給量を増やす(例:プレミアがつきそうなフィギュアなどのグッズを、あえて限定商品としなかったり完全予約製造としたりする)。
需要が供給量を著しく上回る商品は、公正性を担保して抽選販売とする(例:人気のゲーム機やゲームソフト、ライブやイベントのチケットなどは、先着とせずに予約期間をもうけて抽選販売とする)。
正しく適切な情報を都度発信し、消費者の不安の解消に努める(例:トイレットペーパー不足の情報が出た際に、ウェブやSNSなどを活用して在庫が十分にあることを迅速に広報する)、などがあります。
3)消費者の意識向上
しかしながらもっとも根本的かつ汎用的なことは、消費者の立場に立った際の市井の人々一人ひとりが経済に関する正しい知識を持つことです。
例えば、安易に「転売行為」に加担することによって、組織的な犯罪集団と接点を持つ危険性もあります。また、たとえそのときは「転売行為」の恩恵を受けたと感じたとしても、循環が本質の経済行為である以上、大きな意味での損失を被ることにもなりかねません。
不正行為をする人々への対策は、残念ながらいたちごっこの性質をもっています。しかしながら、対策をしなければ、被害は広がり不利益は止まりません。社会状況に応じて変わっていく情報を適切に更新することによって、一人ひとりが消費者としての意識を向上させ、社会全体で「転売行為」を対策することが、今こそ求められています。
<参考文献・参考サイト>
・『チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A』(山下貴司・宮内秀樹・三谷英弘著、第一法規)
・「ビジネスに関わる行政法的事案」第26回:「転売屋からは買わない」というのは正しいのか?
http://gbli.or.jp/kohyama_gyosei-26/
・チケット不正転売禁止法 | 文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html
・『チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A』(山下貴司・宮内秀樹・三谷英弘著、第一法規)
・「ビジネスに関わる行政法的事案」第26回:「転売屋からは買わない」というのは正しいのか?
http://gbli.or.jp/kohyama_gyosei-26/
・チケット不正転売禁止法 | 文化庁
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







