テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
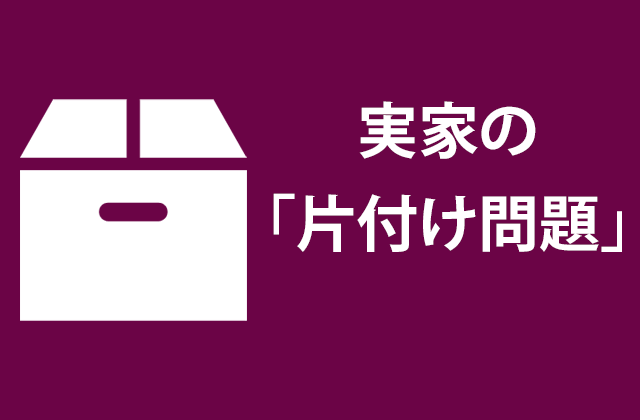
実家の片付け問題…どうやって解決する?
「いつまでも あると思うな 親と金」……昔の人はシビアな言い回しをしたものです。けれども、親が亡くなったとしても身の回りのものが一緒に荼毘にふされるわけではありません。日用品、家具や本、趣味のコレクションや旅行のお土産など、「物」は誰かが処分しなければならないのです。
しかし、両親の世代は「もったいない精神」を強く持っていることも多く、「断捨離しようよ!」と生前整理を呼びかけても反発されてしまうという話もよく耳にします。一筋縄では行きそうにない実家の片付け問題、どのようにしたらうまく進められるのでしょうか。
そんな生前整理にはいくつものメリットがあります。
まず第1に、住んでいる者の日常生活の安全性を高めることができます。加齢により足腰が衰えちょっとした躓きや段差で転倒し、寝たきりになってしまうケースが多いのはよく知られている通りです。足元や周辺を片付けるだけでも事故の予防になるのは間違いありません。必要な物がどこにあるかも把握し易くなりますし、大切なものを保管しておく場所も決めることができます。
何かアクシデントがあったとしても、整理整頓がなされていればすぐ対応ができます。物があふれたままでは工事業者や介護ヘルパーの方に来てもらいたくても作業スペースがないなんてことも出てしまうでしょう。万が一地震や火事が発生したときの避難も危険です。
また、実際問題として、葬儀の後しばらくは相続や手続きなどやらねばならないことが山積の中、片付けはかなり負担になります。今住んでいる親の安全と健康ためにも、後々実家を整理する子供らの負担を軽減するためにも、時間と体力のあるうちになるべく早く始めるのがおすすめです。
イソップの『北風と太陽』ではありませんが、いきなり「片付けて!」と言うのではなく、両親とコミュニケーションをとることから始め、《家の中で困っていること》を聞き出してみましょう。そこからお互いに同じ問題を共有し解決していく流れを作ると片付けの糸口になっていきます。
まだ実家に自分の物がある方はそこから片付けることもできます。子供が自分の部屋を片付け始めると親もつられて身の回りの整頓を始めるケースもよく聞かれます。
それをきっかけに、台所やトイレ、お風呂など、日常的に必ず使う場所から片付けるのが良いでしょう。《片付け》と考えているとどうしても綺麗な部屋を目指してしまいがちですが、実家の片付けに優先されるのは《安全性》です。「綺麗な部屋」よりも「安全な部屋」を目指していきましょう。遠方に住んでいてなかなか片付けに行けない方は行政サービスやプロの業者を頼むことも選択肢に加えておくと良いでしょう。
また、「捨てる」という言葉に拒否反応を示されることも多いので「引き取りたい」「ゆずって」と話すとスムーズに進めやすくなります。持ち帰ったうえで処分するのも方便でしょう。
2019年、WHOはためこみ症を精神疾患のひとつとして認定しました。主な症状は3つ、「自宅にスペースがあろうとなかろうと物を増やしてしまう」「捨てることができず保管し続けてしまう」「整理、片付けができない」と、あげられています。これは尋常ではないと思うところがあれば、行政や医療機関に相談することをおすすめします。
生前整理はどうしても長丁場になります。実家で暮らす両親の安全と健康、先々のことのためにも小さなことからコツコツと進めていくことが肝要です。
しかし、両親の世代は「もったいない精神」を強く持っていることも多く、「断捨離しようよ!」と生前整理を呼びかけても反発されてしまうという話もよく耳にします。一筋縄では行きそうにない実家の片付け問題、どのようにしたらうまく進められるのでしょうか。
生前整理で得られるメリットとは
1つの家にはどれくらいの「物」がたまっているのでしょうか? スタッフが祖父の家を片付けた時は、5人家族が半世紀暮らした家から出たゴミ袋は40リットル入りで300袋はくだりませんでした。処分には数年かかりましたが、コツコツと片付けていたおかげで祖父の他界後、土地の売却が突然決まった時もスムーズに引き渡しができました。そんな生前整理にはいくつものメリットがあります。
まず第1に、住んでいる者の日常生活の安全性を高めることができます。加齢により足腰が衰えちょっとした躓きや段差で転倒し、寝たきりになってしまうケースが多いのはよく知られている通りです。足元や周辺を片付けるだけでも事故の予防になるのは間違いありません。必要な物がどこにあるかも把握し易くなりますし、大切なものを保管しておく場所も決めることができます。
何かアクシデントがあったとしても、整理整頓がなされていればすぐ対応ができます。物があふれたままでは工事業者や介護ヘルパーの方に来てもらいたくても作業スペースがないなんてことも出てしまうでしょう。万が一地震や火事が発生したときの避難も危険です。
また、実際問題として、葬儀の後しばらくは相続や手続きなどやらねばならないことが山積の中、片付けはかなり負担になります。今住んでいる親の安全と健康ためにも、後々実家を整理する子供らの負担を軽減するためにも、時間と体力のあるうちになるべく早く始めるのがおすすめです。
始められない生前整理を始めるために
とはいえ、生前整理を始めたくても当人たちがしたがらない、拒否するという話はよく耳にします。歳をとると気力体力共に減退して変化を嫌う傾向がどうしても出てきがちです。どう切り出すのが良いでしょうか?イソップの『北風と太陽』ではありませんが、いきなり「片付けて!」と言うのではなく、両親とコミュニケーションをとることから始め、《家の中で困っていること》を聞き出してみましょう。そこからお互いに同じ問題を共有し解決していく流れを作ると片付けの糸口になっていきます。
まだ実家に自分の物がある方はそこから片付けることもできます。子供が自分の部屋を片付け始めると親もつられて身の回りの整頓を始めるケースもよく聞かれます。
それをきっかけに、台所やトイレ、お風呂など、日常的に必ず使う場所から片付けるのが良いでしょう。《片付け》と考えているとどうしても綺麗な部屋を目指してしまいがちですが、実家の片付けに優先されるのは《安全性》です。「綺麗な部屋」よりも「安全な部屋」を目指していきましょう。遠方に住んでいてなかなか片付けに行けない方は行政サービスやプロの業者を頼むことも選択肢に加えておくと良いでしょう。
捨てる、捨てないは両親の意思を尊重して慎重に
物を捨てる・捨てないの選別は実家で暮らしている当人を主体に進めていきましょう。思うようにいかなくても勝手に処分するのはNG、信頼関係が壊れてしまうと進む話も進まなくなります。もったいないから寄付をしようと提案したところ、頑なだった両親が承知したというケースもあるそうです。「無駄にしない」と納得してもらうのもポイントです。また、「捨てる」という言葉に拒否反応を示されることも多いので「引き取りたい」「ゆずって」と話すとスムーズに進めやすくなります。持ち帰ったうえで処分するのも方便でしょう。
捨てられないのは「ためこみ症」かもしれない
極端に物が捨てられない、それどころか外からどんどん物を集めてきていわゆるゴミ屋敷になりかけている場合は「ためこみ症」の可能性があると考えられます。2019年、WHOはためこみ症を精神疾患のひとつとして認定しました。主な症状は3つ、「自宅にスペースがあろうとなかろうと物を増やしてしまう」「捨てることができず保管し続けてしまう」「整理、片付けができない」と、あげられています。これは尋常ではないと思うところがあれば、行政や医療機関に相談することをおすすめします。
生前整理はどうしても長丁場になります。実家で暮らす両親の安全と健康、先々のことのためにも小さなことからコツコツと進めていくことが肝要です。
<参考サイト・参考文献>
・『実家の片付けのコツは!?「捨てる」から始めないこと!!』OPT LIFE
https://optlife.co.jp/jikka_katazuke/
・『実家の片づけに2年要した40代女性が得た教訓』東洋経済ONLINE
https://toyokeizai.net/articles/-/320656
・『片付けられない実家の父や母 ためこみ症が急増?』週刊朝日2020.9.18
・『実家の片付けのコツは!?「捨てる」から始めないこと!!』OPT LIFE
https://optlife.co.jp/jikka_katazuke/
・『実家の片づけに2年要した40代女性が得た教訓』東洋経済ONLINE
https://toyokeizai.net/articles/-/320656
・『片付けられない実家の父や母 ためこみ症が急増?』週刊朝日2020.9.18
人気の講義ランキングTOP20










