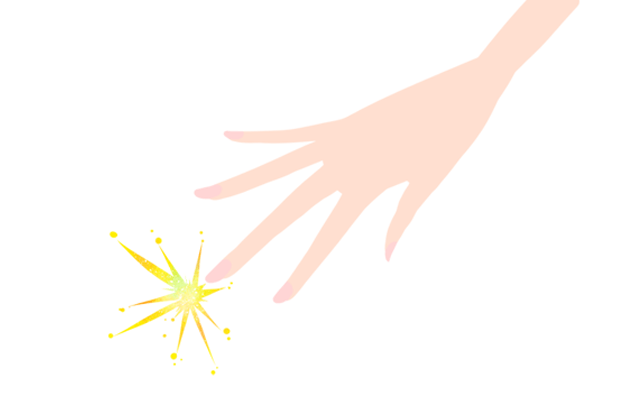
不快な「静電気」の対処法
寒くなり、乾燥する季節になると、気になり始めるのが静電気。ドアノブなどに触るときに「バチッ」とくる、あの不快な感じと刺すような痛み……すごく嫌ですよね。筆者を含め、悩んでいる人は相当多いはずです。
静電気はなぜ起こるのでしょうか。少しでも軽減する方法はないのでしょうか。にっくき静電気のバチバチについて、調べてみました。
私たち人間ふくめ、動物、金属、プラスチック、繊維……などなど、この地球上に存在するすべての物体には、プラスとマイナス2種類の電気を持っています。
普段はこの2種類が偏ることなく、同じ数ずつ存在してバランスを保っています。つまりプラスでもマイナスでもない状態=電気を帯びていない状態です。そのような状態の物体に触れても、電気が発生することはありません。
ところが物体同士が「ぶつかる」「こすれあう」といった刺激があると、“マイナス電気が片方から片方へと移動する”現象が発生します。いっぽうはマイナス過多に、いっぽうはプラス過多にとなり、双方アンバランスな状態になるのです。
この“アンバランスな状態”が「静電気」です。マイナス過多のほうは「マイナスの静電気を帯びた状態」で、プラス過多のほうは「プラスの静電気を帯びた状態」です。これを帯電といいます。
静電気を帯びた物体はプラスマイナス同数の、安定したバランスを取り戻そうとします。そこで「マイナスに帯電した物体」と「プラスに帯電した物体」が近づいたり接触したりすると、その瞬間「マイナスの電気がプラスに帯電した物体のほうへ流れる」現象が起こります。これが一般に言う“静電気で「バチッ」とくる現象(放電)”です。電流そのものは少ないのですが、電圧は強いため「バチッ」と感じるのです。
「バチッ」と感じるものが静電気、と考えられやすいですが、正確には「バチッ」と感じる=“静電気によって起きた放電”が正しい解釈となります。
なお、なぜ「静」という字が使われているかというと、そもそも電気には「静電気」「動電気」があり、一定の場所に静かにとどまっている電気(電荷)が静電気で、移動があるのが動電気という違いがあります。コンセントから流れてくるのが動電気です。一般に「電気」といえば動電気のことを指します。
ふだん体の中で発生した静電気は、肌の水分と空気中の水分を通して素早く、自然と放電されていきます。しかし空気も肌も乾燥しやすい冬場(およそ湿度20%以下、気温20℃以下)は静電気が放出されにくいため、体の中の電気バランスが大きく崩れやすくなっています。
こうした状態の自分の体と、触れた先の物体のプラスマイナスの電気量に差があればあるほど急激に電流が流れ、「バチッ」と痛みを感じやすくなるのです。
・鍵など、先端がとがった金属で対象物に触れる
・綿のハンカチや手袋で対象物に触れる
・コンクリートや土、木製のもの(壁や家具、庭の木など)に触れてから対象物に触れる
・革靴を履く
鍵で開錠してからドアノブに触れると静電気が起こらない……なんてことがあります。これは「先端放電」という現象で、鍵の先端から静電気の一部が放電されたことによるものです。
また、コンクリートや土、木は電気をゆっくり通すので「バチッ」とならず、放電してくれます。
そのためドアノブに触れる時は鍵の先端で触れるか、電気をゆっくり通す素材に触れてからさわると「バチッ」を未然に防ぐことができます。逆にプラスチックやガラス、ゴム類は電気を通さないので、静電気対策には適しません。
また、革製品は体にたまった静電気を逃がしやすい性質があります。足元から地面に逃がすために、革靴を履くのも有効な静電気対策のひとつです。
実は物体ごとに「プラスの電気を帯びやすい」もの、反対に「マイナスの電気を帯びやすい」ものがあります。またプラスにもマイナスにもなりにくい、中間の物体もあります。
衣類の繊維の場合、ウール、ナイロン、レーヨンがプラスに帯電しやすく、ポリエステルやアクリルがマイナスに帯電しやすい素材です。そして麻、木綿、シルクといった天然繊維が、その中間の素材となります。
そのため「パチパチ」やまとわりつきをできるだけ抑えたいなら、同じタイプの素材同士、または中間の素材の衣服を身につけると効果的です。
以上、静電気の性質や、その発生を抑える方法について解説しました。ちなみに、筆者は「ドアノブに触る前に壁を触る」ことを実践し始めてから「バチッ」が明らかに減りました。皆さんも、ここに挙げた対策を実践して、不快な静電気に負けない冬をお過ごし下さいね。
静電気はなぜ起こるのでしょうか。少しでも軽減する方法はないのでしょうか。にっくき静電気のバチバチについて、調べてみました。
そもそも静電気って何? なぜバチッとするの?
対処法を知るために、まずは静電気が起こる仕組みを知っておきましょう(ちょっと専門的な話になりますが、できるだけ分かりやすく書くのでついてきてくださいね)。私たち人間ふくめ、動物、金属、プラスチック、繊維……などなど、この地球上に存在するすべての物体には、プラスとマイナス2種類の電気を持っています。
普段はこの2種類が偏ることなく、同じ数ずつ存在してバランスを保っています。つまりプラスでもマイナスでもない状態=電気を帯びていない状態です。そのような状態の物体に触れても、電気が発生することはありません。
ところが物体同士が「ぶつかる」「こすれあう」といった刺激があると、“マイナス電気が片方から片方へと移動する”現象が発生します。いっぽうはマイナス過多に、いっぽうはプラス過多にとなり、双方アンバランスな状態になるのです。
この“アンバランスな状態”が「静電気」です。マイナス過多のほうは「マイナスの静電気を帯びた状態」で、プラス過多のほうは「プラスの静電気を帯びた状態」です。これを帯電といいます。
静電気を帯びた物体はプラスマイナス同数の、安定したバランスを取り戻そうとします。そこで「マイナスに帯電した物体」と「プラスに帯電した物体」が近づいたり接触したりすると、その瞬間「マイナスの電気がプラスに帯電した物体のほうへ流れる」現象が起こります。これが一般に言う“静電気で「バチッ」とくる現象(放電)”です。電流そのものは少ないのですが、電圧は強いため「バチッ」と感じるのです。
「バチッ」と感じるものが静電気、と考えられやすいですが、正確には「バチッ」と感じる=“静電気によって起きた放電”が正しい解釈となります。
なお、なぜ「静」という字が使われているかというと、そもそも電気には「静電気」「動電気」があり、一定の場所に静かにとどまっている電気(電荷)が静電気で、移動があるのが動電気という違いがあります。コンセントから流れてくるのが動電気です。一般に「電気」といえば動電気のことを指します。
なぜ乾燥の時期に起こりやすい?
物どうしがぶつかることで静電気は発生しますので、静電気そのものは年がら年中発生しています。ではなぜ冬など乾燥した時期に「バチッ」となりやすいのでしょうか。そのポイントが、私たちの体と空気中の水分量です。ふだん体の中で発生した静電気は、肌の水分と空気中の水分を通して素早く、自然と放電されていきます。しかし空気も肌も乾燥しやすい冬場(およそ湿度20%以下、気温20℃以下)は静電気が放出されにくいため、体の中の電気バランスが大きく崩れやすくなっています。
こうした状態の自分の体と、触れた先の物体のプラスマイナスの電気量に差があればあるほど急激に電流が流れ、「バチッ」と痛みを感じやすくなるのです。
静電気対策その1「静電気を逃がしてから触れる」
静電気の放電で一番気になるのが、電気を通しやすい金属に触れる時でしょう。日常生活では、ドアノブや電化製品など、金属に触れる場面が多々ありますよね。そんな時は、以下を試してみてください。・鍵など、先端がとがった金属で対象物に触れる
・綿のハンカチや手袋で対象物に触れる
・コンクリートや土、木製のもの(壁や家具、庭の木など)に触れてから対象物に触れる
・革靴を履く
鍵で開錠してからドアノブに触れると静電気が起こらない……なんてことがあります。これは「先端放電」という現象で、鍵の先端から静電気の一部が放電されたことによるものです。
また、コンクリートや土、木は電気をゆっくり通すので「バチッ」とならず、放電してくれます。
そのためドアノブに触れる時は鍵の先端で触れるか、電気をゆっくり通す素材に触れてからさわると「バチッ」を未然に防ぐことができます。逆にプラスチックやガラス、ゴム類は電気を通さないので、静電気対策には適しません。
また、革製品は体にたまった静電気を逃がしやすい性質があります。足元から地面に逃がすために、革靴を履くのも有効な静電気対策のひとつです。
静電気対策その2「同じ素材同士の衣類を着用する」
よく衣類を着脱する際、「パチパチ」と静電気が放電していたり、まとわりついたりしますよね。あれは衣類の繊維が着脱の際にこすれあうことで静電気が発生しているのです。実は物体ごとに「プラスの電気を帯びやすい」もの、反対に「マイナスの電気を帯びやすい」ものがあります。またプラスにもマイナスにもなりにくい、中間の物体もあります。
衣類の繊維の場合、ウール、ナイロン、レーヨンがプラスに帯電しやすく、ポリエステルやアクリルがマイナスに帯電しやすい素材です。そして麻、木綿、シルクといった天然繊維が、その中間の素材となります。
そのため「パチパチ」やまとわりつきをできるだけ抑えたいなら、同じタイプの素材同士、または中間の素材の衣服を身につけると効果的です。
静電気対策その3「肌の保湿、部屋の加湿」
上記でも触れたように、静電気を体から自然に放出するためには水分が欠かせません。乾燥対策=静電気対策でもありますので、肌の保湿、部屋の加湿は常日頃から心がけたいところです。以上、静電気の性質や、その発生を抑える方法について解説しました。ちなみに、筆者は「ドアノブに触る前に壁を触る」ことを実践し始めてから「バチッ」が明らかに減りました。皆さんも、ここに挙げた対策を実践して、不快な静電気に負けない冬をお過ごし下さいね。
<参考サイト>
静電気の悩みはこれで解決! すぐに試せる5つの対策(沢井製薬「サワイ健康推進課」)
https://kenko.sawai.co.jp/theme/201912.html
静電気が起こるのはなぜ?原因と対策を詳しく解説【医師監修】(Cosmopolitan)
https://www.cosmopolitan.com/jp/trends/lifestyle/a34779783/reason-and-how-to-prevent-static-electricity/
静電気の基礎知識(キーエンス「静電気ドクター」)
https://www.keyence.co.jp/ss/products/static/static-electricity/basic/
「バチッ! 」と静電気が起きるわけ&すぐにできる! 手軽な【静電気防止対策】(東京ガス「ウチコト」)
https://tg-uchi.jp/topics/4069
静電気の発生原因(ホーザン株式会社「静電気対策の森」)
https://www.hozan.co.jp/esd/foundation/cause.html
静電気の悩みはこれで解決! すぐに試せる5つの対策(沢井製薬「サワイ健康推進課」)
https://kenko.sawai.co.jp/theme/201912.html
静電気が起こるのはなぜ?原因と対策を詳しく解説【医師監修】(Cosmopolitan)
https://www.cosmopolitan.com/jp/trends/lifestyle/a34779783/reason-and-how-to-prevent-static-electricity/
静電気の基礎知識(キーエンス「静電気ドクター」)
https://www.keyence.co.jp/ss/products/static/static-electricity/basic/
「バチッ! 」と静電気が起きるわけ&すぐにできる! 手軽な【静電気防止対策】(東京ガス「ウチコト」)
https://tg-uchi.jp/topics/4069
静電気の発生原因(ホーザン株式会社「静電気対策の森」)
https://www.hozan.co.jp/esd/foundation/cause.html
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子
毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング
長谷川眞理子







