テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
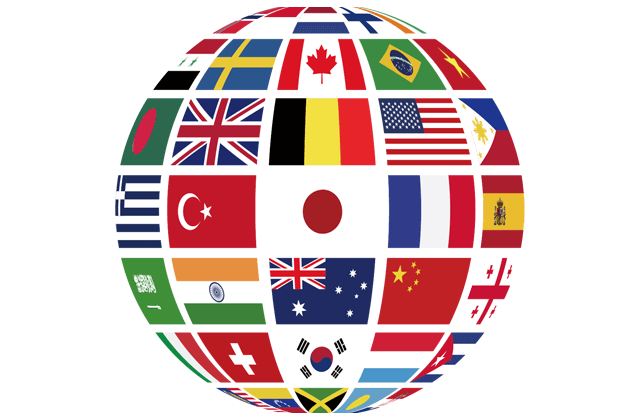
同じ曲や縦読みも…世界のユニークな国歌
スポーツの世界大会などで耳にする機会が多い国歌。特に日本の『君が代』と世界の国歌を聞き比べると、その雰囲気の違いに驚くことが多いです。
今回は世界の国歌の中でも、成り立ちの経緯や歌詞がユニークな国歌をご紹介しましょう。
イギリス(正確にはイギリス王室属領)とリヒテンシュタインの国歌は、メロディーが同じ曲を採用しています。作曲者は不明ですが、スコットランドの民謡を元にしているという説があるようです。
実は同じ曲をドイツやロシア、スイスなどでもかつて国歌として使われていたことがあったようです。その中で、今も国歌として歌い続けているのがイギリスとリヒテンシュタインなのです。
イギリス国歌は統治者の女王を賛美する歌(男性の王が即位した場合は歌詞も変更)、リヒテンシュタイン国歌は自然が美しい祖国を讃える歌となっています。
【フィンランド『我らの地』、エストニア『我が故国、我が誇りと喜び』】
フィンランドとエストニアの国歌も同じ曲です。作曲者は“フィンランド音楽の父”と称されたドイツ出身の音楽家フレドリク・パーシウス。フィンランドでは1919年に、エストニアでは1920年に国歌として採用されました。
フィンランドとエストニアはフィンランド湾を隔てた隣国同士で文化が影響しあっていたため、国歌も同じメロディーが使われたと考えられます。
歌詞はそれぞれの国の歌詞があてられていますが、いずれも祖国への愛を高らかに歌い上げるものとなっています。
スペインの国歌は歌詞がないことで知られています。曲は『擲弾兵行進曲』という作曲者不明の曲で、1761年に歩兵部隊の行進曲として採用されたのが起源だそう。のちに国王の公式行事に使われるようになったことで『国王行進曲』という曲名で認知度が高まり、1870年に国歌として正式に採用されましたが、歌詞はつけられませんでした。
歌詞は19世紀に在位したアルフォンソ13世、そしてスペイン内戦で政権を勝ち取ったフランシスコ・フランコの時に作成されたものの、いずれも定着せずに終わってしまいます。
2007年になって、ようやくスペインのオリンピック協会主導で歌詞が公募されました。このとき7000件の応募が集まりましたが、正式に発表される直前で歌詞が流出。歌詞の中の「スペイン万歳」といった文言を問題視した左派の反発もあって、歌詞の制定は無期限の延期となってしまいました。
もともとスペインには異なる言語を持つ民族がいるうえ、カタルーニャのような独立州もあるなど民族的に複雑な事情を抱えています。挙国一致で歌詞を決めるのは難しいのかもしれません。
『ドイツの歌』は音楽家ハイドンが作曲した『神よ、皇帝フランツを守り給え』に歌詞がついて生まれました。1848年のドイツ革命の際、市民運動の象徴として広く知られるようになり、ドイツ帝国崩壊後に生まれたワイマール共和国時代に正式に国歌となりました。
ではなぜ3番だけ歌われているかというと、1番と2番よりも、3番がもっとも国歌としてふさわしいから、というのがその理由です。
1番は「ドイツよ、すべてのものに勝るドイツよ」、「マース川からメーメル川、エチュ川からベルト海峡に至るまで」といった歌詞が、ナチスドイツの選民思想、かつ広大な領土支配を正当化するのに都合よく解釈されたという経緯があり、現在のドイツ連邦共和国が目指す理想と相反するという理由から歌われなくなりました。
そして2番は「ドイツの女、ドイツの忠義、ドイツのワイン、ドイツの歌曲……」と、ドイツ人が好きなものを並べたて、称賛する歌詞。続く3番は「統一と正義と自由を、父なる祖国ドイツのために」といった雄大で勇ましい歌詞となっています。比較して2番よりは3番のほうが、質実剛健なイメージのドイツらしい国歌と考えられたのでしょう。
タイトルの「ヴィルヘルムス・ファン・ナッソウエ」とは、現オランダ王家の初代オラニエ公ウィレム1世のことです。曲はフランスの従軍歌で、作詞はウィレム1世の腹心マルニクスといわれます。
歌詞は全部で15番まであり、全体の内容はウィレム家への賛美が中心です。現在は1番と6番のみ歌われており、王室と祖国そして神への忠誠を誓う歌詞となっています。
さて、その15番ある歌詞のうち各1節目の頭文字を縦に読むと、ある言葉が浮かび上がります。
(1番)Wilhelmus van Nassouwe …
(2番)In Godes vrees te leven …
(3番)Lydt u myn Ondersaten …
(4番)Lyf en goet al te samen …
(5番)Edel en Hooch gheboren …
(6番)Mijn schild ende betrouwen …
(7番)Van al die my beswaren …
(8番)Als David moeste vluchten …
(9番)Na tsuer sal ick ontfanghen …
(10番)Niet doet my meer erbarmen …
(11番)Als een Prins op gheseten …
(12番)Soo het den wille des Heeren …
(13番)Seer Prinslick was ghedreven …)
(14番)Oorlof, mijn arme schapen …
(15番)Voor Godt wil ick belijden …
縦に読むと“WILLEM VAN NASSOV(ナッソウのウィレム)”。つまりウィレム1世のことで、マルニクスのウィレム1世への並々ならぬ忠誠心を表現していると考えられています。なんともオシャレな歌詞ですよね。
今回は世界の国歌の中でも、成り立ちの経緯や歌詞がユニークな国歌をご紹介しましょう。
違う国だけど同じメロディーを歌う国歌
【イギリス『女王陛下万歳』、リヒテンシュタイン『若きライン川上流に』】イギリス(正確にはイギリス王室属領)とリヒテンシュタインの国歌は、メロディーが同じ曲を採用しています。作曲者は不明ですが、スコットランドの民謡を元にしているという説があるようです。
実は同じ曲をドイツやロシア、スイスなどでもかつて国歌として使われていたことがあったようです。その中で、今も国歌として歌い続けているのがイギリスとリヒテンシュタインなのです。
イギリス国歌は統治者の女王を賛美する歌(男性の王が即位した場合は歌詞も変更)、リヒテンシュタイン国歌は自然が美しい祖国を讃える歌となっています。
【フィンランド『我らの地』、エストニア『我が故国、我が誇りと喜び』】
フィンランドとエストニアの国歌も同じ曲です。作曲者は“フィンランド音楽の父”と称されたドイツ出身の音楽家フレドリク・パーシウス。フィンランドでは1919年に、エストニアでは1920年に国歌として採用されました。
フィンランドとエストニアはフィンランド湾を隔てた隣国同士で文化が影響しあっていたため、国歌も同じメロディーが使われたと考えられます。
歌詞はそれぞれの国の歌詞があてられていますが、いずれも祖国への愛を高らかに歌い上げるものとなっています。
歌詞のない国歌
【スペイン『国王行進曲』】スペインの国歌は歌詞がないことで知られています。曲は『擲弾兵行進曲』という作曲者不明の曲で、1761年に歩兵部隊の行進曲として採用されたのが起源だそう。のちに国王の公式行事に使われるようになったことで『国王行進曲』という曲名で認知度が高まり、1870年に国歌として正式に採用されましたが、歌詞はつけられませんでした。
歌詞は19世紀に在位したアルフォンソ13世、そしてスペイン内戦で政権を勝ち取ったフランシスコ・フランコの時に作成されたものの、いずれも定着せずに終わってしまいます。
2007年になって、ようやくスペインのオリンピック協会主導で歌詞が公募されました。このとき7000件の応募が集まりましたが、正式に発表される直前で歌詞が流出。歌詞の中の「スペイン万歳」といった文言を問題視した左派の反発もあって、歌詞の制定は無期限の延期となってしまいました。
もともとスペインには異なる言語を持つ民族がいるうえ、カタルーニャのような独立州もあるなど民族的に複雑な事情を抱えています。挙国一致で歌詞を決めるのは難しいのかもしれません。
3番だけを歌う国歌
【ドイツ『ドイツの歌』】『ドイツの歌』は音楽家ハイドンが作曲した『神よ、皇帝フランツを守り給え』に歌詞がついて生まれました。1848年のドイツ革命の際、市民運動の象徴として広く知られるようになり、ドイツ帝国崩壊後に生まれたワイマール共和国時代に正式に国歌となりました。
ではなぜ3番だけ歌われているかというと、1番と2番よりも、3番がもっとも国歌としてふさわしいから、というのがその理由です。
1番は「ドイツよ、すべてのものに勝るドイツよ」、「マース川からメーメル川、エチュ川からベルト海峡に至るまで」といった歌詞が、ナチスドイツの選民思想、かつ広大な領土支配を正当化するのに都合よく解釈されたという経緯があり、現在のドイツ連邦共和国が目指す理想と相反するという理由から歌われなくなりました。
そして2番は「ドイツの女、ドイツの忠義、ドイツのワイン、ドイツの歌曲……」と、ドイツ人が好きなものを並べたて、称賛する歌詞。続く3番は「統一と正義と自由を、父なる祖国ドイツのために」といった雄大で勇ましい歌詞となっています。比較して2番よりは3番のほうが、質実剛健なイメージのドイツらしい国歌と考えられたのでしょう。
歌詞の“縦読み”で国王への賛辞を織り込んだ国歌
【オランダ『ヴィルヘルムス・ファン・ナッソウエ』】タイトルの「ヴィルヘルムス・ファン・ナッソウエ」とは、現オランダ王家の初代オラニエ公ウィレム1世のことです。曲はフランスの従軍歌で、作詞はウィレム1世の腹心マルニクスといわれます。
歌詞は全部で15番まであり、全体の内容はウィレム家への賛美が中心です。現在は1番と6番のみ歌われており、王室と祖国そして神への忠誠を誓う歌詞となっています。
さて、その15番ある歌詞のうち各1節目の頭文字を縦に読むと、ある言葉が浮かび上がります。
(1番)Wilhelmus van Nassouwe …
(2番)In Godes vrees te leven …
(3番)Lydt u myn Ondersaten …
(4番)Lyf en goet al te samen …
(5番)Edel en Hooch gheboren …
(6番)Mijn schild ende betrouwen …
(7番)Van al die my beswaren …
(8番)Als David moeste vluchten …
(9番)Na tsuer sal ick ontfanghen …
(10番)Niet doet my meer erbarmen …
(11番)Als een Prins op gheseten …
(12番)Soo het den wille des Heeren …
(13番)Seer Prinslick was ghedreven …)
(14番)Oorlof, mijn arme schapen …
(15番)Voor Godt wil ick belijden …
縦に読むと“WILLEM VAN NASSOV(ナッソウのウィレム)”。つまりウィレム1世のことで、マルニクスのウィレム1世への並々ならぬ忠誠心を表現していると考えられています。なんともオシャレな歌詞ですよね。
世界の国歌に耳を傾けてみよう
普段はつい聞き流してしまう国歌も、歌詞と由来を知るとおもしろい発見がたくさんあります。今回ご紹介しきれなかったユニークな国歌はまだまだたくさんありますので、ぜひ探してみてくださいね。人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










