テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
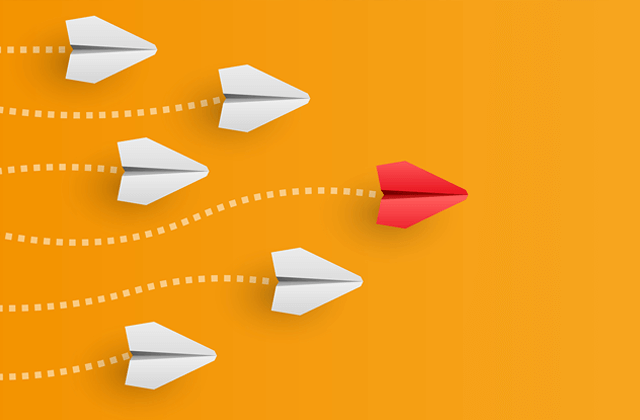
世界の「競争力」ランキング
国や地域の経済的な力を図る指標にはいくつかあります。中でも「競争力」という視点はこの先を占う上で重要な指標と言えるでしょう。この点ついてはスイス・ローザンヌのビジネススクールIMD(国際経営開発研究所:International Institute for Management Development)が「世界競争力年鑑(World Competitiveness Yearbook)」をまとめています。ここでは2021年版に示されているランキングをみてみましょう。
大分類:経済状況
小分類:国内経済、貿易、国際投資、雇用、物価
大分類:政府効率性
小分類:財政、租税政策、制度的枠組み、ビジネス法制、社会的枠組み
大分類:ビジネス効率性
小分類:生産性・効率性、労働市場、金融、経営プラクティス、取り組み・価値観
大分類:インフラ
小分類:基礎インフラ、技術インフラ、科学インフラ、健康・環境、教育
これらの分類に使用される統計データは各国ごとに337個の指標となっています。またこのうち、アンケートデータは92個です。
これによると、トップ3は1位スイス(2020年3位)、2位スウェーデン(2020年6位)、3位デンマーク(2020年2位)となっています。2位、3位に北欧の国が入っていますが、他にも6位にはノルウェー(2020年7位)、11位にフィンランド(2020年13位)が入っています。
一方、2020年版で1位だったシンガポールは5位に後退しています。このほか、アジアでは、7位の香港(2020年5位)、8位の台湾(2020年11位)といったところが比較的上位にランクインしています。ちなみにアメリカは10位(2020年10位)となっています。
1位スイスが評価されているポイントを見てみましょう。小分類での1位の項目は、「政府効率性」からは「財政」と「制度的枠組み」、「ビジネス効率性」から「金融」、インフラから「教育」となっています。平均して他の項目もおおよそトップ15以内にいるのですが、唯一「物価」のみ58位です。2017年からの順位変動としては、2017年2位、2018年5位、2019年4位、2020年3位といったように順調に上位をキープし続けています。
2020年のデータを分析している三菱総合研究所の資料では、特に近年においては「グローバル化」「ICT化」「人材」の3点が重視される傾向にあるとのこと。このあたりは以前から日本の弱みとしてよく話題に上がるポイントではあります。ランキングの低い項目をみると「財政」63位、「経営プラクティス」62位、「物価」61位となっています。一方、ランキングが高い項目は「雇用」が2位、「国内経済」が8位、科学インフラが同じく8位、国際投資が9位、健康・環境で9位といったところです。
2020年のデータと比較すると、あまり大きな変化はありません。2020年の調査でもっとも順位の低かった「経営プラクティス」は2020年から変わらず62位、次に低かった「財政」は61位から63位へ下げ、2020年で3つ目にランキングが低かった「物価」は59位から61位に下げています。順位変動の大きさで見ると「貿易」が39位から43位に4つ下げた以外は、全ての値で2020年から3つ以内の変動に収まっています。2020年に比べて最もランキングが上がった項目は「金融」で18位から15位です。
経済状況、政府効率性、ビジネス効率性、インフラの4つの指標
IMDの「世界競争力年鑑」は、競争力に関するその地域の統計データと、企業の経営層を対象とするアンケート調査から導き出されています。これを世界63の国や地域を対象として収集したものです。統計データだけでなくアンケートを取り入れることにより、データだけからは見えにくい側面を反映させ、幅広い視点から分析できる仕組みになっているようです。大分類としては「経済状況」「政府の効率性」「ビジネスの効率性」「インフラ」の4つがあり、ここからさらに大分類ごとに5つの小分類(計20個)があります。これらをもとにして、総合的な順位が導き出されています。5つの大分類、およびその下にある20の小分類は以下の通り。なお、和訳は三菱総合研究所のものに沿っています。大分類:経済状況
小分類:国内経済、貿易、国際投資、雇用、物価
大分類:政府効率性
小分類:財政、租税政策、制度的枠組み、ビジネス法制、社会的枠組み
大分類:ビジネス効率性
小分類:生産性・効率性、労働市場、金融、経営プラクティス、取り組み・価値観
大分類:インフラ
小分類:基礎インフラ、技術インフラ、科学インフラ、健康・環境、教育
これらの分類に使用される統計データは各国ごとに337個の指標となっています。またこのうち、アンケートデータは92個です。
2021年度のランキングトップはスイス
この調査における実際のランキングをみてみましょう(2021年版)。これによると、トップ3は1位スイス(2020年3位)、2位スウェーデン(2020年6位)、3位デンマーク(2020年2位)となっています。2位、3位に北欧の国が入っていますが、他にも6位にはノルウェー(2020年7位)、11位にフィンランド(2020年13位)が入っています。
一方、2020年版で1位だったシンガポールは5位に後退しています。このほか、アジアでは、7位の香港(2020年5位)、8位の台湾(2020年11位)といったところが比較的上位にランクインしています。ちなみにアメリカは10位(2020年10位)となっています。
1位スイスが評価されているポイントを見てみましょう。小分類での1位の項目は、「政府効率性」からは「財政」と「制度的枠組み」、「ビジネス効率性」から「金融」、インフラから「教育」となっています。平均して他の項目もおおよそトップ15以内にいるのですが、唯一「物価」のみ58位です。2017年からの順位変動としては、2017年2位、2018年5位、2019年4位、2020年3位といったように順調に上位をキープし続けています。
日本は31位
2021年の日本の順位は31位となっています。これまでの変動を見ると、この年鑑がスタートした1989年の時点での日本のランキングは1位となっています。その後1992年までは1位をキープし、1996年まで2位から4位を移動しています。1997年に17位まで落ち、ここ数年は25位前後で変動しましたが、2019年は30位、2020年は34位となっています。2020年のデータを分析している三菱総合研究所の資料では、特に近年においては「グローバル化」「ICT化」「人材」の3点が重視される傾向にあるとのこと。このあたりは以前から日本の弱みとしてよく話題に上がるポイントではあります。ランキングの低い項目をみると「財政」63位、「経営プラクティス」62位、「物価」61位となっています。一方、ランキングが高い項目は「雇用」が2位、「国内経済」が8位、科学インフラが同じく8位、国際投資が9位、健康・環境で9位といったところです。
2020年のデータと比較すると、あまり大きな変化はありません。2020年の調査でもっとも順位の低かった「経営プラクティス」は2020年から変わらず62位、次に低かった「財政」は61位から63位へ下げ、2020年で3つ目にランキングが低かった「物価」は59位から61位に下げています。順位変動の大きさで見ると「貿易」が39位から43位に4つ下げた以外は、全ての値で2020年から3つ以内の変動に収まっています。2020年に比べて最もランキングが上がった項目は「金融」で18位から15位です。
<参考サイト>
World Competitiveness Ranking
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
IMD「世界競争力年鑑2020」からみる日本の競争力 第1回:日本の総合順位は30位から34位に下落|MRI三菱総合研究所
https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20201008.html
World Competitiveness Ranking
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
IMD「世界競争力年鑑2020」からみる日本の競争力 第1回:日本の総合順位は30位から34位に下落|MRI三菱総合研究所
https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20201008.html
人気の講義ランキングTOP20
昭和陸軍の派閥抗争には三つの要因があった
中西輝政
なぜ変異が必要なのか…現代にも通じる多様性創出の原理
長谷川眞理子










