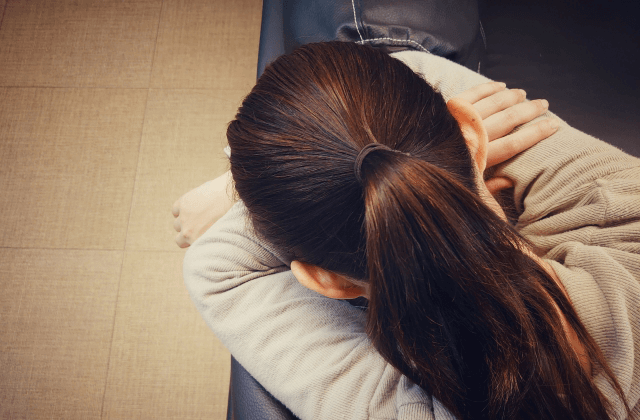
人の話が頭に入らない…その原因とは?
「この前、伝えたでしょう」「人の話、聞いてないですよね」と言われることが多い人、その理由は自分ではっきりしているでしょうか。ちゃんと聞いているつもりなのに、相手の話が頭に入りづらくなるわけは、人によって違います。思い当たる要因と対処法を、あれこれ探ってみましょう。
余裕があれば十分処理できそうなものですが、そこが曲者。
漫然と聞いているとき、脳は余裕を生かして、ネット・サーフィンをするように次々と連想状態に入ります。たとえば相手が「今朝あった嫌なこと」を話しているとき、聞き手のあなたはその相手との間で体験した「嫌なこと」を連想しているかもしれません。もっと部分的に、「相手が持っていた傘の色」から自由連想に入ってしまうこともあります。
それらは病的でもなければ機能的な問題でもなく、意識が自分の側に向いているために起きるコミュニケーション上の障害です。脳は本来自己チューにできていて、よほど意識的にならないと相手に耳を傾けることはできません。
つまり、話をきちんと聞いている「つもり」なのに聞こえていない状態は、決して珍しくありません。親しい間の雑談なら、よく聞いていなくても大したトラブルにはなりませんが、問題は相手の話の核心部分を上の空で聞き逃した場合です。
「言った」「言わない」「聞いていない」のトラブルを避けるためにできることは、いくつかあります。とにかく遠慮をしないで、会話に積極的に参加すること。相手の言葉を単純にくり返すおうむ返しも、話が自分の言葉になるため効果的ですし、質問をしたり、あいづちを打ったりするのも、会話が自分の側に引き寄せられることで、内容が記憶に残りやすくなります。
脳疲労は、スマホやPC、ゲームなどを通じてどんどん新しい情報が勝手に入ってくるために脳に高負荷をかけている状態。現代人のほとんどが自ら望んでその状態に身を置いています。ストレスや睡眠不足などが引き金となり、疲労が限界に達すると、ブレインフォグの症状としてあらわれます。
ブレインフォグ(脳の霧)は、頭にモヤがかかったようにぼんやりして、考えることも集中することもむずかしい状態です。それ自体は病気ではありませんが、うつ病やADHD、慢性疲労症候群などの病気が潜んでいる場合もあります。
現在注目されているのは、新型コロナ感染の後遺症としての「だるさ」「やる気のなさ」として出現するブレインフォグ。集中力欠如から仕事でミスを連発したり、友人や家族との関係が悪くなるため、うつ病を疑う人が多いのですが、抗うつ薬自体がブレインフォグの原因になる場合も多いので厄介です。
ブレインフォグなのか、うつ病や認知症の始まりなのか、自分では判断できません。睡眠・休息をしっかり取っても改善しないようなら、信頼できる医師に相談してみましょう。
おとなのADHDが注目されはじめたのは21世紀に入ってから。子どもの頃は「家庭教育(しつけ)がなっいてない」「甘えている」「性格の問題」と片付けられがちでしたが、働きはじめることで求められる高い行動基準に適応できなくなり、自覚するケースも増えています。
ケアレスミスを毎度繰り返す人、毎朝出がけにバタバタしたり、衝動買いで後悔することの多い人、部屋やデスクの上を片付けられない人は、ADHDの診断テストをチェックしてみるのもいいかもしれません。
ただ、ADHDは病気というよりその人が持っている特性や個性のようなものですから、治すということは難しくなります。たとえば耳から入る情報処理が苦手なら、メモを取るなど視覚化してみる、逆に目や手を使う作業が苦手であればボイスメモを活用するなど、自分にあった方法を工夫していくのが大事です。
人の話を聞きながら、考えているのは自分のこと?
「傾聴」という言葉があるように、人の話に耳を傾けるのは積極的で有意義な行為。でも、普段の会話では「話す」と「聞く」の間で、脳の活動にアンバランスが起こっています。自分が話をしているときには脳の能力が総動員されますが、聞く側にまわった途端、脳には余裕ができてしまうのです。余裕があれば十分処理できそうなものですが、そこが曲者。
漫然と聞いているとき、脳は余裕を生かして、ネット・サーフィンをするように次々と連想状態に入ります。たとえば相手が「今朝あった嫌なこと」を話しているとき、聞き手のあなたはその相手との間で体験した「嫌なこと」を連想しているかもしれません。もっと部分的に、「相手が持っていた傘の色」から自由連想に入ってしまうこともあります。
それらは病的でもなければ機能的な問題でもなく、意識が自分の側に向いているために起きるコミュニケーション上の障害です。脳は本来自己チューにできていて、よほど意識的にならないと相手に耳を傾けることはできません。
つまり、話をきちんと聞いている「つもり」なのに聞こえていない状態は、決して珍しくありません。親しい間の雑談なら、よく聞いていなくても大したトラブルにはなりませんが、問題は相手の話の核心部分を上の空で聞き逃した場合です。
「言った」「言わない」「聞いていない」のトラブルを避けるためにできることは、いくつかあります。とにかく遠慮をしないで、会話に積極的に参加すること。相手の言葉を単純にくり返すおうむ返しも、話が自分の言葉になるため効果的ですし、質問をしたり、あいづちを打ったりするのも、会話が自分の側に引き寄せられることで、内容が記憶に残りやすくなります。
スマホ、脳疲労、ブレインフォグ?
会話の集中を妨げる一番の敵は、今ならスマホです。相手が話している最中にスマホを見るのはもってのほかですが、そうでなくてもスマホやPC画面を長時間見ることにより脳疲労やブレインフォグを起こしていることも多いからです。脳疲労は、スマホやPC、ゲームなどを通じてどんどん新しい情報が勝手に入ってくるために脳に高負荷をかけている状態。現代人のほとんどが自ら望んでその状態に身を置いています。ストレスや睡眠不足などが引き金となり、疲労が限界に達すると、ブレインフォグの症状としてあらわれます。
ブレインフォグ(脳の霧)は、頭にモヤがかかったようにぼんやりして、考えることも集中することもむずかしい状態です。それ自体は病気ではありませんが、うつ病やADHD、慢性疲労症候群などの病気が潜んでいる場合もあります。
現在注目されているのは、新型コロナ感染の後遺症としての「だるさ」「やる気のなさ」として出現するブレインフォグ。集中力欠如から仕事でミスを連発したり、友人や家族との関係が悪くなるため、うつ病を疑う人が多いのですが、抗うつ薬自体がブレインフォグの原因になる場合も多いので厄介です。
ブレインフォグなのか、うつ病や認知症の始まりなのか、自分では判断できません。睡眠・休息をしっかり取っても改善しないようなら、信頼できる医師に相談してみましょう。
おとなのADHD?
人の話が頭に入らない状態がずっと続いている人には、ADHD(注意欠如多動性障害)の可能性もあります。ADHDは発達障害の一種で、主に「じっとしていられない」(多動)、「注意が散漫する」(不注意)、「衝動的な行動をしたがる」(衝動性)としてあらわれます。おとなのADHDが注目されはじめたのは21世紀に入ってから。子どもの頃は「家庭教育(しつけ)がなっいてない」「甘えている」「性格の問題」と片付けられがちでしたが、働きはじめることで求められる高い行動基準に適応できなくなり、自覚するケースも増えています。
ケアレスミスを毎度繰り返す人、毎朝出がけにバタバタしたり、衝動買いで後悔することの多い人、部屋やデスクの上を片付けられない人は、ADHDの診断テストをチェックしてみるのもいいかもしれません。
ただ、ADHDは病気というよりその人が持っている特性や個性のようなものですから、治すということは難しくなります。たとえば耳から入る情報処理が苦手なら、メモを取るなど視覚化してみる、逆に目や手を使う作業が苦手であればボイスメモを活用するなど、自分にあった方法を工夫していくのが大事です。
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







