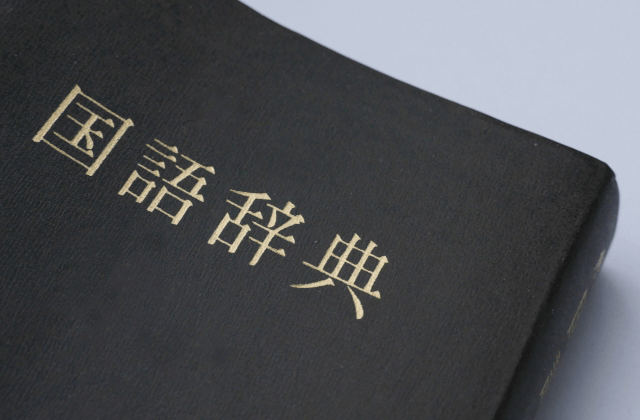
国語辞典から「消えた言葉」とは?
新語、流行語など、新しい言葉が辞書に追加される話はよく聞きます。そうした編集の裏側でニュースにはなりませんが、辞書から削除される言葉もあるのです。今回は、国語辞書の改訂にともなう言葉の扱いに迫ってみましょう。
話題となった三省堂では、5人の編集委員が中心となって、「削除する言葉」と「新たに加える言葉」を挙げていく作業からスタートするとのこと。そして、議論をした上でメンバーに異論がなければ、消すか加えるかが決まり、具体的に辞典を編集していくという流れになります。
消える言葉と残す言葉、その基準は「今使われている言葉かどうか」。三省堂 辞書出版部 奥川健太郎さんによると、一般の方々の生活語彙として広く使われているか、そして、流行語ではなく長く使われているか。その2点が言葉を選んでいく考え方になります。
例えば「MD(ミニディスク)」は消える言葉として選択されましたが、さらに古い音楽メディアである「レコード」や「カセットテープ」、「CD」という言葉は残ります。その理由は、「レコード」や「カセットテープ」といった言葉は、小説や会話で使われることが多い一方、「MD」というのはほとんど使われなくなっているといった現状からの削除判断になります。
辞書から削除された理由をそれぞれしらべてみると、
・「コギャル」→過去の風俗、
・「プロフ」→『プロフィール』の項目で略語形を説明
・「スペースシャトル」→ミッション終了 歴史的な用語に
・「タカラジェンヌ」→固有名詞を縮小する編集方針
・「マイナスイオン」→疑似科学の疑義
・「垂直飛び」→1999年のスポーツテストで削除
・「ボイン」→性俗語を縮小する編集方針
また、ガラケイからスマホの普及に応じて、「着メロ」などが削除され、スマホにまつわる言葉も新たに掲載されるようになりました。
加えて、スマホでネットショッピングをする人が増えた社会を反映して、「置き配」も新たな言葉として加わりました。若者言葉も同様に、「チル」=「のんびりとくつろぐこと」、「ぴえん」=「小声で泣きまねをするときのことば。また、小さく泣く声」も拡充されています。
「ことばで写す時代。」という三省堂のキャッチフレーズを強く感じさせる辞書の編集。辞書は毎年改訂されるタイプの書籍ではないので、長い目でみた言葉の賞味期限、消費期限についてシビアに考えさせられます。
2021年の改訂で約1700語が削除
話題のきっかけは、日本テレビ系で2022/8/22に放映された『月曜から夜ふかし』。2021年末、約8年ぶりに刷新された『三省堂国語辞典』第八版で約1100語が削除されたという特集で、「着メロ」「MD」「コギャル」「伝言ダイヤル」「テレカ」「プラズマディスプレイ」「プロフ」「携番」「スペースシャトル」「タカラジェンヌ」「マイナスイオン」「垂直飛び」「ボイン」といった言葉が紹介されました。三省堂の国語辞書の編集スタンス
辞書編集のコンセプトは出版社それぞれあります。「辞書は言葉の海を渡る舟、編集者はその海を渡る舟を編んでいく」という意味で、編集現場を描いた三浦しをんさんの小説『船を編む』にてその世界を垣間見ることができます。話題となった三省堂では、5人の編集委員が中心となって、「削除する言葉」と「新たに加える言葉」を挙げていく作業からスタートするとのこと。そして、議論をした上でメンバーに異論がなければ、消すか加えるかが決まり、具体的に辞典を編集していくという流れになります。
消える言葉と残す言葉、その基準は「今使われている言葉かどうか」。三省堂 辞書出版部 奥川健太郎さんによると、一般の方々の生活語彙として広く使われているか、そして、流行語ではなく長く使われているか。その2点が言葉を選んでいく考え方になります。
例えば「MD(ミニディスク)」は消える言葉として選択されましたが、さらに古い音楽メディアである「レコード」や「カセットテープ」、「CD」という言葉は残ります。その理由は、「レコード」や「カセットテープ」といった言葉は、小説や会話で使われることが多い一方、「MD」というのはほとんど使われなくなっているといった現状からの削除判断になります。
辞書から削除された理由をそれぞれしらべてみると、
・「コギャル」→過去の風俗、
・「プロフ」→『プロフィール』の項目で略語形を説明
・「スペースシャトル」→ミッション終了 歴史的な用語に
・「タカラジェンヌ」→固有名詞を縮小する編集方針
・「マイナスイオン」→疑似科学の疑義
・「垂直飛び」→1999年のスポーツテストで削除
・「ボイン」→性俗語を縮小する編集方針
新たに加わった言葉は?
今回の改訂で新たに辞書に入る言葉には、2019年から蔓延したコロナ禍をうけて、「黙食」や「ソーシャルディスタンス」など。また、ガラケイからスマホの普及に応じて、「着メロ」などが削除され、スマホにまつわる言葉も新たに掲載されるようになりました。
加えて、スマホでネットショッピングをする人が増えた社会を反映して、「置き配」も新たな言葉として加わりました。若者言葉も同様に、「チル」=「のんびりとくつろぐこと」、「ぴえん」=「小声で泣きまねをするときのことば。また、小さく泣く声」も拡充されています。
「ことばで写す時代。」という三省堂のキャッチフレーズを強く感じさせる辞書の編集。辞書は毎年改訂されるタイプの書籍ではないので、長い目でみた言葉の賞味期限、消費期限についてシビアに考えさせられます。
<参考サイト>
・三省堂国語辞典第八版
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/sankoku8/index.html
・三省堂国語辞典第八版
https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/topic/sankoku8/index.html
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







