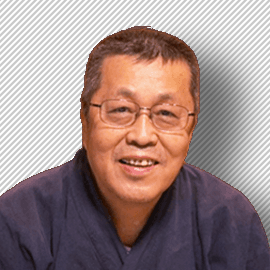●本物を見ながら物づくりがしたくて刀鍛冶の道へ
質問 刀鍛冶を志すようになったきっかけについてお聞きしたいのですが。
松田 私は北海道の出身で、刀というものは、ほとんど見たことがありませんでした。でも、小さい頃から時代劇などで刀は何となく知ってはいました。その後、絵をやるために東京へ出てきて、絵を一生懸命見たのですが、刀も国立博物館などで見て、「刀っていいな」と思ったのです。
しかし、絵はやめました。なぜ絵をやめたのかというと、私は地方で生活していた人間ですから、例えばゴッホとかセザンヌの本物を東京で初めて見たのですが、その時、絵をやるのは難しいと思ったのがその理由です。でも、日本の美術品の中で何か本物を見ながら物をつくることができないかと思っていました。そんな時、東京で刀を見ていて、ぜひ自分でもつくってみたいということになり、刀鍛冶を始めたのです。やはり日本刀は日本にしかないですし、いい刀も日本にしかないですから。
少し戻りますが、なぜ芸大に入り直そうとしてまで絵をやりたかったのかというと、やはりフランスでもドイツでもイタリアでも、そういうところで絵の勉強をしたかったからです。本物を見ながら勉強したかったのです。でも、それが無理だということで、絵はすっぱりやめました。そこは日本画でも良かったのでしょうが、私は日本画というものにはどうもそれほど興味がわきませんでした。それで、刀の方へ入っていったのです。
●目標も苦労もその時々で変化してきた
質問 実際に刀をつくっていく中で、特に苦労している点、また、志していることはどんなことですか?
松田 もう40年ほど刀鍛冶をやっていますから、その時々で思いは変わりますが、初めの頃は、ただ「刀をつくりたいな」ということで始めました。ある時期になると、日本刀は、800年ほど前の鎌倉時代のものを基準にしているということが分かって、何とかその技術を知りたいというのが、目標になったのです。
そして、ある程度それが分かってくると、いいもの、いわゆる国宝や重要文化財に指定を受けているものに、どうすれば近づくことができるかを考えるようになりました。それはただ単に鎌倉時代のものを再現したからいいということではなく、質の問題になってくるわけです。いい材料をどうやって手に入れたらいいだろうか、ということです。
刀は和...