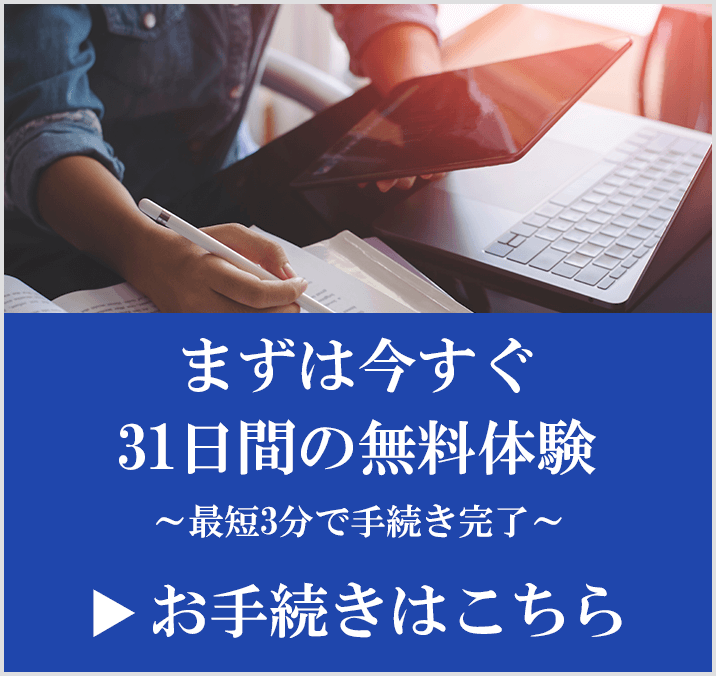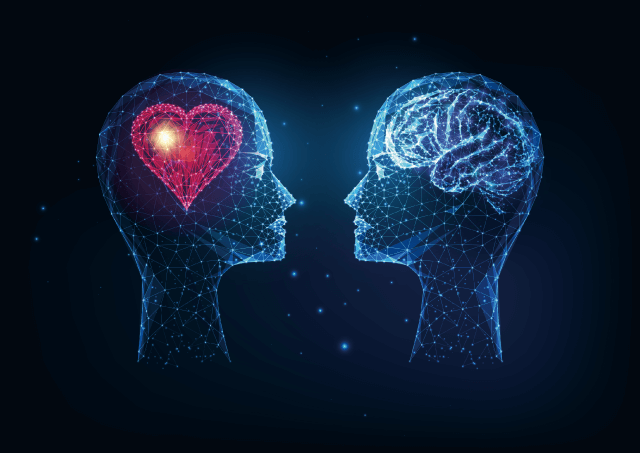●「知情意」とパスカルのことば
日本では、認知科学などが発達するよりずっと前の昔から「知情意」というような言い方をしていました。
「知」というのはおそらく認知・認識のことで、頭で考えることとか、分かって理性で行うことという感じで、道筋をつけて理解をし、言語化すなわち言葉で言えるようにすること。これが「知」ではないかと。
「情」というのは、感情・情動のことでしょう。好き・嫌いとか、「~ような感じがする」とか、気分やムードとか、快・不快など、はっきり言語化されないことが多いのですが、何か分かっているということです。
それに対して「意」というのは、私もよく分からなかったのですが、これは意志でしょう。良いことか悪いことかという倫理的・道徳的な判断も含めて、動機づけによってこれをするのだと決める意志が「意」で、古くからいわれている日本の「知情意」というのは、そういうことのようです。
そうすると、今の脳の働きの研究などからすると、「知」と「情」が合わさって、ある種の判断で行うことが「意」で、(言い換えると)「知」と「情」を混ぜ合わせ、プラス動機付けで、「これをしてはいけない」というような価値観も含めたものが「意」なのでしょう。
日本人が、昔からこのように「知情意」を分けて考えていたということ、(そのうちの)どれかがいいというわけではなかったというのは素晴らしいことだと思います。欧米のように、言語で何でも表して説得していく文化では「知」の部分が大きく持ち上げられます。たしかに「知」は大事ですが、「情」や「意」の部分も非常に大事です。三つを同じように表現して、同等に重みづけする考えは結構なことだし、本当にそうだと思います。
『パンセ』を書いたブレ―ズ・パスカルが面白いことを言っています。「心は理性のあずかり知らぬ理由を持つ」ということです。ここでは“heart”と“reason”が分けてあって、“heart”が「情」、“reason”が理性だから「知」でしょう。その“heart”には“own reason”があって“which reason does not know”、「心には理性が分からない理由がある」ということを書いています。やはり「情」の部分と考えていることにはズレがあり、必ずしも「知」が勝つわけでもないということを、パスカルは分かっていたようです。