テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
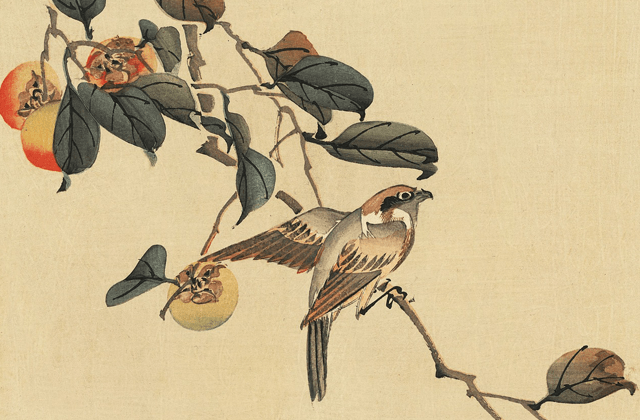
境界がないのに枠がある、日本美術の特質
日本美術ブームは、1990年代の若冲を皮切りに、今なお続いています。2017年は、国宝展と運慶展が東西で行われて大評判。2018年春の東京国立博物館では「名作誕生 つながる日本美術」と題した展覧会を企画。鑑真とともに渡来した仏像と雪舟や宗達、若冲を同時に展示するなど、思いがけない工夫を凝らしています(会期は4月13日~5月28日。展示作品は期間により入れ替えあり)。今日は、日本美術の「面白がり方」について、東博や文化庁を経て東京大学大学院人文社会系研究科で日本美術史を教える佐藤康宏教授に教わってみました。
ギリシャやローマの「円盤投げ」などの彫刻を見ても、中国の「武将俑」を見ても、紀元前3-4世紀、ヘレニズムの時代にはすでに徹底したリアリズムに基づく造形が行われていたことが分かります。
一方、縄文時代中期(約5500-4500年前)のものとして出土した山形県西ノ前遺跡の「土偶」(通称「縄文の女神」、国宝)は、どうでしょうか。表情をあらわす腕と顔面は省略され、弓形の髪、三角の肩・胸・腰、太い柱のような脚が大胆な曲線と直線の組み合わせで、見事なフォルムを生み出しています。「ジャコメッティに見せたい」と佐藤氏が言うように、シャープで洗練された美意識を感じさせるものです。
たとえば古代ギリシャでは陶芸が盛んでしたが、シルエットと線刻によって繊細な絵を描く「黒絵・赤絵・白絵」などが広まります。大英博物館やルーヴル美術館にさまざまな皿やアンフォラ(壺)が展示されています。佐藤氏が例にとるのは、ミノタウロス退治の物語絵が入った「黒像式頭部アンフォラ」。具体的な描写で描かれた物語絵が中心を占め、周縁的な場所に抽象的文様が刻まれています。
かたや縄文土器を見ると、強い生命力や豊穣を象徴する「蛇」が代表的なモチーフです。口縁部分には具象的な蛇の表現がほどこされ、胴体部分の縄目や渦巻、S字なども、抽象化された蛇だと言われています。具象と抽象が境界を隔てず、ぐるりと器を取り巻いて、土器に魔術的な力を与えています。
イメージと文字の間の境界を破った例としてあげられるのは、パリの建物を描いた20世紀初頭の西洋画家、佐伯祐三です。ルネサンス以降、絵画空間から排除されていた文字をパリの建物やポスターから取り込んで、世界が揺れ動いている感じ、一瞬一瞬に変化する世界の有り様を表現したことが、天才の評価をより一段押し上げました。
一方「枠」の存在は、12世紀の絵巻「信貴山縁起」の放埓な表現に明らかです。画面を飛び出して空中を飛び移る米俵の存在が、見るものによく伝わる表現方法。上下の枠があるからこそ、内側と外側の関係が強調され、画の中の空間が画面の枠を越えるからこそ、鑑賞者は枠を意識するのです。
俵屋宗達の傑作「風神雷神図」の画面は、対角線が枠を強調する仕掛けになっています。また、風神の裳と雷神の太鼓が画面の上端からはみ出すことで、空はずっと画面の外にまで続いていることが示されます。画面の枠を強く意識させる形式であるからこそ、その枠を超えるものの効果はいっそう生きてきます。
日本美術では、「本当らしさ」はいつも部分的。ただ一つの見方で、この世界を把握するのは無理だと告げているようだ、と佐藤氏は考えています。
ジャコメッティに見せたかった「縄文の女神」
「境界がないのに、枠がある」。それが日本美術を、ヨーロッパや中国のものと分ける特質だと佐藤氏は言います。その最初の例は、「具象と抽象が、一つの空間に共存する」ことです。ギリシャやローマの「円盤投げ」などの彫刻を見ても、中国の「武将俑」を見ても、紀元前3-4世紀、ヘレニズムの時代にはすでに徹底したリアリズムに基づく造形が行われていたことが分かります。
一方、縄文時代中期(約5500-4500年前)のものとして出土した山形県西ノ前遺跡の「土偶」(通称「縄文の女神」、国宝)は、どうでしょうか。表情をあらわす腕と顔面は省略され、弓形の髪、三角の肩・胸・腰、太い柱のような脚が大胆な曲線と直線の組み合わせで、見事なフォルムを生み出しています。「ジャコメッティに見せたい」と佐藤氏が言うように、シャープで洗練された美意識を感じさせるものです。
絵付けの違う古代の陶芸
抽象的な文様も、ヨーロッパや中国と日本では扱いが異なります。たとえば古代ギリシャでは陶芸が盛んでしたが、シルエットと線刻によって繊細な絵を描く「黒絵・赤絵・白絵」などが広まります。大英博物館やルーヴル美術館にさまざまな皿やアンフォラ(壺)が展示されています。佐藤氏が例にとるのは、ミノタウロス退治の物語絵が入った「黒像式頭部アンフォラ」。具体的な描写で描かれた物語絵が中心を占め、周縁的な場所に抽象的文様が刻まれています。
かたや縄文土器を見ると、強い生命力や豊穣を象徴する「蛇」が代表的なモチーフです。口縁部分には具象的な蛇の表現がほどこされ、胴体部分の縄目や渦巻、S字なども、抽象化された蛇だと言われています。具象と抽象が境界を隔てず、ぐるりと器を取り巻いて、土器に魔術的な力を与えています。
境界や枠を越えるからこそ、意味が強く意識される
「紅白梅図屏風」(国宝)は、尾形光琳の代表的な作品ですが、具象と抽象の共存を見事に果たしています。紅白の梅は枝やおしべ・めしべに至るまで具象的に描かれながら、二つを分断する黒い川の流れは自然の波紋に基づくものの、ほとんど完全な模様です。そして、空間を埋め尽くす圧倒的な金箔は、さらに抽象の進んだ段階。これら三者の対比が複雑な人間感情をも表し、梅と水流の組み合わせが官能に訴えると佐藤氏は解説します。イメージと文字の間の境界を破った例としてあげられるのは、パリの建物を描いた20世紀初頭の西洋画家、佐伯祐三です。ルネサンス以降、絵画空間から排除されていた文字をパリの建物やポスターから取り込んで、世界が揺れ動いている感じ、一瞬一瞬に変化する世界の有り様を表現したことが、天才の評価をより一段押し上げました。
一方「枠」の存在は、12世紀の絵巻「信貴山縁起」の放埓な表現に明らかです。画面を飛び出して空中を飛び移る米俵の存在が、見るものによく伝わる表現方法。上下の枠があるからこそ、内側と外側の関係が強調され、画の中の空間が画面の枠を越えるからこそ、鑑賞者は枠を意識するのです。
俵屋宗達の傑作「風神雷神図」の画面は、対角線が枠を強調する仕掛けになっています。また、風神の裳と雷神の太鼓が画面の上端からはみ出すことで、空はずっと画面の外にまで続いていることが示されます。画面の枠を強く意識させる形式であるからこそ、その枠を超えるものの効果はいっそう生きてきます。
日本美術では、「本当らしさ」はいつも部分的。ただ一つの見方で、この世界を把握するのは無理だと告げているようだ、と佐藤氏は考えています。
人気の講義ランキングTOP20










