テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
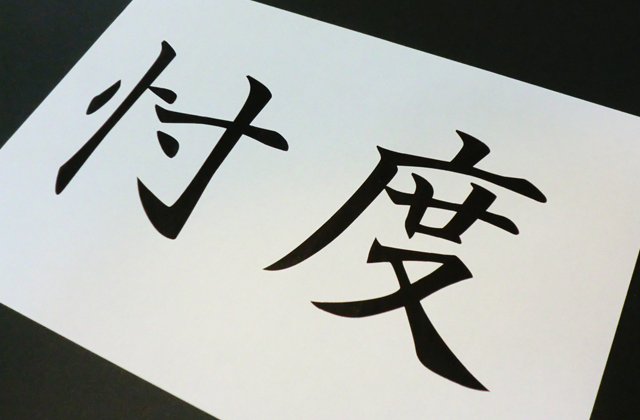
繰り返される「忖度」…自主規制はどう起こる?
「忖度」という言葉が2017年の流行語に選ばれ、日々の会話の中で、ちょっとした社会批判を含みながら、何気なく口に出す人も増えたように思います。元は「相手の気持ちを慮る」というプラスの意味も持っていましたが、最近では政治や歴史の背後にうごめく“闇”のようなニュアンスを感じます。
近現代史研究家の辻田真佐憲(つじた・まさのり)氏の著書『空気の検閲 大日本帝国の表現規制』では、戦前、特に1928年から終戦までの時期に行われていた「検閲」についてまとめられています。実はこの時期の検閲と、メディアの「忖度」とは、切っても切れない相互作用がありました。今回は、こちらの書籍の内容をもとに、「忖度」と「検閲」の関係性について考えてみたいと思います。
戦前、皇室に対する不適切な表現や、反政府的な思想を煽る書物などは、軒並み発禁処分を受けました。この辺りは誰しも知っている部分だと思います。しかし、日々刊行される書籍は、そうしたマジメなものばかりではありません。昭和初期はエロ・グロ・ナンセンスが流行した時代。検閲官たちは、ただのエロ本や、猟奇的な描写のある小説・映画などを見て、「どこがどう卑猥か猥褻か」ということを真剣に指摘しなくてはなりませんでした。
世に溢れるメディア媒体に対して、検閲官の人数は1927年の段階で24名。取り締まりが強化された後でも100名を越えることはなかなかなかったようです。圧倒的な激務とブラックな環境。プライベートな時間も奪われる閲覧地獄で神経衰弱に陥り、病気休職する人も多かったのだとか…。この絶望的な人手不足と、戦争に向けて次第に厳しくなる検閲規準のなか、静かに進行していったのが「忖度」による自主検閲・自主規制でした。
なんとも滑稽なやりとりですが、同書では、そんな出版社と検閲官の間に、奇妙な連帯感が生まれていく様子を説明しています。発禁処分を食らってしまうと、メディア側にも痛手ですが、検閲官側にとっても、ただでさえ忙しい最中に発禁のための書類整備などに追われることになります。そこで、検閲官はメディアに圧力を強めていきます。「発禁にするぞ」と暗にプレッシャーをかけ、メディアは不利益を被りたくはありませんから、次第に利益が一致するようになるのです。
メディア側で行われる自主検閲・自主規制は、検閲官が行う「正規の規制」ではなく、「非正規の規制」です。辻田氏はこれを、タイトルにもなっている「空気の検閲」と呼んでいます。メディアは検閲官たちの意図、つまり空気を読み取り、セーフのラインを探して自主規制の姿勢を強めていったのです。
これは、戦争がはじまり、軍部が介入をはじめるよりも前に行われていたことです。非正規の規制は、公の記録には残りません。それは、作者や発信者の真の意図が、永遠にわからなくなるということでもあります。もしかすると、今も残っている当時の小説や書物には、「空気の検閲」がなされていたのかもしれません。そして、他国に比べても日本における検閲は、この非正規の検閲、つまり「空気の検閲」の割合が多かったと、辻田氏は指摘しています。
辻田氏は同書の中で、「検閲は面白く、恐ろしく、複雑なもの」と述べています。検閲は、一言ですべてが善・悪と判断できません。無論、政権批判に安直に繋がるテーマでもないのです。戦前の検閲の歴史、そして「空気の検閲」の実態を知ることは、表現のあり方、規制のあり方を、冷静に見つめる機会になるのではないでしょうか。
近現代史研究家の辻田真佐憲(つじた・まさのり)氏の著書『空気の検閲 大日本帝国の表現規制』では、戦前、特に1928年から終戦までの時期に行われていた「検閲」についてまとめられています。実はこの時期の検閲と、メディアの「忖度」とは、切っても切れない相互作用がありました。今回は、こちらの書籍の内容をもとに、「忖度」と「検閲」の関係性について考えてみたいと思います。
意外と笑える、戦前の検閲官たちの苦労
まず前提として、今の「日本国憲法」では書籍・映画などへの検閲が禁止されています。それは表現の自由を守るために揺らいではならない理念です。それを踏まえて、実際に戦前の検閲は何をしていたのでしょう?同書の冒頭で語られるのは、思いの外過酷で、どこか悲哀のある検閲官たちの仕事ぶりでした。戦前、皇室に対する不適切な表現や、反政府的な思想を煽る書物などは、軒並み発禁処分を受けました。この辺りは誰しも知っている部分だと思います。しかし、日々刊行される書籍は、そうしたマジメなものばかりではありません。昭和初期はエロ・グロ・ナンセンスが流行した時代。検閲官たちは、ただのエロ本や、猟奇的な描写のある小説・映画などを見て、「どこがどう卑猥か猥褻か」ということを真剣に指摘しなくてはなりませんでした。
世に溢れるメディア媒体に対して、検閲官の人数は1927年の段階で24名。取り締まりが強化された後でも100名を越えることはなかなかなかったようです。圧倒的な激務とブラックな環境。プライベートな時間も奪われる閲覧地獄で神経衰弱に陥り、病気休職する人も多かったのだとか…。この絶望的な人手不足と、戦争に向けて次第に厳しくなる検閲規準のなか、静かに進行していったのが「忖度」による自主検閲・自主規制でした。
「空気の検閲」が公の記録に残らないことの危うさ
しかしメディア側は、はじめから検閲に協力する姿勢ではありませんでした。むしろ出版物を通して検閲官をおちょくったりもしています。ある小説の例では、ラブシーンの場面にかかると、唐突に文章が中国語に変わるのです。「どうだ! 読めないだろう!」というわけです。すると、検閲官は中国語が堪能なスタッフを呼び、解読を試み発禁にするという具合でした。なんとも滑稽なやりとりですが、同書では、そんな出版社と検閲官の間に、奇妙な連帯感が生まれていく様子を説明しています。発禁処分を食らってしまうと、メディア側にも痛手ですが、検閲官側にとっても、ただでさえ忙しい最中に発禁のための書類整備などに追われることになります。そこで、検閲官はメディアに圧力を強めていきます。「発禁にするぞ」と暗にプレッシャーをかけ、メディアは不利益を被りたくはありませんから、次第に利益が一致するようになるのです。
メディア側で行われる自主検閲・自主規制は、検閲官が行う「正規の規制」ではなく、「非正規の規制」です。辻田氏はこれを、タイトルにもなっている「空気の検閲」と呼んでいます。メディアは検閲官たちの意図、つまり空気を読み取り、セーフのラインを探して自主規制の姿勢を強めていったのです。
これは、戦争がはじまり、軍部が介入をはじめるよりも前に行われていたことです。非正規の規制は、公の記録には残りません。それは、作者や発信者の真の意図が、永遠にわからなくなるということでもあります。もしかすると、今も残っている当時の小説や書物には、「空気の検閲」がなされていたのかもしれません。そして、他国に比べても日本における検閲は、この非正規の検閲、つまり「空気の検閲」の割合が多かったと、辻田氏は指摘しています。
現代も無縁ではない「空気の検閲」
現在、日本には正規の検閲システムはありませんが、「空気の検閲」は無縁ではありません。企業やメディアの、消費者からのクレームや回収をおそれた過度な自主規制は頻繁に行われています。日本という空気に内包されている、さまざまな意図や思想。極端になっていく社会の風潮。中立的意見が少しずつ口にしづらくなっているという息苦しさは、多くの人が感じているところではないでしょうか? そうした「忖度」によって、発言を萎縮してしまうということは、とても危ういことなのかもしれません。辻田氏は同書の中で、「検閲は面白く、恐ろしく、複雑なもの」と述べています。検閲は、一言ですべてが善・悪と判断できません。無論、政権批判に安直に繋がるテーマでもないのです。戦前の検閲の歴史、そして「空気の検閲」の実態を知ることは、表現のあり方、規制のあり方を、冷静に見つめる機会になるのではないでしょうか。
<参考文献>
・『空気の検閲 大日本帝国の表現規制』(辻田真佐憲著、光文社)
・『空気の検閲 大日本帝国の表現規制』(辻田真佐憲著、光文社)
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部










