テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
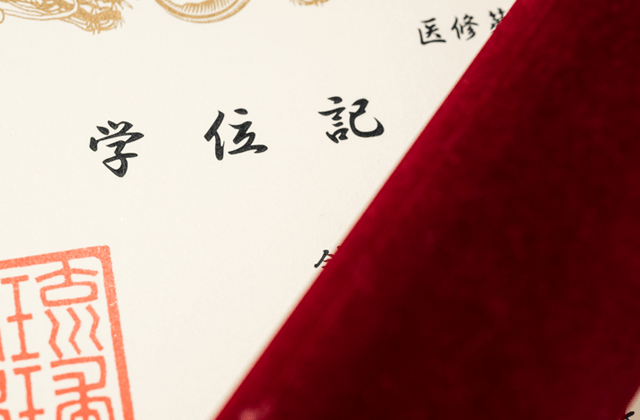
大学院を出るのは無駄なのか?院卒生の実情
2018年1月に公開された第一生命によるアンケート調査「大人になったらなりたいもの」では、「学者・博士」が男の子の1位となったそうです。「末は博士か大臣か」なんて言葉も、最近ではあまり聞かれなくなりましたが、子どもたちの間では夢のある職業として憧れの存在なのかもしれません。
しかしその一方で、厳しい現実が「学者・博士」を目指す人々にふりかかっています。
その後、すんなりと大学や企業の研究機関に入れるかというと、そうではありません。みなさんは「ポストドクター」という言葉をご存じでしょうか?「ポスト(後)・ドクター(博士)」、つまり博士号を取ったあとのことです。通称「ポスドク」と呼ばれ、正規の職員や研究者になるまでの期間のことを指しています。
ポスドクはさまざまな機関で募集されています。それこそ日本国内だけでなく、海外でも募集がかかっています。しかし、このポスドク機関は一般的にいうなら「非正規」の状態です。ある機関、あるプロジェクト内だけ雇用されるという就労形態なのです。その間に、大学教授になるためのポジションなど、安定して研究ができる場を見つけることになります。
では、受け皿として期待されていた企業で、大学院卒業者の採用が進まないのはなぜでしょうか?そもそも、企業が学生を採用する際、院卒と学部卒では、求めている要素が異なると考えられています。院卒には、ものごとを突き詰める能力や、専門的な知識。対して学部卒を採用する場合は、柔軟さや若さです。本来は、両者にそれぞれの利点があるはずなのですが、院卒の高度な専門性を、きちんと評価できるだけの企業・分野が少ないのです。
学部卒:男性20.59万円/女性20.00万円
院卒:男性23.17万円/女性22.97万円
院卒の方が男女差はなくなり、3万円ほど給与があがっています。しかし、学部の就職時期よりも院卒は2年以上遅れるとなると、実質的に学部卒と差が出ないという事実もあるようです。
しかし世界的に見ると、主導的な立場で活躍する人の多くは博士号取得者ということもまた事実です。スタッフの知人は博士号を取得し、現在はアメリカで正規の研究職についています。その人は、所謂一流の大学を出たわけでもなく、両親や親戚のコネクションも一切なかったそうです。ただ自分の夢を掴むために、子どものころから情熱を持ち続けたのだと語ってくれました。
あらゆることにコストパフォーマンスが求められる時代ですが、「知の力」はなかなか目に見える数値に表れません。また、得た知識が発揮されるには年月もかかります。それは個人も会社も同じです。「茨の道」と知識を求める人を脅すのではなく、そうした力を持った人材を、きちんと評価できる環境や雰囲気を作って行くことが大切なのではないでしょうか。
しかしその一方で、厳しい現実が「学者・博士」を目指す人々にふりかかっています。
博士号は「学者・博士」になるためのスタートライン
そもそも、「学者・博士」とはどうやってなるものなのでしょうか?一般的には、まず大学院に進学し博士号をとることが、研究者として活動するためのスタートラインとされています。一口に博士号といっても、2年間の修士課程(博士前期)を終え、3年の博士課程に進み、ようやく博士号取得というシステムです。その後、すんなりと大学や企業の研究機関に入れるかというと、そうではありません。みなさんは「ポストドクター」という言葉をご存じでしょうか?「ポスト(後)・ドクター(博士)」、つまり博士号を取ったあとのことです。通称「ポスドク」と呼ばれ、正規の職員や研究者になるまでの期間のことを指しています。
ポスドクはさまざまな機関で募集されています。それこそ日本国内だけでなく、海外でも募集がかかっています。しかし、このポスドク機関は一般的にいうなら「非正規」の状態です。ある機関、あるプロジェクト内だけ雇用されるという就労形態なのです。その間に、大学教授になるためのポジションなど、安定して研究ができる場を見つけることになります。
一般企業で院卒採用が増えない理由
90年代、欧米先進国と比べた日本の博士人材の少なさなどを理由に、「大学院重点化」政策がはじまりました。この頃から博士課程進学者は急増しますが、修了者に見合うだけの大学教員などの研究職ポストはなく、企業での採用もなかなか増えずじまい。昨今では高学歴ワーキングプアの問題も叫ばれています。ポスドクの人々の年齢は次第に上がっていき、一部の院卒者は学歴に見合わない薄給で労働に従事せざるを得ないという現状を生んでいます。では、受け皿として期待されていた企業で、大学院卒業者の採用が進まないのはなぜでしょうか?そもそも、企業が学生を採用する際、院卒と学部卒では、求めている要素が異なると考えられています。院卒には、ものごとを突き詰める能力や、専門的な知識。対して学部卒を採用する場合は、柔軟さや若さです。本来は、両者にそれぞれの利点があるはずなのですが、院卒の高度な専門性を、きちんと評価できるだけの企業・分野が少ないのです。
院卒と学部卒で初任給に差はあるの?
では院卒と学部卒で、就職後の給与の差などに違いはあるのでしょうか? 厚生労働省の行った「賃金構造基本統計調査」では、学歴別の初任給の平均データを次のようにまとめています。学部卒:男性20.59万円/女性20.00万円
院卒:男性23.17万円/女性22.97万円
院卒の方が男女差はなくなり、3万円ほど給与があがっています。しかし、学部の就職時期よりも院卒は2年以上遅れるとなると、実質的に学部卒と差が出ないという事実もあるようです。
「知の力」に価値を見出す
これだけ見ると、大学院を卒業することに突出した価値を見いだせないという人もいるかもしれません。高い学費に膨大な時間。費やしたものに対して、それ以上のペイバックは補償されるどころか、マイナスにまで落ち込むこともあるでしょう。では、大学院を出ることは無意味なのでしょうか?しかし世界的に見ると、主導的な立場で活躍する人の多くは博士号取得者ということもまた事実です。スタッフの知人は博士号を取得し、現在はアメリカで正規の研究職についています。その人は、所謂一流の大学を出たわけでもなく、両親や親戚のコネクションも一切なかったそうです。ただ自分の夢を掴むために、子どものころから情熱を持ち続けたのだと語ってくれました。
あらゆることにコストパフォーマンスが求められる時代ですが、「知の力」はなかなか目に見える数値に表れません。また、得た知識が発揮されるには年月もかかります。それは個人も会社も同じです。「茨の道」と知識を求める人を脅すのではなく、そうした力を持った人材を、きちんと評価できる環境や雰囲気を作って行くことが大切なのではないでしょうか。
<参考サイト>
・第一生命保険:第29回「大人になったらなりたいもの」調査結果を発表
http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2017_058.pdf
・厚生労働省:平成28年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/16/01.html
・第一生命保険:第29回「大人になったらなりたいもの」調査結果を発表
http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2017_058.pdf
・厚生労働省:平成28年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況:1 学歴別にみた初任給
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/16/01.html
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










