テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
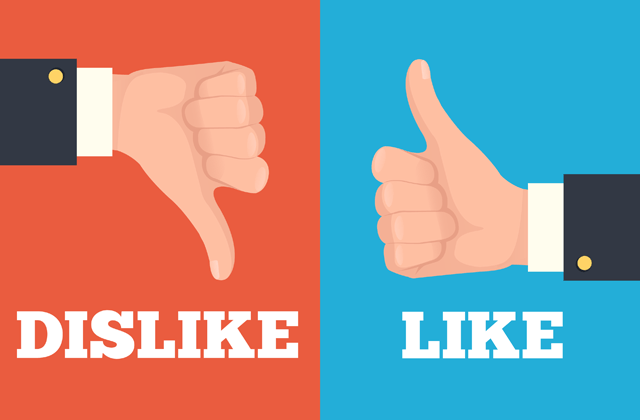
なぜ人には「好き嫌い」があるのか?
「およそ、人生とは趣味や嗜好をめぐる争いなのだ」と喝破したのはドイツの偉大な哲人フリードリヒ・ニーチェですが、彼が言うように、私たちの人生を大きく左右する「好き嫌い」とは、そもそもいったいなぜあるのでしょうか。
どうして、どのように「好き嫌い」は形成されるのでしょう。この問いに対して明快な正解をもっているひとはおそらく存在しないのでは。要するに、超難題というわけです。とはいえ、そう簡単に引き下がるわけにもいきません。これについて考えるためのヒントはいくつか提起されています。
そこで、とっておきの一冊『好き嫌い――行動科学最大の謎』をもとに、「好き嫌い」の謎、すなわち本書のサブタイトルにもあるように「行動科学最大の謎」をひも解いていきたいとおもいます。
たとえば、好きな色はどうやって決まるのかを考えてみましょう。人間の避けられない欲求に食欲があります。そのことを考慮すると、食べ物の「好き嫌い」は比較的早期に形成されると言っていいでしょう。「好きな食べ物」が決まると、日常的にその「好きな食べ物」を食べる機会が増えます。
「色」という視点からみると、「好きな食べ物の色」を見る機会も自然と増えます。上述したように、「好み」は選択したものに影響を受けます。繰り返し「好きな食べ物の色」を見るうちに、いつのまにか、その色が「好きな色」になっているということが起こるのだそうです。
そんなわけで、自己演出的に好みを固定化しようとします。ただし、「自己同一性」というのは、言ってしまえば、単なる「思い込み」でもあるわけで、だんだんと「行動」と「思考」にズレが生じてきます。「行動」は本能的で、「思考」は分析的なはたらきです。
そこから導き出される結論は、ウェブの評価はあまり信用できないということです。
ウェブのレビューや口コミについてもすこし補足すると、ユーザーは最初に下されたレビューに大きく影響を受けることもわかっています。フェイクであれ何であれ、言ったもの勝ちというのが、ウェブレビューの現実なのです。
みなさんはどんな「好き嫌い」がありますか。『好き嫌い――行動科学最大の謎』の帯文を書いている楠木建氏は『「好き嫌い」と才能』『「好き嫌い」と経営』の著者であり、本書において、経営のセンスも才能もその源泉は、それぞれの固有の「好き嫌い」にあることを述べています。「好きこそものの上手なれ」というわけです。
行動科学最大の謎
好きな色、好きな食べ物、好きな動物、好きな人…などなど、どんな人にも「好き嫌い」はかならずあります。たとえ「無趣味」「無趣向」を断言している人がいたとしても、なにかを判断する際に「好み」は避けて通れません。意識しているかどうかはまた別の話です。どうして、どのように「好き嫌い」は形成されるのでしょう。この問いに対して明快な正解をもっているひとはおそらく存在しないのでは。要するに、超難題というわけです。とはいえ、そう簡単に引き下がるわけにもいきません。これについて考えるためのヒントはいくつか提起されています。
そこで、とっておきの一冊『好き嫌い――行動科学最大の謎』をもとに、「好き嫌い」の謎、すなわち本書のサブタイトルにもあるように「行動科学最大の謎」をひも解いていきたいとおもいます。
選択は好みの影響を受けるが、好みも選択の影響を受ける
ひとつ結論めいたことを言えば、人は何かを選択するとき、間違いなく「好み」の影響を受けるわけですが、その逆も同じように起こります。つまり、「好み」は選択したものに影響を受けるということです。たとえば、好きな色はどうやって決まるのかを考えてみましょう。人間の避けられない欲求に食欲があります。そのことを考慮すると、食べ物の「好き嫌い」は比較的早期に形成されると言っていいでしょう。「好きな食べ物」が決まると、日常的にその「好きな食べ物」を食べる機会が増えます。
「色」という視点からみると、「好きな食べ物の色」を見る機会も自然と増えます。上述したように、「好み」は選択したものに影響を受けます。繰り返し「好きな食べ物の色」を見るうちに、いつのまにか、その色が「好きな色」になっているということが起こるのだそうです。
「自分はこれが好きなんだ」と思い込みたい
興味深いことに、私たちは好みが決まると、その好みに固執しようとします。要するに「自分はこれが好きなんだ」と思い込もうとするのです。アイデンティティが「自己同一性」を意味することからもわかるように、私たち人間は「自分は、○○な人間です」という統合された自己を求めます。それが曖昧になると不安になってしまいます。そんなわけで、自己演出的に好みを固定化しようとします。ただし、「自己同一性」というのは、言ってしまえば、単なる「思い込み」でもあるわけで、だんだんと「行動」と「思考」にズレが生じてきます。「行動」は本能的で、「思考」は分析的なはたらきです。
そこから導き出される結論は、ウェブの評価はあまり信用できないということです。
「☆」の数(レーティング)は信用できない?
いま、ウェブ社会は「☆」の数で評価するレーティングやランキングに溢れていますが、じつはそれらはユーザーの本当の好みを反映しているとはかぎりません。つまり、多くのユーザーが「自己演出的」に評価をくだしている可能性がかなり高いのです。ウェブのレビューや口コミについてもすこし補足すると、ユーザーは最初に下されたレビューに大きく影響を受けることもわかっています。フェイクであれ何であれ、言ったもの勝ちというのが、ウェブレビューの現実なのです。
好き嫌いとビジネスセンス
さて、摩訶不思議な「好き嫌い」の謎が多少は明らかになったのではないでしょうか。まだまだ紹介したいことはあるのですが、それはまた別の機会にとっておきましょう。ここまで、どうして「好き嫌い」は形成されるのか、というやや哲学的な問いについてご案内してきましたが、私たちが生きるうえでもっと大事なことは自分がどんな「好き嫌い」をもっているかということです。みなさんはどんな「好き嫌い」がありますか。『好き嫌い――行動科学最大の謎』の帯文を書いている楠木建氏は『「好き嫌い」と才能』『「好き嫌い」と経営』の著者であり、本書において、経営のセンスも才能もその源泉は、それぞれの固有の「好き嫌い」にあることを述べています。「好きこそものの上手なれ」というわけです。
<参考文献>
・『好き嫌い――行動科学最大の謎』 (トム ヴァンダービルト著、桃井緑美子翻訳、早川書房)
・『「好き嫌い」と才能』(楠木建著、東洋経済新報社)
・『「好き嫌い」と経営』(楠木建著、東洋経済新報社)
・『好き嫌い――行動科学最大の謎』 (トム ヴァンダービルト著、桃井緑美子翻訳、早川書房)
・『「好き嫌い」と才能』(楠木建著、東洋経済新報社)
・『「好き嫌い」と経営』(楠木建著、東洋経済新報社)
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










