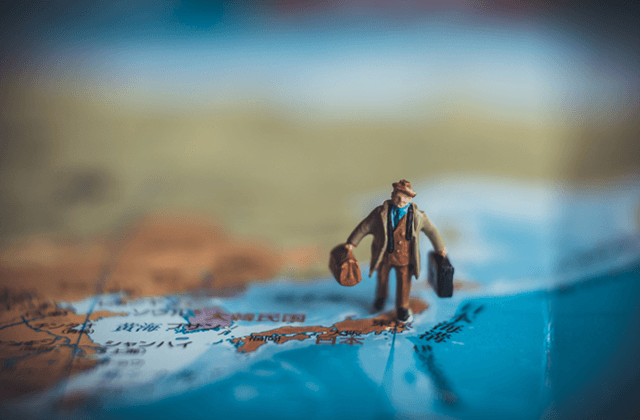
世界の「親日国」とその理由
世界にはさまざまな国があり、国連加盟国でも193カ国あり(2018年8月現在)、そのなかにはたくさんの「親日」国があります。
科学ジャーナリスト・ノンフィクション作家で、統計学の分野でも活躍する佐藤拓氏は、236ものデータを徹底的に読み解き親日度を計った『親日国の世界地図』において、「国民のおよそ八割以上が親日的で、反日派が一割に満たない」世界で最も親日的な6カ国として、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、台湾を挙げています。
ではなぜこれらの国は親日的なのでしょうか。上記の6カ国をはじめ、世界の「親日」国を取り上げ、その理由を考えてみたいと思います。
一方、インドネシアと同じく日本が最大の援助国であるベトナムやフィリピンにおいても親日感情はとても高く、とくにベトナムでは、2015年に米調査機関が実施した対日好感度の三国の比較でも「とても好き」と答えた人の割合が50%と、かなり多い結果がでています(「どちらかといえば好き」は32%で、合計すると82%)。なお、フィリピンの「とても好き」は28%・「どちらかといえば好き」は53%で、インドネシアの「とても好き」は29%・「どちらかといえば好き」は42%でした。
他方、タイにおける対日信頼度は、2016年の外務省の世論調査結果、「信頼できる」42%、「どちらかといえば信頼できる」42%、「どちらでもない」14%、「どちらかといえば信頼できない」1%、「わからない」1%をみれば、信頼度が高いことがよくわかります。他にもタイと日本には、東南アジアで欧米の植民地にならずに独立を保ったことや王室・皇室を戴いているなどいくつかの共通点があることも、親日感情を高める要因であるといわれています。
タイと同じくマレーシアの対日信頼度も、2016年の外務省の世論調査結果をみると「信頼できる」37%、「どちらかといえば信頼できる」47%、「どちらでもない」13%、「どちらかといえば信頼できない」1%、「わからない」2%と、信頼度が高いことがよくわかります。また、その背景には、マレーシアを22年にわたって率いてきた親日家のマハティール元首相による、日本や韓国に学び経済開発を進めようとする「ルック・イースト」政策等の影響も大きいとも考えられています。
そして、台湾の親日度の高さも広く知られています。調査の方法により多少結果は異なりますが、一つの例として2016年に日本台湾交流協会がおこなった「台湾が世界でいちばん好きな国」の一国選択の世論調査では、2位の「中国」6%に対し、「日本」56%というダントツの結果がでています。
台湾は1895年から50年間、日本の統治下にありました。その際、台湾総督府民政局長を務めた後藤新平を中心に公道整備・鉄道敷設、下水道整備・伝染病対策、砂糖・樟脳・煙草等の増産といった政策や、土木技術者の八田与一によるダム建設による嘉南平原の穀倉地帯化といった功績により、近代化が進められました。その頃から新日感情は高く、2011年の東日本大震災の際、お見舞いのメッセージとともに200億円を超す巨額の義援金や救援金、レスキュー隊や支援物資をいち早く大量に届けてくれました。
例えば江戸時代から良好な外交関係をもっていたオランダですが、1)アジア・太平洋戦争によって親日感情は低下していました。しかし、2)戦後の平和外交の努力、特に9)皇室外交として2000年に今上天皇・皇后両陛下のご訪問により親日感情は、当時のオランダ特命全権大使であった池田維氏によると、「劇的に改善」したといいます。
また親日国といわれるトルコには、8)二国間の特別な歴史的事件として、1890年の軍艦エルトゥールル号座礁の際に日本人が救助し日本海軍が送り届けた史実と、その95年後の1985年に「恩返し」としてトルコ政府がイラン・イラク戦争時に在留邦人の救出を行った事実があります。
その中の一国に、ソ連崩壊により1991年に独立したウズベキスタンがあります。ウズベキスタンでは日本人はめったに見かけることはないそうですが親日的な国といわれ、「たまに日本人がいると記念撮影を求められるほど」だそうです。ウズベキスタンが親日国になった背景には、アジア・太平洋戦争終結後に抑留された457人の日本人捕虜と、彼らが首都タシケントに建設したオペラハウス「ナボイ劇場」の存在があります。
強制労働なうえ粗末な食事しか与えられず、休みもほとんどなかった現場でも、彼らは日本兵収容所の隊長をつとめた永田行夫を中心に“和”の精神をもって働き、一切の手抜きをすることなく、ウズベク人とも協力して、“ソ連四大劇場”と讃えられた中央アジア最大のオペラハウスを完成させました。
その真価は、建設から20年たった1966年、タシケントを見舞った震度8の大地震の際にも発揮されました。街はほぼ全壊しましたがナボイ劇場は無傷でした。集まった人々はみんな、息を呑むほどに驚き、絶好の避難場所ともなりました。また、無傷のナボイ劇場は瞬くうちにウズベキスタン国内や隣接するキルギス、カザフスタン、トルクメニスタン、タジキスタンなど中央アジア各国にも伝わり、「シルクロードの“日本人伝説”」となったといいます。
そしてもう一人、ウズベキスタンと日本をつないだ代表的な人物に、文化人類学者・国立民族学博物館名誉教授の加藤九祚がいます。65歳で、シルクロードの要所として栄えた三蔵法師ゆかりの地でもあるウズベキスタンのテルメズで遺跡発掘を開始し、見事仏教遺跡の発掘に成功しました。
その功績はウズベキスタンの小学校の教科書にも取り上げられ、「ウズベクの人びともまた、彼を敬愛するがゆえに“ドラム=先生”とよんでいる」と讃えられ、訃報の際にはウズベキスタン政府が「国民にとって大きな損失」と悼み、大きく報道されたといいます。
いかがでしたでしょうか。馴染み深い国から少し縁遠く思える国まで、さまざまな「親日」国をみてきました。その背景には先人たちの努力と功績と交流がありました。大切に守り、そして新たに育みながら、未来にもつなげていくことが肝要です。
科学ジャーナリスト・ノンフィクション作家で、統計学の分野でも活躍する佐藤拓氏は、236ものデータを徹底的に読み解き親日度を計った『親日国の世界地図』において、「国民のおよそ八割以上が親日的で、反日派が一割に満たない」世界で最も親日的な6カ国として、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、マレーシア、台湾を挙げています。
ではなぜこれらの国は親日的なのでしょうか。上記の6カ国をはじめ、世界の「親日」国を取り上げ、その理由を考えてみたいと思います。
世界の「親日」国・トップ6と日本の関係
まずインドネシアを取り上げてみましょう。2016年の外務省の調査によると、「日本を信頼できる」理由として、第一に「ODAなどによる経済的貢献」が挙げられていることから、「日本が長期にわたって最大の援助国であり続けてきたことが親日感情につながっているといえる」と、佐藤氏は述べています。またアジア・太平洋戦争の残留日本兵が独立に大きな貢献をしたことも大きな要因と考えられています。一方、インドネシアと同じく日本が最大の援助国であるベトナムやフィリピンにおいても親日感情はとても高く、とくにベトナムでは、2015年に米調査機関が実施した対日好感度の三国の比較でも「とても好き」と答えた人の割合が50%と、かなり多い結果がでています(「どちらかといえば好き」は32%で、合計すると82%)。なお、フィリピンの「とても好き」は28%・「どちらかといえば好き」は53%で、インドネシアの「とても好き」は29%・「どちらかといえば好き」は42%でした。
他方、タイにおける対日信頼度は、2016年の外務省の世論調査結果、「信頼できる」42%、「どちらかといえば信頼できる」42%、「どちらでもない」14%、「どちらかといえば信頼できない」1%、「わからない」1%をみれば、信頼度が高いことがよくわかります。他にもタイと日本には、東南アジアで欧米の植民地にならずに独立を保ったことや王室・皇室を戴いているなどいくつかの共通点があることも、親日感情を高める要因であるといわれています。
タイと同じくマレーシアの対日信頼度も、2016年の外務省の世論調査結果をみると「信頼できる」37%、「どちらかといえば信頼できる」47%、「どちらでもない」13%、「どちらかといえば信頼できない」1%、「わからない」2%と、信頼度が高いことがよくわかります。また、その背景には、マレーシアを22年にわたって率いてきた親日家のマハティール元首相による、日本や韓国に学び経済開発を進めようとする「ルック・イースト」政策等の影響も大きいとも考えられています。
そして、台湾の親日度の高さも広く知られています。調査の方法により多少結果は異なりますが、一つの例として2016年に日本台湾交流協会がおこなった「台湾が世界でいちばん好きな国」の一国選択の世論調査では、2位の「中国」6%に対し、「日本」56%というダントツの結果がでています。
台湾は1895年から50年間、日本の統治下にありました。その際、台湾総督府民政局長を務めた後藤新平を中心に公道整備・鉄道敷設、下水道整備・伝染病対策、砂糖・樟脳・煙草等の増産といった政策や、土木技術者の八田与一によるダム建設による嘉南平原の穀倉地帯化といった功績により、近代化が進められました。その頃から新日感情は高く、2011年の東日本大震災の際、お見舞いのメッセージとともに200億円を超す巨額の義援金や救援金、レスキュー隊や支援物資をいち早く大量に届けてくれました。
親日感情を生み出してきた要素とは?
佐藤氏は親日感情を生み出してきた要素として、1)アジア・太平洋戦争(反日感情)、2)戦後の平和外交、3)経済大国への成長、4)経済・技術支援、5)科学技術および工業製品の信頼度、6)日系人の功績、7)日露戦争での勝利、8)二国間の特別な歴史的事件、9)皇室外交、の9点の要素を挙げています。例えば江戸時代から良好な外交関係をもっていたオランダですが、1)アジア・太平洋戦争によって親日感情は低下していました。しかし、2)戦後の平和外交の努力、特に9)皇室外交として2000年に今上天皇・皇后両陛下のご訪問により親日感情は、当時のオランダ特命全権大使であった池田維氏によると、「劇的に改善」したといいます。
また親日国といわれるトルコには、8)二国間の特別な歴史的事件として、1890年の軍艦エルトゥールル号座礁の際に日本人が救助し日本海軍が送り届けた史実と、その95年後の1985年に「恩返し」としてトルコ政府がイラン・イラク戦争時に在留邦人の救出を行った事実があります。
シルクロードの“日本人伝説”
上記に取り上げた国以外にも、たくさんの親日国があります。『「あの国」はなぜ、日本が好きなのか』ではそのうちの約60カ国を取り上げ、日本とのエピソードやキーパーソンとなった方々を紹介しています。その中の一国に、ソ連崩壊により1991年に独立したウズベキスタンがあります。ウズベキスタンでは日本人はめったに見かけることはないそうですが親日的な国といわれ、「たまに日本人がいると記念撮影を求められるほど」だそうです。ウズベキスタンが親日国になった背景には、アジア・太平洋戦争終結後に抑留された457人の日本人捕虜と、彼らが首都タシケントに建設したオペラハウス「ナボイ劇場」の存在があります。
強制労働なうえ粗末な食事しか与えられず、休みもほとんどなかった現場でも、彼らは日本兵収容所の隊長をつとめた永田行夫を中心に“和”の精神をもって働き、一切の手抜きをすることなく、ウズベク人とも協力して、“ソ連四大劇場”と讃えられた中央アジア最大のオペラハウスを完成させました。
その真価は、建設から20年たった1966年、タシケントを見舞った震度8の大地震の際にも発揮されました。街はほぼ全壊しましたがナボイ劇場は無傷でした。集まった人々はみんな、息を呑むほどに驚き、絶好の避難場所ともなりました。また、無傷のナボイ劇場は瞬くうちにウズベキスタン国内や隣接するキルギス、カザフスタン、トルクメニスタン、タジキスタンなど中央アジア各国にも伝わり、「シルクロードの“日本人伝説”」となったといいます。
そしてもう一人、ウズベキスタンと日本をつないだ代表的な人物に、文化人類学者・国立民族学博物館名誉教授の加藤九祚がいます。65歳で、シルクロードの要所として栄えた三蔵法師ゆかりの地でもあるウズベキスタンのテルメズで遺跡発掘を開始し、見事仏教遺跡の発掘に成功しました。
その功績はウズベキスタンの小学校の教科書にも取り上げられ、「ウズベクの人びともまた、彼を敬愛するがゆえに“ドラム=先生”とよんでいる」と讃えられ、訃報の際にはウズベキスタン政府が「国民にとって大きな損失」と悼み、大きく報道されたといいます。
いかがでしたでしょうか。馴染み深い国から少し縁遠く思える国まで、さまざまな「親日」国をみてきました。その背景には先人たちの努力と功績と交流がありました。大切に守り、そして新たに育みながら、未来にもつなげていくことが肝要です。
<参考文献>
・『親日国の世界地図』(佐藤拓著、祥伝社新書)
・『「あの国」はなぜ、日本が好きなのか』(「ニッポン再発見」倶楽部、知的生きかた文庫)
・『日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた』(嶌信彦著、KADOKAWA)
・『親日国の世界地図』(佐藤拓著、祥伝社新書)
・『「あの国」はなぜ、日本が好きなのか』(「ニッポン再発見」倶楽部、知的生きかた文庫)
・『日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた』(嶌信彦著、KADOKAWA)
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子







